脳腸相関とは?メカニズムからセロトニン・自律神経・睡眠との関係まで徹底解説!
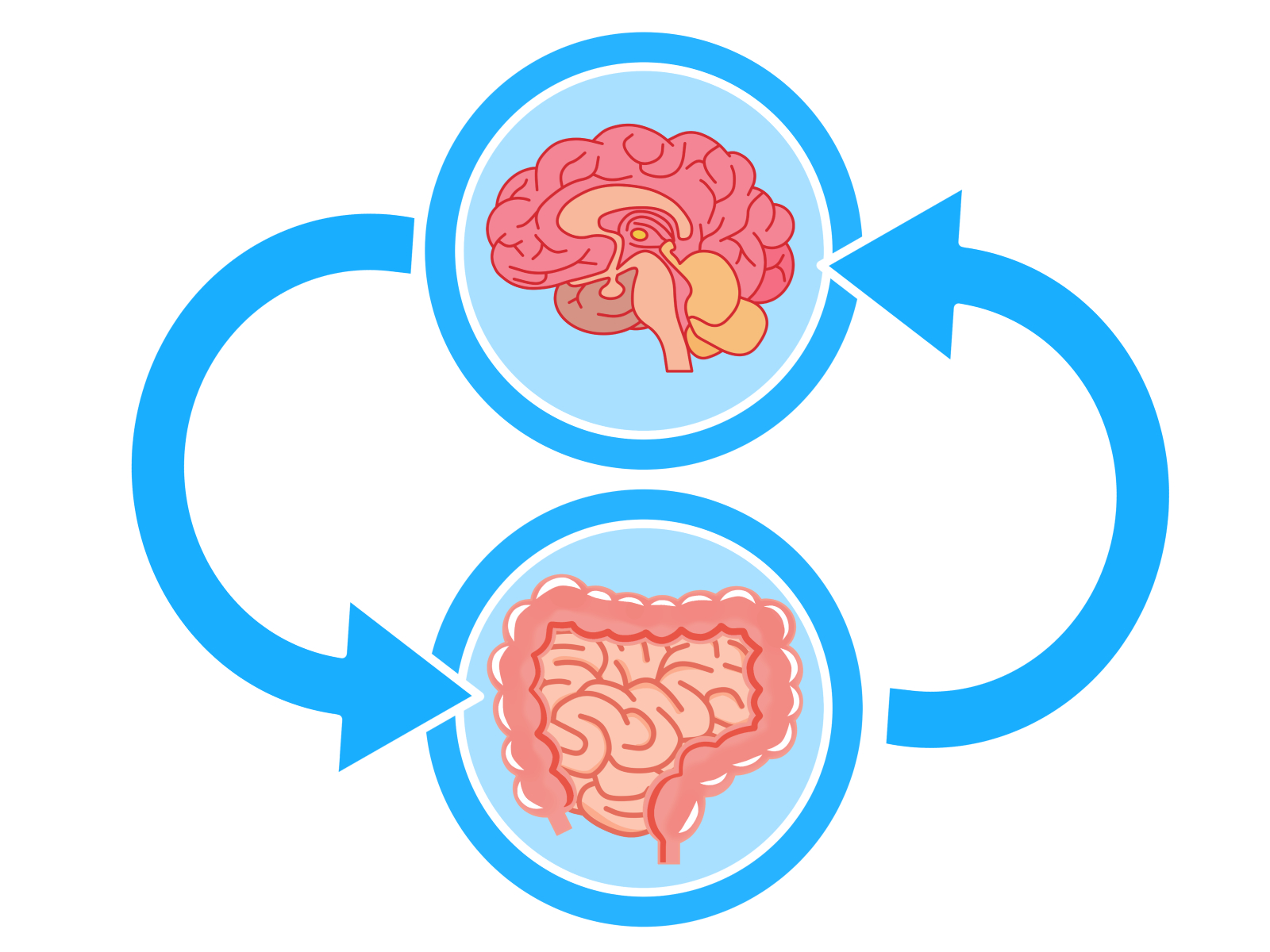
「脳腸相関ってよく聞くけれど、具体的にどういう仕組みなの?」「腸と脳が関係しているって本当?」「自律神経やセロトニン、睡眠とどうつながっているのか知りたい!」そう思う方もいるかもしれません。実は、脳と腸は密接に関係しており、自律神経系や腸内細菌の代謝物を通じて相互に影響を与えています。腸内環境が脳の働きやメンタルに影響を及ぼすこともわかっており、睡眠の質にも関係がある事が研究されています。この記事では、脳腸相関のメカニズムをわかりやすく解説し、セロトニンや自律神経、睡眠との関係について詳しく紹介します。健康維持のために脳腸相関をどのように整えればよいのか、具体的な方法についても解説していきます。
※研究開発コラムは微生物を活用した研究開発において参考になるトピックを集めたもので、全てのテーマについて当社が研究開発を実施しているわけではございません。
目次
脳腸相関とは?基本的な仕組みと重要性
脳腸相関は、脳と腸の間に存在する双方向のコミュニケーションネットワークを指します。この相関関係は、神経系(神経伝達物質を介した電気信号:早い一時的な情報伝達)、内分泌系(ホルモンなど遅い長時間作用する情報伝達)、免疫系(ストレスなどに対する生体防御のための情報伝達)を通じて形成され、脳と腸が互いに影響を及ぼし合うことを示しています。近年の研究により、脳腸相関が精神的健康や身体的健康において重要な役割を果たすことが明らかになっています。
脳腸相関の定義
脳腸相関は、脳と腸の間の相互作用を示す概念であり、特に腸内細菌叢(マイクロバイオーム)がこの相関において重要な役割を果たしています。腸内には数兆個の微生物が存在し、これらは腸の健康だけでなく、全身の健康にも関わり、脳の機能にも影響を与えることが知られています。例えば、腸内細菌は腸内における神経伝達物質の合成に関与し、神経伝達物質の一種であるセロトニンの約90%が腸管で生成され腸で作用することが報告されていますが、腸内細菌が作る短鎖脂肪酸の刺激によって腸クロム陽性細胞(EC細胞)がセロトニンを合成する事が知られています。そして腸の求心性迷走神経末端にこのセロトニンが作用する事で延髄孤束核(脳への情報中継地)を通じ脳へ情報を伝える経路が存在する事が報告されており、腸内環境が脳の健康に間接的な影響を与えることが示唆されています。
さらに、脳腸相関はストレス応答や感情調節にも関与しています。ストレスが腸内環境に悪影響を及ぼすことがあり、逆に腸内の健康状態が脳のストレス応答に影響を与えることもあります。これにより、腸内の健康がメンタルヘルスにおいて重要な要素であることが示されています。
参考:
須藤信行「ストレスと腸内フローラ」(腸内細菌学雑誌 19 2005)
鈴木チセ「社会的敗北ストレスが腸内エコシステムに与える影響」(腸内細菌学雑誌 vol.31 2017)
なぜ脳と腸はつながっているのか?
脳と腸がつながっている理由は、進化的な観点からも説明できます。ヒトをはじめ哺乳類の中枢神経系(脳)は、腸管神経系が進化したものと考えられています。脳と腸は共に生存に不可欠な機能を持っており、食物の摂取や消化、栄養の吸収、さらには危険からの回避に関与しています。脳は腸の状態を監視し、腸は脳に対してその状態を報告することで、身体全体のバランスを保つ役割を果たしています。また進化的には脳は腸管神経系から生じていますが、この神経系の進化的形成過程に腸の共生細菌である、腸内細菌の持つ菌同士の情報伝達物質が関与している可能性が示唆されています。具体的には、カテコラミン、ヒスタミン、アセチルコリンなどの神経伝達物質の合成酵素が最近からヒトに水平伝播されたという説があります。
これらの腸内細菌-腸-神経系の相互作用は、主には迷走神経を通じて行われます。迷走神経は脳と腸を直接結びつける主要な神経経路であり、腸からの信号が大量に脳に伝達されることで、食欲や消化、さらには感情に影響を与えます。例えば、腸内に炎症が起こっている場合、その情報を脳に信号として送ることで、ストレスや不安感が増加することがあるため、腸の健康がメンタルヘルスにおいて重要であることが示されています。
また、腸内細菌は免疫系とも密接に関連しており、腸内の微生物バランスが免疫応答に影響を与えることが知られています。腸内の健康が免疫系を通じて脳に影響を与えることで、精神的な健康状態にも影響を及ぼす可能性があります。最近の研究では、腸内細菌のバランスがうつ病や不安障害に関連していることが示されており、腸内環境の改善がメンタルヘルスの向上に寄与する可能性があることが示唆されています。
このように、脳腸相関は脳と腸の間の複雑な相互作用を示すものであり、腸内環境が脳の健康に与える影響は多岐にわたります。今後の研究により、脳腸相関のメカニズムがさらに解明されることで、メンタルヘルスや身体的健康の改善に向けた新たなアプローチが期待されます。
参考:
西田憲生「腸内細菌の良好な環境が自律神経のバランスを整える」(ヘルシスト vol.288 2024年11月10日号)
須藤信行「腸内細菌と脳腸相関」(福岡醫學雑誌 vol.100 No.9 2009)
脳腸相関のメカニズム:セロトニン・自律神経との関係
脳腸相関は、脳と腸の間の双方向のコミュニケーションを指し、精神的および身体的健康において重要な役割を果たしています。この相関関係は、腸内細菌叢代謝産物や神経系、内分泌系、神経内分泌系、免疫系などのクロストークで複雑に制御されていますが、一般的に分かりやすい例としてセロトニンと自律神経系の働きが脳腸相関のメカニズムの一例として紹介されています。以下では、セロトニンと腸の関係、自律神経と脳腸相関の関係について詳しく説明しますが、その中でも特に脳腸相関が病態の中心をなす疾患として、IBS(過敏性腸症候群)とセロトニンに関する研究を紹介します。

セロトニンと腸の関係
セロトニンの働きとは?
セロトニンは、神経伝達物質の一種であり、主に脳内で気分や感情の調整に関与しています。セロトニンは、幸福感や満足感をもたらす重要な役割を果たし、うつ病や不安障害の治療においても注目されています。中枢神経系では不安や恐怖の惹起と関連し、扁桃体や情動制御に関連する視床下部、海馬などに高濃度に存在していますが、腸では粘膜に存在し、実に全身の90%のセロトニンが腸で生産されています。
腸で作られるセロトニンの役割
腸内で生成されるセロトニンは、腸の運動を調整する役割を果たしています。具体的には、腸の平滑筋を収縮させ、消化を促進することで、食物の移動を助けます。また、腸内のセロトニンは、腸内細菌と相互作用し、腸内環境を整える役割も果たしています。最近の研究では、腸内のセロトニンが脳に信号を送ることで、食欲や気分に影響を与えることが明らかになっています。
IBS(過敏性腸症候群)とセロトニン
近年の研究で、難治性の消化器疾患として知られるIBSにセロトニン関連薬が有効であることが分かってきました。IBS患者では通常人では何の影響もないストレスにも過敏に反応し、腸の蠕動運動異常を起こしますが、セロトニンはこのストレスに対する情動と、消化管運動の両方に関わる重要な神経伝達物質です。セロトニンの受容体はいくつかの種類がありますが、それぞれ役割が異なっておりIBSの症状(不安、大腸運動亢進、内臓知覚過敏)を示すモデルマウスにあるセロトニン受容体の刺激薬を与えると、この症状が改善されることが示されています。また脳の可塑性(成長期における脳の発達時期で、神経細胞同士の連絡(シナプス)の形成が一時的に過形成される時期)に同じセロトニン受容体を阻害する薬を投与すると、シナプスの形成が低下し、セロトニン神経回路の機能的異常を起こして成長後のストレス負荷に対する耐性が低下する事が示唆されています。つまりセロトニンは、IBSの消化管症状と、IBSの原因の一つなる中枢性の機能異常形成どちらにも関与している事が分かってきています。また他のセロトニン受容体は消化管平滑筋や筋層間神経叢に主に見られ、消化管機能や内臓知覚に関与していますが、これらの受容体刺激薬をIBS患者に投与する事で腹痛や下痢、便秘などの症状を抑制する事が報告されています。
参考:
谷莉ら「過敏性腸症候群とセロトニン」(心身医 vol.50 No.1 2010)
自律神経と脳腸相関の関係
自律神経系は、体の無意識的な機能を調整する神経系であり、交感神経と副交感神経の2つの部分から構成されています。脳腸相関において、自律神経系は腸の機能に大きな影響を与えます。一例では、腸内細菌叢等のバランス悪化(dysibiosis)が腸管腔内環境の変化を誘発し、腸粘膜上皮における炎症反応を起こして自律神経求心路あるいは消化管ホルモンや炎症性サイトカインを介して脳機能変化を誘発し,消化器症状を起こす事が推測されています。
自律神経のバランスが脳腸相関に与える影響
自律神経のバランスが崩れると、腸の機能にも悪影響を及ぼすことが知られています。例えば、ストレスがかかると交感神経が優位になり、腸の動きが抑制されることがあります。これにより、便秘や腹痛などの消化器系の問題が引き起こされることがあります。逆に、副交感神経が優位になると、腸の動きが活発になり、消化が促進されます。このように、自律神経のバランスは脳腸相関において重要な役割を果たしており、自律神経のバランスの乱れで起こる消化管症状は近年では機能性消化管障害と呼ばれ、特に機能性ディスペプシア(FD)、過敏性腸症候群(IBS)といった消化管疾患で自律神経と脳腸相関の研究が進められています。ストレス管理やリラクゼーションが腸の健康に寄与することが示されています。
参考:
本郷道夫「自律神経と消化器症状」(自律神経 vol.58 2021)
大島忠之ら「ストレスと機能性消化管障害」(日職災医誌 vol.63 2015)
腸内環境と脳の健康の関係とは?
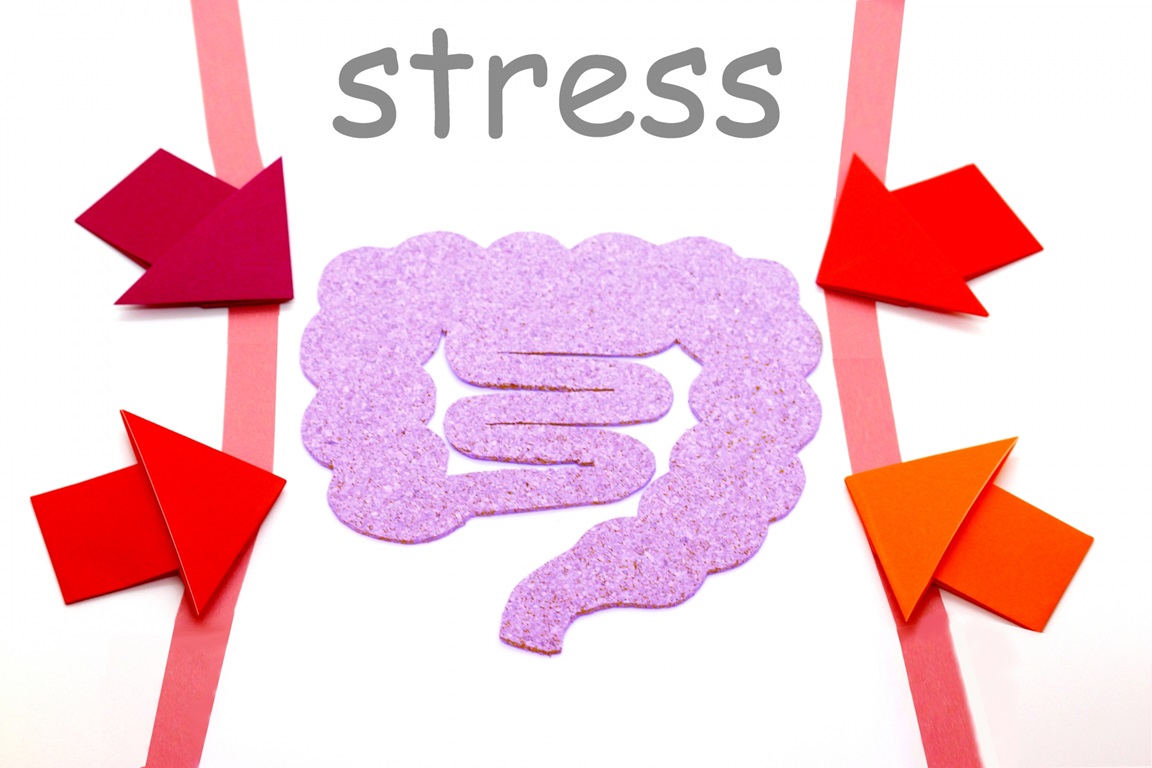
腸内環境は、私たちの健康において重要な役割を果たしています。特に、腸内細菌と脳の健康との関係は、近年の研究によって注目されています。腸内細菌は、腸内での消化や栄養吸収だけでなく、脳の機能にも影響を与えることが示されています。この関係は「腸脳相関」と呼ばれ、腸内環境が脳の健康に及ぼす影響についての理解が深まっています。
腸内細菌が脳に与える影響
腸内細菌は、神経伝達物質の合成や免疫系の調整に関与しており、これが脳の健康に影響を与えることが分かっています。例えば、腸内細菌は腸内のセロトニンの合成に関与しており、腸内のセロトニンは迷走神経を介し気分や感情の調整に役割を果たします。研究によると、ある種の乳酸菌を投与したマウスはストレス惹起性不安・抑うつ行動が減弱しますが、これは迷走神経を切除したマウスでは見られない事から、この乳酸菌によるメンタルへの効果は腸からの迷走神経を介して作用する事が確かめられています。腸内細菌のバランスが崩れるdysbiosisと呼ばれる病態では、体内で微細炎症環境が形成され、炎症性サイトカインなどの透過性が亢進し、それらが脳血液関門を通り中枢に作用する事でうつ病や不安障害のリスクが高まることが示されています。さらに、腸内細菌は短鎖脂肪酸(SCFA)を生成します。SCFAは腸内の炎症を抑える効果があり、脳の健康にも寄与します。特に、酪酸は神経保護作用があり、神経細胞の成長を促進することが知られています。腸内環境が良好であれば、これらの有益な物質が十分に生成され、脳の健康を維持する助けとなります。また、腸内細菌は腸-脳軸を介して脳に信号を送ることができます。腸内の状態が脳に影響を与えるメカニズムとして、先程の腸からの迷走神経系を介した中枢への情報伝達の他に、腸内細菌が産生する代謝物質(アミン類など)が血流を介して脳に到達し、神経伝達物質の放出や神経炎症に影響を与えることが考えられています。これにより、腸内環境が脳の機能や行動に直接的な影響を及ぼすことが示唆されています。
参考:
須藤信行「ストレスと腸内フローラ」(腸内細菌学雑誌 19 2005)
本郷道夫「腸内細菌と精神神経疾患からみる腸脳相関」(心身医学 vol.62 No.6 2022)
宇佐美眞ら「多様な酪酸投与とその効果」(甲南女子大学研究紀要Ⅱ vol.13 2019)
腸内環境を悪化させる要因とは?
腸内環境は、さまざまな要因によって悪化する可能性があります。まず、食生活が大きな影響を与えます。高脂肪食や高糖質食は、腸内細菌のバランスを崩し、悪玉菌の増殖を促進します。これにより、腸内の炎症が引き起こされ、脳の健康にも悪影響を及ぼすことが報告されています。さらに、ストレスも腸内環境に悪影響を与える要因の一つです。ストレスは腸内のバリア機能を低下させ、腸内細菌のバランスを崩すことが知られています。慢性的なストレスは、腸内の炎症を引き起こし、脳の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。また、抗生物質の使用も腸内環境を悪化させる要因です。抗生物質は、腸内の善玉菌を減少させ、悪玉菌の増殖を助長することがあります。これにより、腸内のバランスが崩れ、脳の健康に影響を与えることが示されています。最後に、運動不足も腸内環境に悪影響を及ぼす要因です。運動は腸内の血流を促進し、腸内細菌の多様性を高めることが知られています。運動不足は腸内環境を悪化させ、脳の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。腸内環境と脳の健康の関係は、今後の研究によってさらに明らかにされることが期待されます。腸内環境を改善することで、脳の健康を維持し、さまざまな精神的な問題を予防する可能性があるため、腸内環境の重要性を理解し、日常生活に取り入れることが重要です。
参考:
須藤信行「ストレスと腸内フローラ」(腸内細菌学雑誌 19 2005)
脳腸相関が睡眠に与える影響とは?

脳腸相関は、脳と腸の間の双方向のコミュニケーションを指し、近年の研究により、腸内環境が睡眠の質に大きな影響を与えることが明らかになっています。この相関関係は、腸内細菌が神経伝達物質やホルモンの生成に関与していることから説明されます。特に、セロトニンやメラトニンといった睡眠に関連する物質は、腸内で生成されることが多く、腸内環境の改善が睡眠の質を向上させる可能性があります。
良質な睡眠と腸内環境の関係
良質な睡眠は、心身の健康に不可欠であり、腸内環境がその質に影響を与えることが多くの研究で示されています。また逆に、睡眠の質の悪化が腸内菌叢への悪影響を及ぼす事も調べられています。例えば、短時間の睡眠によりFirmicutes門の腸内細菌が増え,Bacteroidetes門の腸内細菌の減少が認められ,その結果インスリン抵抗性と耐糖能の悪化が認められた研究報告があります。腸内細菌は、食事から得られる栄養素を分解し、短鎖脂肪酸やビタミンB群などの重要な物質を生成します。これらの物質は、脳の機能をサポートし、ストレスを軽減する効果があります。特に、短鎖脂肪酸は、腸内の炎症を抑える作用があり、これが睡眠の質に寄与することが示されています。また、腸内細菌のバランスが崩れると、腸内の炎症が増加し、これが脳に悪影響を及ぼすことがあります。例えば、腸内の炎症は、ストレスホルモンであり、抗炎症作用を持つコルチゾールの分泌を促進し、これが睡眠の質を低下させる要因となります。これはコルチゾールが覚醒準備ホルモンとも呼ばれ、早朝に通常は高くなるのですが、腸内の炎症やストレスに曝露され日中コルチゾールが高濃度に分泌される事で、夜間の睡眠の質の低下に繋がると考えられています。さらに、腸内環境が悪化すると、腸内細菌による短鎖脂肪酸の生産量が低下し、短鎖脂肪酸の刺激により腸管のクロム親和性細胞(EC細胞)が産生するセロトニンが減少し腸の蠕動運動に影響を及ぼします。腸で作れられたセロトニンは脳血液関門を通過できないため直接中枢神経系に作用する事はありませんが、ある種のビフィズス菌が腸内に定着していると、脳血液関門を通過できるセロトニンの前駆体となるトリプトファンの血中濃度が上昇する事が報告されております。セロトニンは、メラトニンの前駆体であり、メラトニンは睡眠を促進するホルモンです。このように、腸内環境と睡眠の質は密接に関連していることがわかります。
参考:
入江潤一郎ら「睡眠と腸内細菌叢」(腸内細菌学雑誌 31 2017)
中山二郎「腸内細菌と健康」(日本醸造協会誌 Vol.108 No.10 2013)
M3.com 臨床ニュース「腸内環境と心の病の知られざる関係」(2022年2月7日記事)
睡眠の質を向上させるためにできること
睡眠の質を向上させるためには、腸内環境を整えることが重要です。以下に、腸内環境を改善し、睡眠の質を向上させるための具体的な方法をいくつか紹介します。
バランスの取れた食事: 腸内環境を整えるためには、食物繊維が豊富な野菜や果物、発酵食品を積極的に摂取することが推奨されます。これにより、腸内の善玉菌が増え、腸内フローラのバランスが改善されます。特に、ヨーグルトや納豆などの発酵食品は、腸内の健康をサポートするために効果的です。
適度な運動: 定期的な運動は、腸内環境を改善し、ストレスを軽減する効果があります。運動によって腸の動きが活発になり、腸内の血流が改善されることで、腸内細菌のバランスが整います。また、運動はセロトニンの分泌を促進し、睡眠の質を向上させることが知られています。
ストレス管理: ストレスは腸内環境に悪影響を及ぼすため、リラクゼーション法や趣味の時間を持つことが重要です。瞑想や深呼吸、座禅、ヨガなどは、ストレスを軽減し、心身のリラックスを促進します。これにより、睡眠の質が向上することが期待されます。
規則正しい生活リズム: 睡眠の質を向上させるためには、毎日同じ時間に寝起きすることが重要です。体内時計を整えることで、メラトニンの分泌が促進され、より良い睡眠が得られます。また、就寝前のブルーライトの影響を避けるために、スマートフォンやパソコンの使用を控えることも効果的です。これらの方法を実践することで、腸内環境を整え、睡眠の質を向上させることが可能です。脳腸相関の理解が進む中で、腸内環境の改善が睡眠の質に与える影響についての研究は今後も重要なテーマとなるでしょう。
参考:
小西正良ら「セロトニン分泌に影響を及ぼす生活習慣と環境」(大阪河崎リハビリテーション大学紀要 vol.5 2011)
脳腸相関を整えるための具体的な方法
脳腸相関とは、脳と腸の間に存在する双方向のコミュニケーションを指し、これが健康に与える影響は非常に大きいとされています。腸内環境が脳の機能や感情に影響を与えることが多くの研究で示されています。ここでは、脳腸相関を整えるための具体的な方法について詳しく解説します。

食生活の改善が鍵
食生活は脳腸相関を整える上で非常に重要な要素です。特に、腸内フローラのバランスが重要と考えられ、それを保つためには、食物繊維や発酵食品を積極的に摂取することが推奨されています。食物繊維は腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整える役割を果たします。例えば、野菜、果物、全粒穀物などに食物繊維が豊富に含まれています。また、発酵食品(ヨーグルト、納豆、キムチなど)は腸内の善玉菌を直接補充する効果があります。これにより、腸内のバランスが整い、脳への信号が改善されることが期待されます。研究によると、腸内フローラの多様性が高いほど、メンタルヘルスが良好であることが示されています。さらに、オメガ-3脂肪酸を含む食品(青魚、ナッツ、亜麻仁油など)も脳の健康に寄与します。オメガ-3脂肪酸は脳の神経細胞の構造を保つために必要不可欠であり、セロトニン代謝に影響を与え、炎症を抑える効果もあります。これにより、脳の機能が改善し、ストレスや不安感の軽減にもつながるとされています。
参考:
西田憲生「ストレスと脳腸相関:プロバイオティクスによるストレス緩和作用」(第25回腸内フローラシンポジウム 論文要旨集)
浜崎景ら「ω3系多価不飽和脂肪酸と気分障害」(静脈経腸栄養 vol.28 No.4 2013)
適度な運動で自律神経を整える
有酸素運動は腸内細菌叢に多くの影響を与えることが研究で示されています。特に、運動を行うことで特定の有益な菌種が増加し、腸内環境が改善されることが確認されています。
具体的な菌種名
ベイロネラ属(Veillonella): この菌は運動によって増加することが知られており、特に持久力トレーニングを行うアスリートの腸内で多く見られます。ベイロネラは乳酸をエネルギー源として利用し、プロピオン酸などの短鎖脂肪酸を生成します。これにより、腸内環境が整い、炎症が抑制される可能性があります。
ラクトバチルス属(Lactobacillus): 有酸素運動はラクトバチルスの増加にも寄与します。この菌は腸内のpHを低下させ、病原菌の抑制に寄与します。ラクトバチルスはストレス軽減やメンタルヘルスの改善にも関連しています。
ビフィズス菌(Bifidobacterium): ビフィズス菌も運動によって増加することが示されており、腸内の健康を維持するために重要な役割を果たします。この菌は免疫機能を強化し、ストレス応答を改善することが知られています。
腸内細菌叢の変化は自律神経系やメンタルヘルスにも影響を及ぼします。腸内細菌は脳腸相関において重要な役割を果たし、以下のようなメカニズムで影響を与えます。
ストレス応答の調整: 腸内細菌はストレスホルモンであるコルチゾールの分泌に影響を与え、ストレス応答を調整します。特に、ビフィズス菌や乳酸菌はストレス軽減に寄与することが示されています。
神経伝達物質の生成: 腸内細菌はセロトニンやGABAなどの神経伝達物質の生成に関与しており、これらは気分や感情に影響を与えます。腸内の善玉菌が増えることで、これらの神経伝達物質のバランスが改善され、メンタルヘルスが向上する可能性があります。
炎症の抑制: 腸内細菌は炎症を抑える短鎖脂肪酸を生成し、これが脳の炎症を軽減することが研究で示されています。腸内環境が整うことで、メンタルヘルスの改善が期待されます。
腸内細菌叢の変化に関する研究では、運動が腸内の特定の菌種に与える影響が明らかになっています。特に、運動後に酪酸菌の一種であるフィーカリバクテリウムが増加することが報告されています。この菌は短鎖脂肪酸を生成し、腸内の炎症を抑える効果があります。また、運動によって腸内のアクチノバクテリウムやバクテロイデスの割合も変化し、これらの菌は腸内環境の多様性を高める要因となります。
さらに、腸内細菌は自律神経系に影響を与え、特にストレス応答に関与しています。腸内の善玉菌が増加することで、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑制され、結果としてメンタルヘルスの改善が期待されます。研究によると、腸内細菌の多様性が高い人は、ストレスや不安を感じにくい傾向があることが示されています。これにより、運動が腸内細菌叢を改善し、メンタルヘルスに良い影響を与えることが示唆されています。
参考:
「ウォーキングが腸内フローラを改善 運動をすると腸内菌が健康に」(糖尿病ネットワーク 2016年1月26日記事)
「<連載> 腸サイエンスの時代 運動で腸内細菌を鍛える アスリート菌ってなに、その特徴とは」(朝日新聞Reライフ.net 2021年9月3日記事)
上田江里子「乳幼児期からのメンタルヘルス対策に向けての一考察 -気質と腸内細菌叢に着目した発達支援の提案-」(京都大学大学院教育学研究科紀要 70号 2024年)
ストレス管理とメンタルケアの重要性
精神的ストレスは脳腸相関に悪影響を及ぼす要因の一つです。ストレスがかかると、腸内のバランスが崩れ、腸内フローラが乱れることが知られています。これにより、脳への信号が悪化し、メンタルヘルスに悪影響を及ぼす可能性があります。したがって、ストレス管理は脳腸相関を整えるために非常に重要です。
精神的ストレス管理には、リラクゼーション法やマインドフルネス、座禅、瞑想などが効果的です。これらの方法は、心を落ち着け、ストレスを軽減する効果があります。研究によると、マインドフルネス瞑想はストレスを軽減し、脳の構造を変化させることが示されています。
また、十分な睡眠も脳腸相関を整えるために欠かせません。睡眠中に脳は情報を整理し、腸内環境を整えるためのホルモンが分泌されます。質の良い睡眠を確保することで、脳と腸の健康を保つことができます。
このように、食生活の改善、適度な運動、ストレス管理は、脳腸相関を整えるための具体的な方法です。これらを実践することで、腸内環境が整い、脳の健康が向上し、メンタルヘルスの改善が期待できます。日常生活に取り入れやすい方法から始めて、徐々に習慣化していくことが重要です。
参考:
三好巧真「瞑想中脳状態の脳機能ネットワーク解析」(The 31st Annual Conference of the Japanese Society for Artificial Intelligence, 2017)
池田真紀ら「総説 睡眠と健康:思春期から青年期」(保健医療科学 vol.64 No.1 2015)
まとめ:脳腸相関を理解し、健康を向上させよう

この記事では進化の過程で腸の神経細胞から高等動物の脳という中枢神経系に発達し、それにはおそらく腸の共生細菌である腸内細菌同士の連絡物質や代謝産物が関与している事、またそのため私たちの体でも腸内細菌、腸、脳が密接に関係し影響を及ぼし合っている事をIBSなどの疾患や睡眠、ストレスの関係から紹介しました。ストレスがかかれば消化管の機能や腸内細菌叢のバランスも悪化し、それがまた脳へ負のフィードバックとして負担をかける事にもなります。しかしsy会生活を行う私たちはストレスから逃れるのは簡単ではないので、まず取り掛かりやすい食生活の改善や腸内細菌叢の改善、運動習慣から脳機能を含む全身の健康維持へ繋げ、また瞑想や座禅といったストレス緩和のための行動にも取り組むと良いでしょう。
一覧へ戻る

