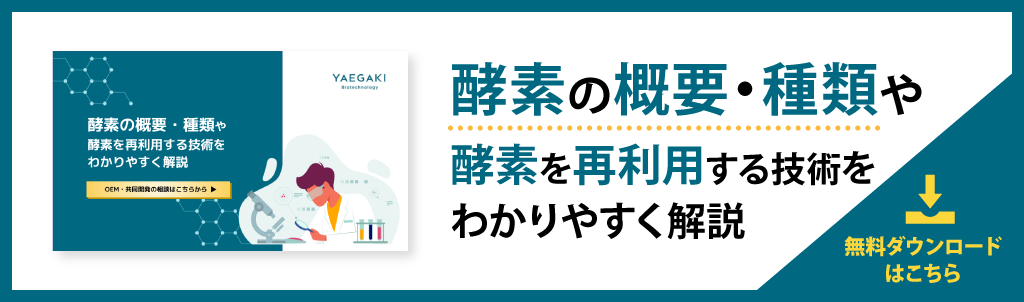高い健康効果で話題!発酵食品の種類と身体にもたらすメリットを解説
「発酵食品について詳しく知りたい」「食品が腐るのと何が違うのか」と気になる方は多いでしょう。発酵において微生物は非常に重要で、食品のみならず人間の生活に深く関わってきました。
そこで本記事では、発酵食品の概要とその種類について紹介します。発酵食品の魅力を学び、より発酵について詳しく理解しておきましょう。
※研究開発コラムは微生物を活用した研究開発において参考になるトピックを集めたもので、全てのテーマについて当社が研究開発を実施しているわけではございません。
目次
発酵食品とは?腐敗との違い
発酵とは、食品に微生物が増え起こる変化を指します。一方、腐敗も食品に微生物が増え起こる変化という点では同じになります。
そこで「発酵」と「腐敗」を分ける判断基準として定められているのが、人間にとって「有害」か「無害」かの違いです。
味や匂いの好みは普段食べている物や育ってきた環境で、人それぞれ大きく異なるため発酵と腐敗の線引は難しいですが、一番考慮すべきは人間にとって安全かどうかです。
そもそも安全性が保たれていないものを「食品」とは呼べないため、食品に微生物が増えた物のうち人が食べて安全な物が「発酵食品」、有害なものが「腐敗物」となります。
人間の生活と微生物の関係
微生物はあらゆる環境に存在しており、食品の腐敗と発酵に関与はもちろん感染症の発症、自然界の物質循環に大きく関わっています。
食物を栄養源として、増殖した微生物の中で人が口にしても無害である「発酵食品」
には以下のようなものが挙げられます。
- ・醤油
- ・味噌
- ・日本酒
- ・ワイン
- ・ビール
- ・チーズ
- ・パン漬物
- ・納豆
これらは先人達が試行錯誤を重ね、地域の気候風土に合った発酵を繰り返した結果生まれた食品です。
さらにこれらに加え、麹を利用して作られる発酵食品も数多く存在します。
参照:伝統発酵食品に関する食文化的,食品衛生学的および 微生物学的研究
発酵食品が定着した理由
日本はアジアモンスーン地域に位置し、昔から水田や稲作が行われてきました。
そのため、主食を米としてそこに汁物と菜の物菜を加えて構成される食事形態が室町時代にほぼ確立し、今の私達の食事まで継承されています。
主食である米はたんぱく質含量が少なく、必要なたんぱく量を摂取するには大量に食べる必要がありました。そこで美味しく米を食べるために考案されたのが、うま味が豊富で多様な発酵食品です。
また、1200年間続いた肉食禁忌の食習慣で米と共に食べる菜以外で味にバラエティをつけるために、味噌や醤油、かつお節などの発酵食品が発達したと言われています。
このため、発酵食品である味噌や醤油、だしが発達したのは日本人が昔から好んで食べる汁物の存在が大きいとされています。
発酵させる利点
発酵させる最大の利点が、保存性の向上です。
今は冷蔵庫の普及により保存性が保たれていますが、まだ冷蔵技術がなかった時代の保存技術として重宝されていたのが発酵です。
また、発酵させることでうま味が引き出されます。発酵する過程でうま味物質などの機能性成分や健康成分が生まれるのです。
「味噌は体に良い」と江戸時代の本に多く記されていますが、当時の文明では体に良いとは証明できません。
それにも関わらず体に良いと記載されていたのは、当時の人々が経験的に認識していたためだと言われています。だからこそ今日まで発酵食品は作り続けられてきました。
日本の発酵食品の特徴
日本の発酵食品の一番の特徴は「麹(こうじ)」を使用している点です。
麹とは、米や麦、大豆などの穀物に「麹菌」を播種し、発酵させたものです。醤油や味噌、みりん、酢、酒、焼酎などは麹を使用し作られています。
日本で麹が使われ始めた起源は諸説ありますが、米で麹を作るようになってから発酵技術は格段に進歩しました。そこから米や味噌が全国に広がり、後に味噌が各地で作られるようになりました。
また、麹を育てて塩水に浸けることで発酵と分解が促進されて香りの際立つ醤油が生まれたとされています。酒に関しても麹を使い試行錯誤を重ね、今の酒や焼酎に継承されたとされています。
麹を使うメリット
麹菌は酵素を大量に生成することで、米や麦などの穀物の炭水化物やタンパク質成分を分解します。そしてこれらの分解物を用いて、乳酸菌や酵母を自然に増殖させます。この乳酸菌と酵母が発酵を広げ、味に奥行きを産み複雑なおいしさに繋げるのです。
乳酸菌や酵母、酢酸菌を使用する国は世界中にありますが、発酵食品に麹を用いているのは稀です。麹菌は和食にとってなくてはならない存在で、日本人に昔から愛されている菌の1つと言えるでしょう。
代表的な発酵食品の種類
日本には昔から暑くて高湿度な梅雨があり、カビが生える時期を利用して麹菌を活かす発酵技術を確立しました。
麹を使用し日本の伝統的な発酵食品を製造することを「醸造」と呼びます。代表的な醸造物としては、醤油や味噌、みりんが挙げられます。
また、麹菌は醸造以外にも酸素工業や医薬と幅広く利用され、日本人の健康に大きく貢献しています。
ここでは日本食の中で特に影響が大きい発酵食品について、それぞれ解説します。
参照:発酵のチカラ
醤油
醤油には香味成分だけでなく、多くの機能性成分が含まれています。
酵母がつくるフラノンであるHEMFには発がん抑制効果、ニコチアナミンによる血圧上昇抑制、メラノイジンのよる抗酸化性、しょうゆフラボンによる骨粗鬆症予防などがあります。
また、醤油に含まれる多糖類からはアレルギーを抑える効果や、鉄分の吸収を促進する効果なども発見されており、摂取のメリットは大きいといえます。
味噌
味噌は醤油と違い、発酵管理が比較的容易で圧搾工程もなく簡単に作れることから、重宝されています。
醤油同様に味噌にも機能性成分が多く含まれていて、血圧上昇抑制、放射線防御効果、胃がんや乳がんに対する抗腫瘍性、抗変異源性、抗酸化性などがあり、味噌の健康維持効果に注目が集まっています。
参照:
発酵のチカラ
大豆・イソフラボン摂取と乳がん発生率との関係について | 現在までの成果 | 多目的コホート研究
納豆
納豆は蒸した大豆を納豆菌で発酵させた発酵食品です。
タンパク質、脂質、ミネラル、ビタミンなどを含む栄養価の高い発酵食品として日本人に重宝されてきました。
また大豆の機能性成分に含まれる抗酸化作用や血圧降下作用、コレステロール調節作用など生活習慣病の予防にも期待でき、注目を集めています。
みりん
みりんは最初、女性やお酒の飲めない人用の甘いお酒でした。
しかし江戸時代後期にうなぎのタレや、そばつゆに使われはじめ、次第に調味料として定着していきました。
調理効果としては、品のある甘みやテリ・ツヤの付与、煮崩れ防止や消臭効果が期待されます。そして機能性効果としては、抗酸化性と血圧上昇抑制があります。
参照:発酵のチカラ
代表的な発酵菌の種類
日本の発酵食品は1種類の発酵菌から生成されているわけではなく、複数の組み合わせによって複雑なうま味が得られます。
ここでは発酵菌にどのような種類があるか、解説していきます。
麹菌
麹菌とは様々な日本の伝統的な醗酵食品・飲料の製造に使われてきた糸状菌(しじょうきん)の一種です。
また、麹菌のポイントは酵素を大量に生成する点です。麹菌は様々な発酵食品に用いられ、用途によって働きと作り出す味わいも異なります。
発酵食品の代表的存在として、日本の食文化を支え、日本醸造学会によって「国菌」に認定されました。
参照:麹菌や微生物の話
酵母
酵母菌は微生物の一種であり、キノコやカビと同じ仲間です。酵母菌は自然界のさまざまな場所に生息しており、皮膚の表面や消化管などにも住んでいます。
大きくアルコール発酵酵母と耐塩性酵母の2種類に分けられ、アルコール発酵酵母は日本酒やパン、耐塩性酵母が味噌や醤油をつくる際に用いられます。
参照:酵母利用食品
乳酸菌
乳酸菌とは、ブドウ糖や乳糖などの糖を分解して乳酸を生成する細菌の総称で、人類にとって最も有益な細菌です。
また、乳酸菌はほとんどの発酵食品の製造過程に関与する発酵食品の中心的存在と言っても過言ではありません。
やや渋味がある独特のすっぱさが特長で、ヨーグルトやチーズ、キムチなどに含まれています。
参照:
(2018年7月発行)発酵食品と乳酸菌 -発酵過程における役割と機能-
乳酸菌の基礎知識
納豆菌
納豆菌は、環境中に栄養素が豊富な時は活発に分裂増殖を行う一方、栄養素がなくなったり環境ストレスが強くなると芽胞という休眠状態を取る細菌です。独特の匂いと発酵によってつくられるネバネバが特徴で栄養価は極めて高く、日本人の食事に昔から取り入れられています。
参照:納豆菌 酢酸菌 乳酸菌
酢酸菌
酢酸菌は酢をつくるのに不可欠な菌で、食酢製造やビタミンC合成のためのソルボース発酵などに関わる重要な微生物です。酢酸特有のツンと鼻にくる酸味が特徴とされています。
まとめ:発酵食品のメリットは製品に活かせる
発酵させることで得られる機能性成分の種類は、多岐にわたります。
重要なのは、それぞれの発酵食品に含まれる機能性成分を理解し、用途別に使い分けることです。
これらを正しい知識で使い分けることで、健康効果が期待できるでしょう。発酵に関する今後の研究についても、見守っていく必要があります。
一覧へ戻る