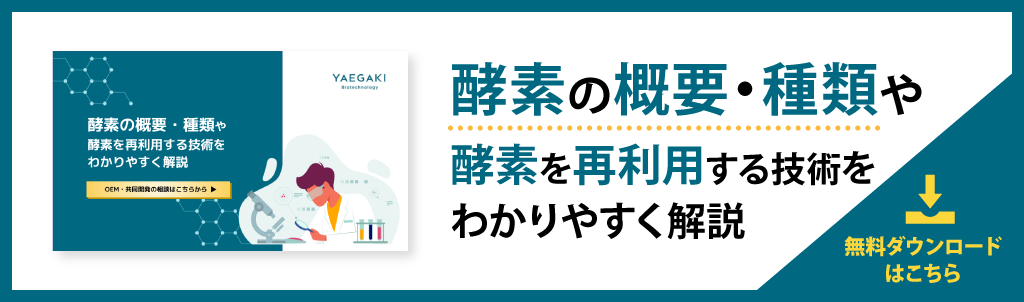酒粕の製造方法とは?種類・摂取のメリットもあわせて解説
酒粕は日本酒の製造過程で生まれる栄養豊富な副産物であり、古くから食材や美容、健康面で幅広く活用されています。
しかし、酒粕の製造方法やその種類、さらにどのようなメリットがあるのかを詳しく知っている方はあまり多くありません。
そこで本コラムでは、酒粕がどのようにつくられるのか、その種類や特徴、そして健康や美容にどんな恩恵があるのかを詳しく解説します。
※研究開発コラムは微生物を活用した研究開発において参考になるトピックを集めたもので、全てのテーマについて当社が研究開発を実施しているわけではございません。
目次
酒粕とは
酒粕は、日本酒を製造する過程で、もろみを搾ったあとに残る固形物です。米・米麹・酵母が発酵することで生まれた栄養素が豊富にあり、タンパク質やビタミンなどが含まれています。
酒粕は料理の材料として使われることが多く、鍋物や味噌漬け、甘酒の原料として親しまれています。
さらに健康や美容にとって良い成分が含まれているのも特徴で、近年は健康食品や化粧品の素材としても注目されています。
酒粕の歴史
酒粕は、甘みや旨味調味料などに使われていたと古い読み物の中で少し語られているほどで、日本酒に比べると有名ではありません。ただ、酒粕は稲作によってお酒造りが生まれたのと同時期に誕生したと考えられています。
初めの頃のお酒は、米・米麹・水を混ぜて発酵させただけの「どぶろく」に似たものです。
その後もろみを濾す・搾るなどをおこなって上澄みの清酒と下に沈んだ酒粕を分けるようになっていきました。
はっきりと清酒と酒粕をわけるようになったのは、濾す・搾るなどができる道具ができ、生活技術が発達していったからとされています。
酒粕の歴史が文字として歴史に出てくるのは、奈良時代~平安時代ごろからです。
901~923年に出た「延喜式」には、「甘口の濃厚酒を、ザルで漉したり、絹の袋で漉した」「上澄みは上流階級や天皇の宮中での儀式に使った」といった記載があります。
同じく平安時代、天皇や貴族の料理を調理する「内膳司」での記述では、濃厚酒や濃厚酒の粕を料理に使っていたことがわかります。
参考:延喜式
そして現在のような圧搾された白板粕が一般的になったのは、江戸時代です。その後徐々に全国で酒屋が生まれていき、酒造りの職人も増えていきました。
酒粕の種類
酒粕の種類は主に4種類です。ここではそれぞれの種類について、ひとつずつ詳しく解説します。
板粕
板粕は、日本酒を絞る際に自動圧搾機を使うことで板状に残る酒粕であり、スーパーなどでよく見かける一般的な商品です。
板粕は平たく四角い形をしており、そのままでは固く溶けにくくなっています。そのため料理に使用する際は水や酒でふやかしたり、ミキサーでペースト状にするなどして使います。
主に鍋料理・甘酒・漬物の風味づけとして活用されています。
ばら粕
ばら粕は、板粕が崩れた状態の酒粕です。圧搾機からこぼれた酒粕や、柔らかすぎて板状にならなかった酒粕を集めています。
板粕が崩れた状態ではありますが、品質自体は板粕と同等のため心配いりません。ただ、ばら粕のほうが柔らかく溶けやすいという特徴があります。
板粕は小さく割れているため料理に使う際に扱いやすく、鍋料理や甘酒づくりなどでスムーズに混ざりやすいのが利点です。
踏込み粕
踏込み粕は、酒粕を半年ほど熟成発酵させたものです。
茶色や黄金色をしており、スーパーで漬物用として販売されている茶色い酒粕が踏込み粕にあたります。地方によって土用粕・押し粕などと呼ばれるほか、練り粕と呼ばれることもあります。
熟成によってコクや甘みが増し、特に奈良漬けなどの漬物に広く使われてきました。
漬物床として使用する際は、さらに熟成が進んで柔らかくなり薄いピンク色になったものが最適とされています。
練り粕
練り粕とは酒粕を熟成させて柔らかく練り上げたものであり、特に漬物や調味料として使われます。
踏込み粕とも呼ばれ、酒粕を半年ほど発酵・熟成させた後、滑らかなペースト状に仕上げられます。熟成が進むことで茶色や黄金色になり、コクや甘みが強くなるのが特徴です。
酒粕の製造方法
ここでは、基本的な酒粕の製造方法について、日本酒の工程を含めそれぞれ解説します。
①蒸米
まずは精白した米を蒸して、麴の製造・酒母用の米・掛米に分けます。比率は2:1:7と、掛米が多めです。
麹用の蒸米には種麹を散布し、温度や湿度を調整しながら麹菌を増やしていきます。
②もろみの製造
次は掛米に麹を混ぜて発酵させてもろみをつくります。もろみをつくる工程は「仕込み」といい、一般的に取られている方法が「三段仕込み」です。
麹と酒母を混ぜる「初添仕込」が1回目、数日間撹拌し酵母菌を増殖させるのが2回目の「中添仕込」です。
そしてそれぞれ掛米や麹、水の量を徐々に増やして仕込み、温度管理をしながら発酵を進めるのが最後の「留添仕込」です。
発酵後〜もろみの完成までは約1か月ほどかかります。
③日本酒の搾り
日本酒を搾って酒粕と分けることを、「上槽工程」といいます。酒粕を生み出すためには上槽工程を踏む、つまり日本酒を搾らなくてはなりません。
搾る方法は主に「自動圧搾機」「槽搾り(ふなしぼり)」「袋吊り」の3つです。
自動圧搾機の場合は、圧搾機の中にもろみを入れて圧力を加えて日本酒を搾り出します。布を重ねた多くの板に圧力を加えて酒粕が残るという仕組みのため、搾り出された酒粕は板状になっているのが特徴です。
槽搾りとは、もろみ酒袋を入れ、槽の中に入れて上から圧力をかけて搾り出す方法です。時間はかかるものの、優しく絞り出す方法のため、大吟醸など繊細な日本酒に向いています。
袋吊りは、もろみを入れた酒袋を吊るして、重力で酒を絞り出します。人の手や機械を使わないため、一番時間と手間がかかる方法です。
酒粕の栄養素
ここでは、酒粕に含まれている栄養素について解説します。
レジスタントプロテイン
レジスタントプロテインは、消化酵素によって分解されにくいタンパク質の一種です。胃で消化されず、大腸にまで届きます。通常のタンパク質は体内でアミノ酸に分解されて吸収されますが、レジスタントプロテインは分解されにくく、そのまま消化管を通過します。
レジスタントプロテインには、健康や美容に関する効果も期待できます。実際に酒粕で甘酒をつくり、3週間毎日飲み続ける試験では、LDLコレステロール値の低下や、排便回数や排便量の増加などがみられました。
葉酸
葉酸は水溶性ビタミンで、ビタミンB群のひとつです。酒粕の葉酸含有量は100gあたり500μg以上とされていますが、酒粕の葉酸含有量は商品により異なります。
そのため中にはホウレンソウの約2.5倍もの葉酸を含む場合もあり、健康維持に役立つのではとされています。
葉酸は特に胎児の成長に不可欠なもので、赤血球の産生やDNAの合成に重要な役割を持っていることから妊娠中や授乳中の女性には欠かせない栄養素とされています。
また、ビタミンB12とともに赤血球の生成を助けるため、「造血のビタミン」としても知られています。
S-アデノシルメチオニン(SAM/SAMe)
S-アデノシルメチオニンは、体内に存在する生理活性物質のひとつです。気分改善作用や抗肝障害作用、抗関節炎作用などがあるとされており、一般的な食品には含まれていません。
なお、S-アデノシルメチオニンはドイツやロシアなどでは処方薬、カナダや米国などではサプリメントとして広まっています。しかし長期の使用や妊娠中の使用についての安全性は出ていないため、今後の研究を待つ必要があります。
参考:発酵食品「酒粕」による老化抑制および脳機能活性化の検討
α-EG(α-エチル-D-グルコシド)
α-EG(α-エチル-D-グルコシド)は、グルコース(ブドウ糖)にエチル基が結合した化合物で、D-グルコースにエタノールが脱水縮合して生じます。日本酒や酒粕に含まれるうま味成分のひとつで、健康や美容に役立つ特性に注目が集まっています。
体内に取り込まれたα-EGは小腸から吸収され、皮膚の真皮層に存在する線維芽細胞に溜まったのち、コラーゲンの生成が促進されます。
α-EGは塗布する事で細胞間の脂質合成を促進し、角質層のバリア機能を強くしてくれるため、肌の保湿力アップにも繋がります。さらに角質が保つ水分量も増えるため、肌のアンチエイジング効果が期待できます。
参考:
日本酒に含まれる美肌成分「α-EG」高含有パウダーの開発とその活用
世界初。日本酒の成分α-EGが皮膚真皮層のコラーゲン量を増やすことを学術的に実証。日本酒復権に弾み
Effect of a Sake Concentrate on the Epidermis of Aged Mice and Confirmation of Ethyl α-D-Glucoside as Its Active Component
L-システインは、アミノ酸の一種です。抗酸化作用があり、肌や髪の健康をサポートするのに役立ちます。またメラニンの生成を抑制するとされており、シミやくすみの改善効果が期待されます。
参考:肌の代謝とL-システイン | ハイチオール【エスエス製薬】
酒粕を摂るメリット
酒粕を摂るメリットは主に3つあります。ここからはそれぞれ詳しく解説します。
美容効果
酒粕にはアミノ酸やペプチドなどの成分が豊富に含まれており、肌の保湿を助ける働きがあります。乾燥肌の改善や、肌の潤いを保つ効果が期待できる点が魅力です。さらに酒粕ペプチドには抗酸化作用もあり、老化の原因となる活性酸素を除去する働きもあります。
参考:
納豆菌由来の発酵ペプチドで実現し た 界面活性剤を極力使わず マイルドで環境に優しい処方の クレンジングジェルが登場
酒粕の分解物による抗酸化作用 | 美と健康の研究 | 月桂冠総合研究所 | 月桂冠
また、酒粕にはα-EG(α-エチル-D-グルコシド)が含まれており、コラーゲンの生成を促進し、肌のハリや弾力を保つ効果が期待されます。
参考: 日本酒に含まれる美肌成分「α-EG」高含有パウダーの開発とその活用
健康効果
酒粕に含まれる栄養素のひとつに、ペプチドがあります。ペプチドは、含まれている食品によって異なる効果を発揮するのが特徴です。
酒粕に含まれるペプチドは、血圧を上昇させる役割を持つ「アンジオテンシン変換酵素」を抑制し、血圧を下げる効果があることが認められています。
また酒粕ペプチドの特長は、血圧降下剤に比べてより穏やかなペースで血圧の上昇を抑えることにあります。
参考:酒「粕」も百薬の長 酒粕から血圧を下げるペプチド | 美と健康の研究 | 月桂冠総合研究所 | 月桂冠
冷え性の緩和
酒粕は、冷え性の緩和にも効果が期待できます。酒粕=体が温まるというイメージを持っている方は多いと思いますが、決定づけるような研究はほとんどありませんでした。
そこで月桂冠では、冷え性の症状がある男女8人にそれぞれ「酒粕粉末」か「米粉」を食べてもらい、冷却負荷の直後・10分後・30分後に確認したところ、酒粕を食べた人に手の表面温度の上昇が見られました。
さらに長期間(8週間)をかけて試験をおこなったところ、日時が経つにつれて手の温度の回復が早まり、指先まで温まったとされています。
引用:酒粕による冷えの改善 酒粕のイメージを検証し、酒粕に体を温める効果を実証| 美と健康の研究 | 月桂冠総合研究所 | 月桂冠
上記研究により、酒粕を継続して摂取することで冷え性の改善につながると考えられます。
まとめ
酒粕は、日本酒を製造する際に生まれる副産物であり、もろみの発酵を経て日本酒を搾る過程で作られるもので、長い歴史を持っています。
種類としては板粕・ばら粕・踏込み粕・練り粕などがあり、それぞれ異なる特徴を持っています。
また栄養価が高く、レジスタントプロテインや葉酸、L-システインなどが含まれ、美容や健康に多くの効果があります。
伝統的な食品である酒粕を活かし、健康・美容の関連事業に役立ててください。
一覧へ戻る