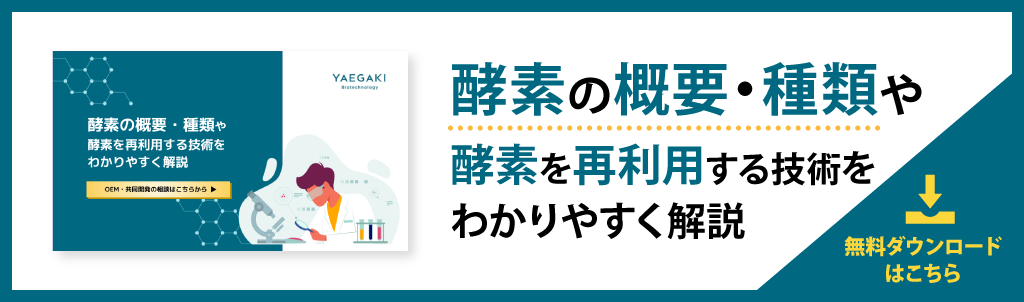酒粕の再利用方法とは? 食品での使用例や肥料利用例を解説
甘酒や漬物、さらにはかす汁など、さまざまな料理に使用されている酒粕ですが、実は産業廃棄物として捨てられることが多くなっています。
そのため廃棄される酒粕を再利用できないか前向きな検討や研究が進められています。環境意識が高まっている現在、酒粕を再利用できれば消費者からのイメージ向上にもつながるでしょう。
本記事では、酒粕の廃棄量の現状を説明しつつ、実際の再利用の例を紹介します。酒粕の再利用について興味を持っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
※研究開発コラムは微生物を活用した研究開発において参考になるトピックを集めたもので、全てのテーマについて当社が研究開発を実施しているわけではございません。
目次
酒粕とは
酒粕とは、日本酒を作る際の工程として「もろみ」に圧力をかけて日本酒を絞り出した後の残りかすです。
詳しくは下記記事で解説していますが、もろみとは米や米麴を水や酵母によって発酵させることで、米や米麹が溶け出したものです。
日本酒を作る際は、もろみを日本酒と酒粕に分ける必要があります。分けた際に出てきた酒粕には炭水化物やタンパク質、さらにはビタミンなどの栄養素が豊富に含まれています。
酒粕の原材料
酒粕の原材料は主に水と米であり、酒粕の風味は日本酒の種類によって異なります。吟醸酒の製造から得られる酒粕は、お菓子作りで使用されることが多くなっています。
また純米酒から作られる酒粕は、かす汁などの料理で使用するのに適しています。
酒粕の製造方法
日本酒を作る際には、原料である米、米麹、水から発酵や熟成を通してもろみを生成します。もろみは日本酒と酒粕が混ざった状態であり、そこから日本酒と酒粕を分ける工程のことを上槽と呼びます。
上槽には自動圧搾機、槽搾り、袋吊りなどの方法があり、生成する日本酒の種類により上槽の方法を分けています。
酒粕の栄養素
酒粕可食部100gあたりに含まれる栄養素は、以下の通りです。
- ・カロリー…215kcal
- ・炭水化物…23.8g
- ・たんぱく質…14.9g
- ・食物繊維…5.2g
- ・糖質…18.6g
- ・脂質…1.5g
- ・ビタミンB1…0.03mg
- ・ビタミンB2…0.26mg
- ・ビタミンB6…0.94mg
- ・ナトリウム…5mg
- ・カリウム…28mg
- ・亜鉛…2.3mg
- ・銅…0.39mg
- ・葉酸…170μg
- ・アルコール…8.2g
酒粕には炭水化物のほか、たんぱく質や食物繊維、カリウム、亜鉛や銅など、さまざまな栄養が含まれています。食物繊維、ビタミンなど健康に役立つ成分が数多く含まれているため、酒粕には今後も注目が集まるでしょう。
参考:食品成分データベース
酒粕の効果
酒粕には身体にとって良い働きがあります。この章では、酒粕の働きについて説明します。
①身体の調子を改善させる
酒粕には、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6などのビタミン群が含まれています。ビタミンB1はブドウ糖をエネルギーに変換する際に必要な栄養素です。この栄養素が不足するとブドウ糖から十分にエネルギーを生成できず、食欲不振やだるさ、疲労の症状が出現します。
またビタミンB2はエネルギー代謝の補酵素としての働きがあり、成長促進・粘膜保護を行います。ビタミンB2が不足すると成長障害・脂漏性皮膚炎・口内炎を引き起こすことが知られています。
そしてビタミンB6は、丈夫で健康な皮膚、粘膜、髪、歯、爪などの生育、脂質の代謝や赤血球のヘモグロビンの合成に不可欠です。
酒粕にはビタミンB類が含まれていることから、継続した摂取で健康維持に繋がるといえるでしょう。
参考:
ビタミンB1の働きと1日の摂取量
ビタミンB2 – 「 健康食品 」の安全性・有効性情報
ビタミンB6とは?体をつくるタンパク質の元となる
②血圧上昇の抑制
酒粕には、アミノ酸やタンパク質の他にもペプチドという栄養素が含まれています。
ペプチドは含まれる食物によって効果が異なり、酒粕ペプチドには医薬品のように急速に血圧を低下させる効果はありません。
しかし1~2ヶ月ほどかけて緩やかに血圧を下げる作用があり、一定期間効果を持続させるとされています。そのため、毎日続けて食べることで身体の健康を維持できると考えられています。
③コレステロール濃度の低下
酒粕にはレジスタントプロテインというタンパク質が含まれており、その量は酒粕(半乾燥)100g中に対して3.87gとなります。
レジスタントプロテインは身体に消化されにくいタンパク質であり、コレステロール由来の胆汁酸を吸着し体外への排出を促す働きがあります。この働きにより胆汁酸が減ると新たな胆汁酸が体内で生成され、結果として体内のコレステロール濃度が低下します。
参考:
レジスタントプロテイン含有量の調査
酒粕レジスタントプロテインの正体とは?~血中コレステロール低減に寄与、にごり酒でも摂取可能~
酒粕の生成量と廃棄量
この章では、酒粕の生成量や廃棄量の実態を説明します。
酒粕が廃棄される要因もお伝えするので、今後の廃棄量を減らすためのアイデアに繋げてください。
酒粕の生成量
酒粕は日本酒づくり中に生成されるもので、令和4年度の生成量は約34,000tです。この量は年間で作られる日本酒の総量の約10%程度となります。
昨今、酒粕が多く生成される吟醸酒の生産割合が高くなっていることから、酒粕の生成量は増加しています。
酒粕の廃棄量
酒粕の廃棄率を示した具体的な資料はありませんが、酒類業中央団体連絡協議会より「酒粕(精米時の糠を含む)の食品廃棄物等の発生量全体の再生利用等率は90%以上を維持している」との見解が出ています。
この見解を参考にすると、酒粕の廃棄率は10%以下ということになります。
参考:「食品廃棄物等の発生抑制目標値の策定に対する酒類製造業の意見等」
酒粕が廃棄される理由
本業が酒造業である酒蔵では酒粕の生成に重点を置いていないため、多少コストがかかっても、廃棄処分をすることが多くなっています。
廃棄する理由として、生酒粕は水分が多く保存しにくいことが挙げられます。
近年は酒粕の活用量が減っています。その理由として、家庭で奈良漬けや柴漬けなどを作る文化が減っていることで酒粕の需要が減っていることや、吟醸酒に代表される高品質な日本酒の製造が進むことで、上槽時の搾り方に起因して生成される酒粕の量が増加していることとされています。
自分たちで酒粕をリサイクルするとしても費用も手間がかかることから、処分する酒蔵は少なくありません。
参考:
廃棄していた酒粕の積極的な活用と地域連帯
酒粕の再利用状況を探る – 廃棄率/再利用率の統計や取り組み事例など、最新情報レポート
酒粕の廃棄方法
この章では実際に酒粕が廃棄される方法について説明します。
酒粕の廃棄方法
酒粕は飼料や漬物の材料として使用されない限り、産業廃棄物として処分されます。
再利用を検討する酒造は多いものの、もろみを絞って出てくる酒粕にはいろいろな成分が入っていることから、有効成分のみを求めた商品化は容易ではありません。
そのため漬物の材料や飼料・肥料として活用するか、蔵の近隣住民に配布して引き取ってもらうことが多くなっています。
そのため上述のように様々な栄養素を含む酒粕を廃棄するのではなく、酒粕を有効活用して価値を向上させていく技術の開発が今後の持続可能な社会形成に必要と言えます。
参考:「酒粕リユース蒸溜所」産業廃棄物として処分される酒粕をリユースし、ジンを創ると共に循環経済を実現する世界初のプロジェクトが始動
酒粕を商品や肥料として再利用する例
酒粕は再利用可能であるため、廃棄せずに様々なアイディアを考える事で売上に繋げる酒蔵も存在します。
ここでは廃棄される酒粕を減らすため、再利用の具体例を紹介します。
酒粕を利用した加工品
酒粕を使った加工品として思い浮かべるもののひとつに、『粕取り焼酎』があります。
粕取り焼酎は酒粕から作られるお酒であり、栄養分や旨み成分を豊富に含むことから近年人気が高まっています。
また粕取り焼酎以外に、酒粕を粉末やペースト状に加工し、「ばら粕」や「板粕」など料理の原料や調味料に生まれ変わらせる酒造もあります。
酒粕を利用したスイーツ
酒粕の再利用例として、酒粕を使ったスイーツも多数販売されています。
酒粕スイーツの製造では、乾燥粕をパウダーにして原料に混ぜることが多いです。乾燥粕を用いることで味わいにコクがでて、深みのある味わいや芳醇な香りを演出できます。
酒粕の家畜の飼料としての活用例
酒粕は、家畜の飼料として用いられることも多いです。
酒粕を家畜の飼料として再利用するためには、酒粕を粉砕した後、乾燥させて粉末化し、酒粕から水分を飛ばす必要があります。
乾燥粕にすることで栄養素が高くなり、食いつきもよくなります。全国各地で売られている「ほろよいとん」は、酒粕を家畜飼料として活かした代表的な例となります。
酒粕の肥料としての活用例
栄養価が高い酒粕を、米栽培用の肥料として活用している事例もあります。酒粕を肥料として使用すると窒素成分がアンモニア態窒素などへ分解されながら栄養となり、土壌の負荷を減らせます。
そのほか、「米ぬか×酒粕」で発酵させた循環型肥料などもあり、酒粕の農業利用にも大きな注目が集まっています。
まとめ:酒粕を再利用することで廃棄せずに有効活用することが可能
酒粕をいかに廃棄せず、再利用していくか考えることは重要です。
近年は食文化の変化から家庭の酒粕利用が減少傾向ですが、SDGsが社会に浸透してきたこともあり、酒粕の新たな活用方法を見出す動きも色々な業界の中で活発になっています。
酒粕の廃棄コストによって経営を切迫させるのではなく、酒粕を有効活用させることで経営を助けるような活用が今後求められます。
一覧へ戻る