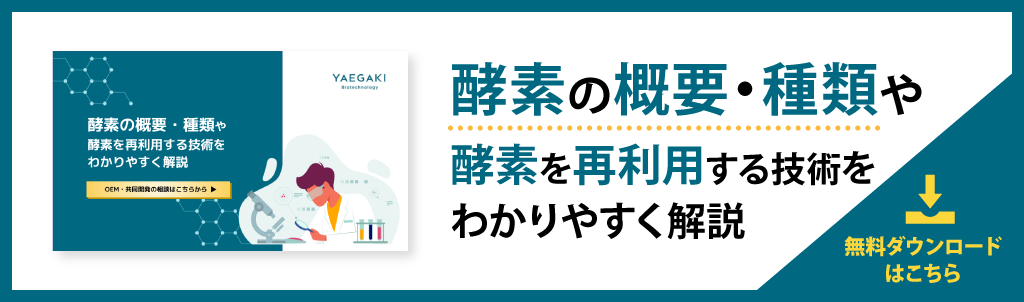酒粕の効果とは?保存方法や調理方法の注意点も徹底解説
国民の健康意識の向上によって、近年酒粕の食品としての保健効果にも注目が集まり様々な研究が行われています。
甘酒にしたり、かす汁にしたりと色々な使用方法がある酒粕ですが、意外と酒粕の効果や長持ちする保存方法を知らずに使用している方も少なくありません。
そこで本記事では、酒粕の栄養素や嬉しい身体への効果、さらに長持ちする保存方法や調理上の注意点を解説しています。酒粕を新しい商品やサービスに繋げたい方は、ぜひ最後までお読みください。
※研究開発コラムは微生物を活用した研究開発において参考になるトピックを集めたもので、全てのテーマについて当社が研究開発を実施しているわけではございません。
目次
酒粕とは
酒粕とは、日本酒を作る際の工程として「もろみ」に圧力をかけてお酒を絞り出した後の残りかすのことです。
もろみとは米や米麴を水や酵母によって発酵させたものであり、米や米麹が溶けたものです。そこから日本酒を作ろうと思うと、日本酒とそれ以外に分ける必要があります。
その分けた後の日本酒以外の残りかすが「酒粕」であり、酒粕には炭水化物やタンパク質、さらにはビタミンなどの栄養素が豊富に含まれています。
この章では、酒粕の原材料や製造方法などの基本的な情報をお伝えします。
酒粕の原材料
酒粕の原材料は主に水とお米であり、酒粕の風味は日本酒の種類によって異なります。日本酒の中でも、吟醸酒の製造から得られる酒粕には華やかな香りがあり、お菓子作りで使用されることが多くなっています。
また純米酒から作られる酒粕は米由来の香りを多く持っており、かす汁などの料理で使用するのに適しています。
酒粕の製造方法
日本酒を作る際には、原料である米、米麹、水から発酵や熟成を通してもろみを生成します。もろみは日本酒と酒粕が混ざった状態であり、そこから日本酒と酒粕を分ける工程のことを「上槽」と呼びます。
ここでは、酒粕の主要な製造方法を3つ解説します。
①自動圧搾機
日本酒のほとんどは、自動圧搾機を使用して作られます。圧搾機の中にもろみを入れ、両側から力をかけることで酒を搾り出します。機械の中は板が連なりあい、圧力をかけることで板状の酒粕が作られます。均一に搾ることができるので、品質を安定させることができます。また自動化により、蔵人の負担を大きく減らせます。
②槽搾り
槽搾りは、大吟醸など精細な日本酒づくりに向いています。酒袋と呼ばれる袋にもろみを入れて槽の中に積み重ね敷き詰めると、上から自重による圧力がかかり日本酒を搾り出せます。自動圧搾機よりも搾るのに時間がかかります。
③袋吊り
もろみを入れた袋を吊るして、重力によって酒を搾りだす方法です。自然の重力を利用して搾りだすので、一番時間がかかる方法です。袋吊りでは雑味のない最高品質のお酒をつくることが可能です。新酒評論会で出すようなお酒を作る際、この方法を利用します。
酒粕の栄養素
酒粕可食部100gあたりに含まれる栄養素は、以下の通りです。
- ・カロリー…215kcal
- ・炭水化物…23.8g
- ・たんぱく質…14.9g
- ・食物繊維…5.2g
- ・糖質…18.6g
- ・脂質…1.5g
- ・ビタミンB2…0.26mg
- ・ビタミンB6…0.94mg
- ・ナトリウム…5mg
- ・カリウム…28mg
- ・亜鉛…2.3mg
- ・銅…0.39mg
- ・葉酸…170μg
- ・アルコール…8.2g
酒粕には炭水化物のほか、たんぱく質や食物繊維、ミネラル、ビタミンなど、さまざまな栄養が含まれています。食物繊維、ビタミンなど健康に役立つ成分が数多く含まれているため、酒粕には今後も注目が集まるでしょう。
酒粕の種類
酒粕は、用途に合わせて使い分けることが重要です。酒粕は種類によって使うのに適した料理や調理方法が異なり、練り粕は野菜や魚を漬けるのに適しています。
この章では酒粕の種類や適した調理方法をお伝えします。
①板粕
自動圧搾機でもろみを搾った際に板状になって出てくるのが、板粕です。スーパーなどで発売される際は自動圧搾機から出てきたものを適度な大きさにカットしています。板粕はそのまま焼いたりして食べることが多いです。
②ばら粕
ばら粕は圧搾機で搾っている際、板状に固まらずにこぼれおちたものや、やわらかすぎた酒粕を集めたものです。品質は板粕とほとんど変わりませんが、板粕よりも溶けやすいです。板粕同様に味噌汁に入れたりなどさまざまな料理に使用できるほか、化粧品としてフェイスパックなどにも利用できます。
③練り粕
酒粕に水や焼酎などの液体を加え、ペースト状にして数か月寝かせたものが練り粕です。ペースト状になっており、ばら粕や板粕よりも溶けやすいです。野菜や魚を漬けたり、お肉を漬けたりするときに使われます。
④踏込粕
踏込粕は酒粕を半年ほど熟成発酵させたもので、茶色や黄金色をしています。地方によって踏込粕の呼び方が異なり、土用粕と呼んでいる地方もあります。
また、踏込粕を練り粕と呼んでいるところもあります。コクや甘味があるため、奈良漬けなどを作る際には踏込粕を使用することが多いです。
酒粕の効果
酒粕には、身体にとって良い働きがたくさんあります。ここでは、酒粕の主な効果を4つ解説します。
- 肌の状態を改善させる
酒粕には、ビタミンB群が豊富に含まれています。
ビタミンB1は神経の疲労回復や皮膚の健康維持に働くとされており、ビタミンB2やビタミンB6は肌のトラブルに対して改善させる効果があります。
さらに酒粕には、美肌作用の可能性があるL-システインやフェルラ酸、グルタチオンといった成分が含まれています。
これらの栄養素は肌のターンオーバーの正常化を促します。また体内の異物の解毒作用や酸化ダメージの抑制、メラニン色素を生成するチロシナーゼという成分の活性を抑える働きを持ちます。
- 冷え性の改善
酒粕には、アデノシンや酵素の一種であるプロテアーゼにより酒粕のたんぱく質を分解してできる酒粕ペプチドという物質が含まれています。これらの成分は血管の収縮を抑制して、血管を拡張させる働きがあります。
血管を拡張させると身体の末梢部まで血流がよくなり、肩こりや頭痛、冷え性が改善することが期待されます。
参考:
酒粕分解ペプチドに冷え性の血流改善効果
日本酒に含まれる栄養素とは?日本酒と健康の関係
- 血圧上昇の抑制
酒粕には、酒米を麹菌で発酵した際に、麹菌の持つ消化酵素の働きで作られるアミノ酸やペプチドという栄養素が含まれています。
酒粕ペプチドには医薬品のような急速に血圧を低下させるような効果はありません。しかし1~2ヶ月ほどかけて緩やかに血圧を下げる作用があり、しばらく摂らなくても一定期間効果を持続させるとされています。
- 便秘の改善や整腸作用
酒粕には100gあたり5gの食物繊維が配合されており、精米されたご飯の10倍の量の食物繊維を摂ることが可能です。
酒粕に含まれる食物繊維は不溶性食物繊維であり、保水性が高いので腸内で膨張し、腸の中で蠕動運動を促してくれるでしょう。
また、酒粕にはレジスタントプロテインというタンパク質が含まれており、その量は酒粕100g中に対して1500mgにもなります。
レジスタントプロテインは身体に消化されにくいタンパク質であり、腸の中で消化吸収されないままコレステロールや脂肪分を吸着し、便と一緒に排出されます。便のかさが増え、脂肪分によって柔らかくなって出てくるため便秘解消に効果的です。
参考:酒粕レジスタントプロテインの正体とは?~血中コレステロール低減に寄与、にごり酒でも摂取可能~
酒粕の保存方法や調理方法の注意点
酒粕の効果を最大限発揮させるには、保存方法や調理方法に注意しなければなりません。ここでは、酒粕を活かす保存方法、調理の際の注意点を解説します。
酒粕の保存方法
酒粕の保存は常温・冷凍どちらでも問題はありません。しかし、直射日光が当たらないことや高温多湿を避け、涼しいところで保存することが重要です。また、冷凍することで長期保存することが可能です。これから各保存方法のポイントを説明します。
常温保存
常温の場合、直射日光を避けて冷暗所で保存します。
酒粕は生ものなので、常温のなかで保管していると熟成が進みます。買った後は冷蔵、もしくは冷凍保存すると熟成が遅くなります。
常温の保存期間は、未開封で3ヶ月程度です。開封後はできるだけ早く使い切るか、使い切れない場合は冷蔵保存が推奨されます。
冷蔵保存
冷蔵庫で保存すると熟成の進行具合が遅くなり、常温よりも長く保存できます。
酒粕にはアルコールが含まれているため菌が増殖しにくく長期保存できますが、それでも風味は損なわれていくので、早く使い切るのがおすすめです。
冷凍保存
冷凍保存する場合、ラップで小分けして包んだ後、ファスナーで密封できる袋に入れておくことで新鮮な状態を保てます。冷凍保存の場合でも保存期間は1年程度にしましょう。
酒粕を調理するときの注意点
酒粕には100gあたり8.2gのアルコールが含まれており、ビールより多めです。
アルコールは78℃が沸点なので、加熱調理すればある程度のアルコールはとびます。しかし、完全に全てのアルコールをとばすことはできません。調理後も少しのアルコールは残ることは意識しておく必要があります。
そのため妊娠中の方が酒粕を食べると、胎児に悪影響を及ぼす危険性があります。なので、妊娠中は酒粕を使った食べ物や飲み物に注意しましょう。
また、酒粕を多量に食べると、酔いがまわる可能性があります。酒粕を食べて酔いがまわった感覚がある場合は、運転を控えましょう。
まとめ:身体の内面・外面に効果がある酒粕
酒粕は、肌改善や冷え性改善などさまざまな効果を発揮する食品です。
酒粕のメリットは多くの方に注目されているため、今後のさらなる研究が望まれます。
酒粕に関連する商品・サービスを提供する際は効果のほか、食べ方や保存方法についても丁寧に伝えましょう。
一覧へ戻る