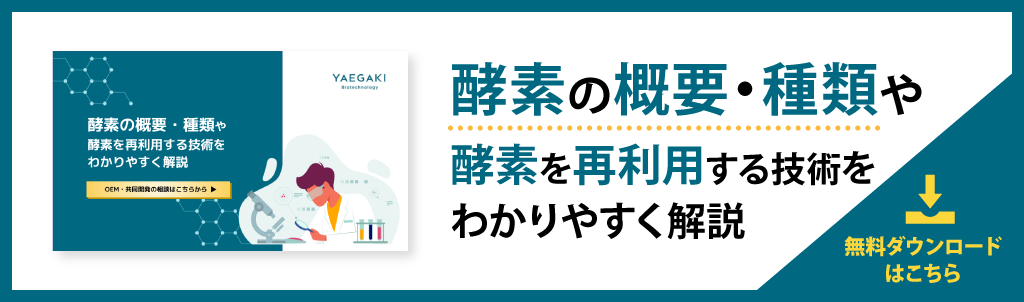腸活に関する最新の研究|健康に役立つ新たな取り組みを解説
近年は、健康増進のために腸活に励む人が増えています。
食生活の改善やサプリの導入など、腸活の手法も多様化しており、現在では誰もが気軽に取り組めるものとなりました。
加えて、腸活に関する最新の研究は現在進行形で進められており、その結果、腸活に関する新たな取り組みが発見されました。
本記事では腸活の基本的な知識や、最新の研究などについて解説します。また、腸活を効率的に進める取り組みも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
※研究開発コラムは微生物を活用した研究開発において参考になるトピックを集めたもので、全てのテーマについて当社が研究開発を実施しているわけではございません。
目次
腸活とは
ここでは、まず腸活の基本的な知識について解説します。最新の研究について学ぶ前に、あらためてチェックしましょう。
腸活の概要
腸活とは、腸内環境を整え、健康増進を目指す取り組み全般を指す用語です。
元々人間の腸には約数十兆~数百兆個におよぶ腸内細菌が生息しています。大量の腸内細菌は観察すると花畑のように見えることから、「腸内フローラ」と呼ばれています。
腸内細菌の種類は大きく分けて3つあり、それぞれ以下のとおりです。
- ・善玉菌…悪玉菌の増殖を抑え、健康に良い影響を与える人間にとって有益な細菌
- ・悪玉菌…腸内で有害物質を産生する細菌。
- ・日和見菌…腸内で悪玉菌が多いと有害物質を産生するが、善玉菌が多いと無害な細菌
そして腸活においては、善玉菌30~40%・悪玉菌10%・日和見菌50~60%のバランスを保つことが理想とされています。
一方、腸活は特定の善玉菌ばかり摂取する取り組みではありません。特定の腸内細菌の勢力が強まると腸内フローラのバランスが崩れ、かえって悪影響を及ぼす恐れがあります。
そのため、さまざまな種類の菌をバランス良く摂取し、腸内フローラの多様性を守ることが重要です。
腸活が注目される背景
腸活が注目されるようになった背景には、腸内環境が健康に与える影響が挙げられます。近年、医療技術の進歩から、腸内環境の重要性が注目されるようになりました。
以前、腸内環境の改善は便通改善の効果しかない印象を持たれていました。しかし、腸内環境の改善には便通改善だけでなく、以下のような効果が期待できます。
- ・肥満の改善
- ・免疫の維持
- ・肌荒れの防止など美容に関する効果
- ・睡眠の質の向上
上記以外にも腸内環境が関係している疾患は存在しており、躁うつ病のような精神疾患にも腸内細菌との関連性があることも発見されています。
そのため、昨今は健康増進のために腸活が有効的な手段として注目されるようになりました。
一方、腸活に関する研究は日々進められています。悪玉菌と思われていた細菌が健康改善に役立ったり、逆に善玉菌が健康に悪影響を及ぼしたりするなど、定説が覆るような発見も少なくありません。
そのため、今後も腸活に関する研究はより一層注目されるでしょう。
従来の腸活の取り組み
従来の腸活の取り組みは、大きく分けて「プロバイオティクス」「プレバイオティクス」「シンバイオティクス」の3種類を用いて行われます。本章では、これら3種類を用いた腸活をそれぞれ解説します。
プロバイオティクス
プロバイオティクスは腸活の基本となるものであり、健康に良い影響を与える善玉菌を直接摂取するための微生物や食品を指します。
プロバイオティクスによる腸活では、主にビフィズス菌・乳酸菌・納豆菌・酪酸菌などのような善玉菌を摂取します。いずれも健康改善に役立つ作用があり、腸活において重要視されているものです。
善玉菌を摂取する際にもっともよく利用されている食品は、発酵食品や乳製品です。特に発酵食品は、納豆やヨーグルトなどのような身近な食材で気軽に摂取できます。
一方、プロバイオティクスは肝心の善玉菌が腸にまで届かなければ効果がありません。
そのため、いかに生きた状態で腸内に届けるかが課題です。
近年では、多くの企業が独自に発見・開発した善玉菌を摂取できる食品やサプリメントが増えており、腸内に生きた善玉菌を届けられるものも増えています。その影響もあり、以前よりプロバイオティクスによる腸活は手軽に実践できるようになりました。
プレバイオティクス
プレバイオティクスとは、腸内の善玉菌に良い影響を与える食材や成分です。
腸内の善玉菌は特定の成分を栄養とすることにより、増殖する事で健康に役立つ働きをしたり、代謝物を産生したりします。そのためプレバイオティクスによる腸活は善玉菌がより活発に活動するよう、エサを補給することを目的としています。
プレバイオティクスで重視される成分の代表は、オリゴ糖・食物繊維・難消化性でんぷんです。オリゴ糖・食物繊維・難消化性でんぷんは野菜類・豆類・果物・海藻類などに含まれており、いずれも善玉菌の栄養分として高い効果を発揮します。
なお、プレバイオティクスはただ善玉菌を活性化させることだけが目的ではありません。
腸内細菌には、細菌にとっての栄養分が不足すると腸内の粘液を食べる種類がいます。このような状況になると、腸内のバリア機能が低下し、病原菌が侵入しやすくなるため、健康リスクが増大します。
そのため、プレバイオティクスによって腸内細菌のエサを安定的に供給することは、消化管粘膜のバリア機能を守ることにもつながる取り組みです。
シンバイオティクスの推奨
シンバイオティクスは、近年医療現場でも投入されている新しい概念です。
シンバイオティクスは、プロバイオティクスとプレバイオティクスを同時に摂取できる食品や成分を指します。つまり、善玉菌とそのエサとなる成分を同時に摂取し、腸内環境を整えることを目的としています。
シンバイオティクスは医療現場で積極的に実践されており、がんのような重病を抱える患者の合併症を抑制するなど、さまざまな効果が報告されています。
腸活および腸内フローラに関連する最新の研究
本章では、腸活や腸内フローラに関連する最新の研究についてそれぞれ順番に解説します。
グアーガム分解物の発見
グアーガム分解物とは、次世代の水溶性食物繊維として注目されている成分です。正確には、パキスタンやインド北部などで食べられているグアー豆に含まれるグアーガムを酵素分解したものです。
グアーガム分解物には、通常の水溶性食物繊維よりも短鎖脂肪酸の産生量を増加させる効果があり、腸活においても高い効果が期待できます。さらにミネラルの吸収促進・コレステロールの改善・血糖値の上昇抑制など、さまざまな効果も発見されました。
近年は技術の発展に伴い、グアーガム分解物を利用したサプリメントや健康食品が開発されています。
参考:栄養治療センター通信|東邦大学大森病院栄養治療センター
ポストバイオティクスの推奨
ポストバイオティクスとは、善玉菌が生み出す生体に有用な代謝成分を指し、これらを培養液などから抽出し直接摂取することを目的としています。
ポストバイオティクスではさまざまな善玉菌の代謝物が注目されており、代表的なものには短鎖脂肪酸やγ-アミノ酪酸などが挙げられます。
また、腸内に常在する善玉菌の代謝物産生を促す栄養素の摂取もポストバイオティクスの一環です。ビタミンB群やn-3系脂肪酸などの成分は、腸内に常在する善玉菌に作用し、代謝物の産生を活発化させます。
ポストバイオティクスなら効率的に有効成分を摂取できることから、ポストバイオティクスを用いた腸活は今後も注目されています。
腸内フローラによる膣内フローラへの影響
腸内フローラと同様に、女性の膣にも膣内フローラと呼ばれる細菌の集まりがあります。
膣内フローラは腸内フローラと同様、バランスが崩れると、性感染症や子宮頸がんなどのリスクが高まるうえに、妊娠率・着床率にも影響をおよぼします。
そのため、膣内フローラも善玉菌を増やし、適切なバランスを維持しなければなりません。
膣内フローラの場合、ラクトバチルス属の乳酸菌が善玉菌として機能していますが、これらの善玉菌は腸内フローラと連動しています。つまり、腸内フローラを改善すれば、善玉菌が膣内に移動し、膣内フローラのバランスを整える効果が期待できます。
参考: 腸活ナビ 腸内フローラと膣内フローラの不思議な関係(大正製薬製品情報サイト)
難病として知られているパーキンソン病ですが、最近は腸内環境と関連があることが発見されました。
2022年の名古屋大学の研究によると、腸内細菌の減少によって短鎖脂肪酸が産生されない状態ではパーキンソン病が発症するリスクが高まることが明らかになりました。
そのためパーキンソン病治療の一環として、短鎖脂肪酸を産生する腸内細菌の増加が進行抑制に効果的と期待されています。
参考:パーキンソン病患者において世界中で共通して認められる腸内細菌叢の変化を明らかにした|日本医療研究開発機構
推奨される新たな腸活の取り組み
最近は腸活のやり方が多様化しており、より効率的に腸内環境を整備する方法が登場しています。そこで本章では新たな腸活の取り組みについて解説するので、ぜひ参考にしてください。
アプリによる手軽な腸活管理
最近は、スマートフォンのアプリを利用して腸活をよりスムーズに進めることができるようになりました。特に、腸音をAIに分析してもらって腸の状態を把握できるアプリや、便の状態を記録して調べられるアプリが人気を集めています。
参考:
腸note AI活用ノウハウが示す可能性とは(SUNTORY LIFESTYLE DX分科会 REPORT)
ウンログ – No.1観便&腸活サポートアプリ
また、自分にあった腸活の方法を紹介してくれるアプリも注目されています。
便秘解消のための医療用デバイスの開発
便秘解消のために腸活に取り組んでいる方向けに、最近は専用の医療用デバイスも開発されています。
VIBRANT社が開発中のVibranは、白いカプセル型の医療用デバイスです。直接飲むと振動によって腸内で蠕動を起こし、便秘を解消できます。
参考:便秘を「振動する錠剤」で治療(m3.com 臨床ダイジェスト 2023年2月27日 MDLinx)
専用のアプリを利用すれば状況のチェックもできるため、使い勝手が良い医療用デバイスとなることが期待されます。
まとめ:最新の研究を知れば腸活の新しい取り組みがわかる
最近は、健康増進のために多くの人が積極的に腸活に取り組むようになりました。腸活に関する研究も進められており、新しい発見も次々と発表されています。
現在では、腸活はただの健康増進に留まらず、疾病を予防する取り組みとしても注目されています。そのため、腸活の重要性はますます向上するでしょう。
腸活に関する最新の研究を知れば、新しい取り組みを迅速にチェックできます。ぜひ積極的に学んでください。
一覧へ戻る