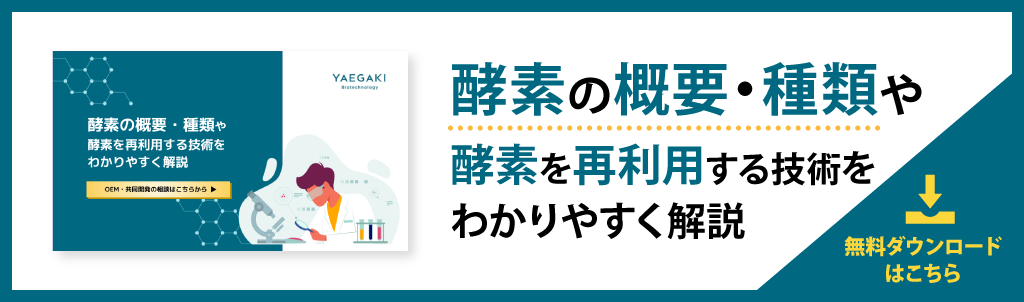プレバイオティクスとは?特徴や魅力、最適な摂り方を解説
プレバイオティクスは腸内環境を整え、健康をサポートする食品成分として注目されています。
善玉菌のエサとなり、腸内フローラのバランスを改善する効果が期待できるため、健康志向の高まりとともに需要が増加しています。
そこで本コラムでは、プレバイオティクスの基本的な特徴や摂取のメリット、効果的な摂取方法について詳しく解説します。
プレバイオティクスに興味のある方は、ぜひ最後までご覧ください。
※研究開発コラムは微生物を活用した研究開発において参考になるトピックを集めたもので、全てのテーマについて当社が研究開発を実施しているわけではございません。
目次
プレバイオティクスとは?
プレバイオティクスとは、胃や小腸で分解・吸収されることなく大腸まで届き、腸内に生息する微生物の栄養源となる難消化性のオリゴ糖や、食物繊維などの食品成分を指します。
プレバイオティクスは病原性細菌を抑制する抗生物質(アンチバイオティクス)に対抗する概念として、1994年にイギリスの微生物学者Gibson氏らによって提唱されました。
難消化性は、お腹の調子を整えるオリゴ糖の主な特徴です。
通常、食べ物は口から摂取されると胃液などの消化酵素によって分解され、小腸で消化・吸収されます。
しかし、オリゴ糖はこれらの酵素ではほとんど分解されず、小腸で消化・吸収されることなく大腸まで届きます。
オリゴ糖は糖質として体のエネルギー源になりにくく、摂取しても血糖値の上昇にほとんど影響を与えません。
大腸に届いたオリゴ糖は、善玉菌として広く知られているビフィズス菌を増やしてくれるため、腸内環境の改善につながります。
プレバイオティクスとプロバイオティクスとの違い
プレバイオティクスは善玉菌の増殖を促す食品を指すのに対し、プロバイオティクスとはそのもの自身が善玉菌ともなりうる生きた微生物、または食品のことです。
プロバイオティクスとして認められる条件は、以下の通り腸内細菌学会が定めています。
- 1.安全性が保証されている
- 2.もともと宿主の腸内フローラの一員である
- 3.胃液、胆汁などに耐えて生きたまま腸に到達できる
- 4.下部消化管で増殖可能である
- 5.宿主に対して明らかな有用効果を発揮できる
- 6.食品などの形態で有効な菌数が維持できる
- 7.安価かつ容易に取り扱える
引用:プロバイオティクス(probiotics)|用語集|腸内細菌学会
プロバイオティクスは、1989年にイギリスの微生物学者Fuller氏によって提唱されたもので、「腸内フローラのバランスを改善することによって宿主の健康に有益に働く生きた微生物」と定義されました。
プロバイオティクス食品の具体例としては、ヨーグルト・乳酸菌飲料(乳酸菌やビフィズス菌)・チーズ・納豆・ぬか漬け・味噌・甘酒・キムチなどです。
プロバイオティクスには下痢や便秘を抑える、腸内環境を改善する、免疫力を回復させる、腸内の感染を予防するなどの効果があります。
プレバイオティクスの主な働き
プレバイオティクスの主な働きは、主に以下2つです。
- ・腸のぜん動運動を刺激
- ・腸内細菌のバランスを整える
ぜん動運動とは、消化管の壁が狭まったり広がったりを繰り返しながら食べ物を押し進める運動のことです。自分の意志とは関係なく、自動的に体がおこなっています。
プレバイオティクスには主に大腸での腸内細菌叢の変化を介して腸のぜん動運動を促す働きがあり、腸が健康的に動くことで消化がしやすくなる、便通を促して便秘を防ぐなどの効果が期待できるでしょう。
また、便通が促されれば、便と一緒に悪玉菌が作り出した腐敗物質も体外へ排出されます。
さらに、プレバイオティクスは腸内のビフィズス菌のエサ隣、腸内細菌のバランスを整えます。
プレバイオティクスに要求される条件
プレバイオティクスとして認められる条件は、以下の通り腸内細菌学会が定めています。
- 1.消化管上部で加水分解、吸収されない。
- 2.大腸に共生する一種または限定された数の有益な細菌(ビフィズス菌等)の選択的な基質であり、それらの細菌の増殖を促進し、または代謝を活性化する。
- 3.大腸の腸内細菌叢(フローラ)を健康的な構成に都合の良いように改変できる。
- 4.宿主の健康に有益な全身的な効果を誘導する。
引用:プレバイオティクス(prebiotics)|用語集|腸内細菌学会
具体的には、次に詳しく解説するオリゴ糖、水溶性食物繊維などがプレバイオティクスに該当します。
プレバイオティクスの食品成分
ここからは、プレバイオティクスとしての要件を満たす食品成分を2つ紹介します。
オリゴ糖
オリゴ糖とは、糖質の最小単位である単糖が2~10個程度結びついたものです。「少糖」とも呼ばれ、一般的には3つ以上の糖が結びついたものを指します。
オリゴ糖は難消化性のため、胃や小腸で消化されずに大腸まで届きます。
そして大腸まで到達したオリゴ糖は、善玉菌によって分解・代謝されます。代謝されることで善玉菌はさらに増えやすくなり、腸内環境が整えられるのです。
善玉菌が活発になると悪玉菌など有害な菌の増殖が抑えられ、便通改善、免疫力向上などに役立ちます。
食物繊維
食物繊維は、小腸で消化・吸収されない物質です。食べ物の中に含まれているもので、小腸を通り過ぎて大腸まで達します。
便通を促しているのは、プレバイオティクスに含まれている食物繊維によるものです。
食物繊維には水に溶ける水溶性食物繊維と、水に溶けない不溶性食物繊維があります。
水溶性食物繊維とは、腸内の水に溶けてゲル状になり、便をやわらかくしたり腸内環境を整えたりする働きがある食物繊維です。
一方、不溶性食物繊維は、腸のぜん動運動や便通の改善に役立つもので、水に溶けない性質を持つものを指します。
プレバイオティクスを含む食品・飲み物一覧
ここからは、プレバイオティクスを含む主な食品・飲み物を紹介します。
大豆
大豆は食物繊維やオリゴ糖を豊富に含むため、プレバイオティクス効果が期待できます。
特に発酵食品である納豆や味噌は腸内で善玉菌の栄養源となり、腸内環境を整えるのに役立ちます。
ごぼう
ごぼうは食物繊維が豊富で、特にイヌリンという難消化性の成分が含まれています。
イヌリンは腸内で発酵され、善玉菌の栄養源となるため、腸内環境を改善する効果があります。
ごぼうに含まれるイヌリンの量は、3.5~4%程度です。
イヌリンには他にも血糖値の低下・ 利尿作用などがあり、腸内フローラのバランスも整えてくれます。
参考:時間生物学を利用した機能性食品開発 ~イヌリンのヒト試験を中心に~
こんにゃく
こんにゃくは、グルコマンナンという水溶性食物繊維を豊富に含んでいます。腸内で分解されにくく、善玉菌のエサとなるため、腸内環境を改善します。
また、低カロリーで満腹感を得やすいので、減量のサポートとして活用することも可能です。
海藻類
海藻類は食物繊維が豊富で、アルギン酸やフコイダンなどの成分を含みます。特に多く含まれている水溶性食物繊維が腸内で善玉菌の増殖を促進し、腸内環境を整えるのが大きな特徴です。
また、海藻にはミネラルやビタミンも豊富に含まれており、栄養バランスの向上や免疫力の強化にも寄与します。
昆布やわかめ、ひじき、めかぶなどの海藻類の積極的な摂取で、腸内フローラが整います。
ケフィア
ケフィアとは発酵乳製品の一種で、牛乳や山羊の乳に「ケフィア粒」と呼ばれる、酵母や乳酸菌の共生体を加えて発酵して作る飲み物です。
ケフィア粒は、数mmから数cmの粒状をしています。カリフラワーのようなプルプルとした粒々が特徴で、乳酸菌が目に見える形で存在する珍しいものです。
発酵によって乳糖が乳酸に変わるため、乳糖不耐症の人でも比較的飲みやすいとされています。
ケフィアは腸内フローラのバランスを整えるだけでなく、免疫力を高める効果も期待されています。
甘酒
甘酒は、お米と麹菌を発酵させた飲み物です。栄養価が非常に高く、ノンアルコールのため子供から高齢者まで幅広い層に親しまれています。
甘酒には数種類のオリゴ糖が含まれており、腸内フローラを整える効果があることから腸活にも有効です。
特に米麹と米から作られる甘酒は便秘解消に役立つとされる研究結果もあり、腸内環境の改善に注目されています。
参考:【世界初】甘酒を飲んで、便通改善、コレステロール低減、肥満抑制。応用バイオ学科尾関研究室が企業との共同研究で学術的に初めて実証 | ニュース | KIT 金沢工業大学
ヨーグルト
ヨーグルトは、乳酸菌を豊富に含む発酵食品です。腸内の善玉菌を増やす効果が高く、腸内環境の改善に非常に効果的とされています。
特に、プレバイオティクス成分であるガラクトオリゴ糖は、腸内のビフィズス菌を増やして腸内環境を整える力があります。
参考:β 1-4系ガラクトオリゴ糖のヒト腸内菌叢に及ぼす影響
さらにガラクトオリゴ糖が加えられたヨーグルトもあわせて摂ると、腸内フローラのバランスを整える効果が一層高まります。
また、ヨーグルトはカルシウムやビタミンDも豊富に含んでおり、骨の健康維持に役立つ点も魅力です。
牛乳
牛乳にはラクトースというプレバイオティクス成分が含まれており、腸内で善玉菌の栄養源として働き、腸内環境を整える効果があります。
さらに、牛乳に含まれるカルシウムやビタミンDは、骨の健康維持や免疫力の向上にも重要な役割を果たします。発酵乳製品と組み合わせることで、さらに高い効果が期待できるでしょう。
プレバイオティクスの効果的な摂り方
ここでは、プレバイオティクスを効果的に摂る4つの方法をお伝えします。
プロバイオティクスとの併用摂取
プレバイオティクスと一緒に生きた善玉菌であるプロバイオティクスを摂ると、腸活の効果が高まります。
プレバイオティクスとプロバイオティクスを一緒に摂ることを「シンバイオティクス」といいます。
シンバイオティクスは、接頭辞の「syn(一緒に、共に)」と、生物を意味する「biotic」を組み合わせた言葉です。
シンバイオティクスを実践すると、体内の善玉菌・悪玉菌・中間の菌のバランスをちょうどよい状態に保つことが可能です。
継続的な摂取
腸によい食品をこまめに摂取すれば、プレバイオティクスの効果をさらに感じられます。
腸内環境は毎日変化するものであり、ストレス・遅い時間の食事・脂質の多い食事・睡眠不足などが原因で悪玉菌も増加します。
悪玉菌を増やしにくくし、腸内環境を良好に保つためには、1回摂取するだけでなく、継続して毎日摂り続けることが重要です。
まずは2週間の摂取
プレバイオティクスの摂取は、まずは2週間試すことが重要です。
腸内細菌は、腸内において同じ菌の種類同士の塊を作ります。菌同士の塊は腸内フローラと呼ばれますが、腸の中で定住する菌が決まった後はほとんど変化しません。
善玉菌を一度取り入れただけでは腸内に定住しませんが、継続的に摂取することで腸内フローラの一部として機能しやすくなります。
そのため、無理なく継続しやすい方法でプレバイオティクスを摂取することが大切です。
プレバイオティクスが入ったサプリの摂取
プレバイオティクスが含まれるサプリメントなら、忙しい日常の中でも手軽に必要な量を摂取できます。
オリゴ糖や食物繊維など、腸内の善玉菌のエサとなる成分が含まれているサプリを補助的に利用すると効果的です。
なお過剰摂取は体調不良を起こす原因となる事もあるため、サプリメント開発の際は正しい飲み方について繰り返し呼びかけることが重要です。
まとめ
プレバイオティクスは腸内環境を整え、健康をサポートする食品成分です。
プレバイオティクスにはオリゴ糖と食物繊維があり、食物繊維は主に水溶性食物繊維がプレバイオティクスとして働きます。
善玉菌のエサとして機能することで、腸内フローラを改善します。
プレバイオティクスの効果をさらに高めるには、プロバイオティクスと合わせて摂取することが重要です。
また最低でも2週間の摂取が推奨されているため、消費者にはプレバイオティクスの理想的な摂り方を繰り返し伝えていきましょう。
一覧へ戻る