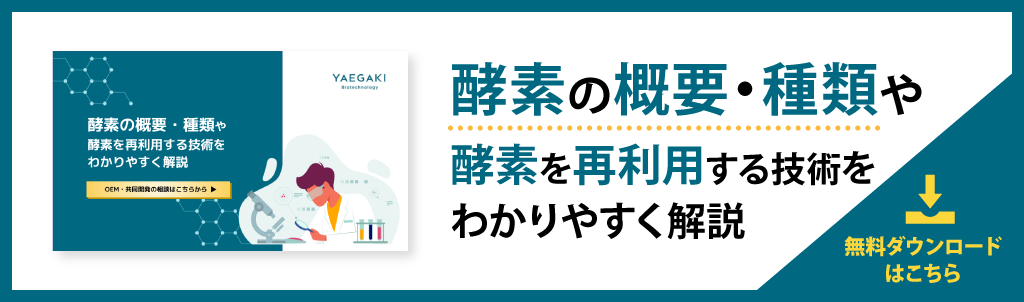乳酸菌における球菌と桿菌の違いとは
乳酸菌は多様な動植物と共生しており、私たち人間の生活でも欠かせない微生物です。
乳酸菌は、その形状や機能により乳酸球菌と乳酸桿菌の2つに分けられ、それぞれ異なる健康効果をもたらします。
本記事では、乳酸球菌と乳酸桿菌の基本的な特徴や役割、含まれる食品例などを詳しく解説し、これらの乳酸菌を効果的に取り入れる方法について考察します。
※研究開発コラムは微生物を活用した研究開発において参考になるトピックを集めたもので、全てのテーマについて当社が研究開発を実施しているわけではございません。
目次
球菌と桿菌の基本的な形状と構造の違い
球菌と桿菌では、形状と構造が異なります。この形状と構造の違いが、生物学的特性に影響しています。ここでは球菌と桿菌の違いについて、基本的な部分を解説します。
球菌の形状と構造の特徴
球菌は名前の通り球形で、直径約0.5~2.0μmの大きさです。単独、双球菌、四連鎖、葡萄の房状など様々な分裂形式の違いによる形態で見られます。
代表的な球菌には、Staphylococcus属ブドウ球菌があります。またStreptococcus属も球菌ですが、感染症を引き起こすStreptococcus pyogenes(溶血性連鎖球菌)や、Streptococcus thermophilusのように乳製品にも利用される有用菌が含まれます。
球菌は、グラム染色で紫色に見えます。これは、細胞壁の厚いペプチドグリカン層が、グラム染色の結晶紫を保持するためです。そして、この厚い細胞壁によって、グラム陽性菌は非常に強い外部からのストレス耐性を持ちます。
また、球菌には黄色ブドウ球菌・溶血性連鎖球菌・肺炎球菌など、感染症の原因となるものも多く確認されています。
参考:乳酸菌とはどのような菌ですか?|一般社団法人 日本乳業協会
桿菌の形状と構造の特徴
桿菌は棒状の形態を持ち、長さが2~10μm、幅が0.5~1μm程度です。
代表的な桿菌には、大腸菌(Escherichia coli)やバシラス属(Bacillus)が含まれます。
桿菌は、グラム染色で陽性と陰性の両方が存在します。グラム陽性の桿菌は厚いペプチドグリカン層を持ち、グラム陰性の桿菌は薄いペプチドグリカン層の外側にリポ多糖層を持つのが特徴です。この構造の違いが、抗生物質の効果や抵抗性に影響を与えます。
桿菌は二分裂によって増殖し、環境条件に応じてエンドスポア(芽胞)を形成するものもあります。
エンドスポアとは、厳しい環境条件に耐えるために特定の細菌が形成する耐久性の高い構造体です。エンドスポアは栄養不足・高温・放射線・化学物質などの過酷な条件下でも生存する能力があります。
参考:
乳酸菌とはどのような菌ですか?|一般社団法人 日本乳業協会
細菌芽胞(胞子)一その特徴と調製法,抵抗性試験法,第14改正日本薬局方での関連記載項目および芽胞形成菌管理の意義一
球菌と桿菌の顕微鏡観察による違い
顕微鏡観察では、球菌と桿菌の形状の違いは明確です。
球菌は球形で対や連鎖状に配置され、桿菌は棒状で単独または短い鎖状に見えます。これらの形状や配置は、細菌がどのように成長し、環境に適応するかを示しています。
球菌は光学顕微鏡で観察すると丸い形状で、しばしば複数の細菌が集合している様子が見られます。連鎖球菌は連なった鎖のように見え、ブドウ球菌は葡萄の房のような配置です。これらの配置は、細菌が分裂する際の方向性によって決まります。
一方、桿菌は光学顕微鏡で観察すると棒状の形態です。大腸菌は短い棒状で、単独で存在することが多いのに対し、バシラス属は長い鎖を形成することがあります。
球菌と桿菌の観察結果などを基にした迅速な細菌同定により、適切な治療や予防策が講じられます。
乳酸菌としての球菌と桿菌の役割と機能
乳酸菌にも、球菌と桿菌の2種類があり、それぞれが持つ形状の違いによって異なる役割や機能があります。
この章では、乳酸球菌と乳酸桿菌の具体的な役割と健康効果について詳しく解説します。
乳酸球菌の役割と健康効果
乳酸球菌は、主に腸内環境の改善や免疫力の向上に役立ちます。代表的な乳酸球菌には、ラクトコッカス・ラクティス(Lactococcus lactis)やエンテロコッカス・フェカリス(Enterococcus faecalis)があります。
これらの球菌は発酵食品であるヨーグルトやチーズ、漬物などに含まれており、ラクトコッカスは特に発酵乳製品のスターターとして広く使われています。乳酸球菌は短期間で増殖するため、早期に効果を実感しやすい点も特徴です。
さらに、乳酸球菌には免疫細胞を刺激し、体内の自然免疫を活性化する働きがあります。マウスによる実験では、すでに風邪やインフルエンザなどの感染症の予防効果が認められています。
参考:Lactococcus lactis JCM5805 の免疫調節能に関する研究|腸内細菌学会
乳酸桿菌の役割と健康効果
乳酸桿菌は、主に消化促進や抗炎症作用に優れています。
代表的な乳酸桿菌には、ラクトバチルス・アシドフィルス(Lactobacillus acidophilus)やラクトバチルス・カゼイ(Lactobacillus casei)があります。
これらの桿菌は腸内に定着しやすく、長期的に腸内環境を安定させる働きがあります。乳酸桿菌は乳酸を産生することで腸内を酸性に保ち、有害な細菌の増殖を抑えます。
さらに、桿菌は消化酵素の分泌を促進し、食物の消化吸収を助けます。これにより、便秘の改善や栄養吸収率の向上が期待できます。
また、乳酸桿菌には腸内の炎症を抑える抗炎症作用があり、大腸癌の予防に寄与します。腸管上皮のバリア機能を強化・修復し、病原菌の侵入を防ぐ働きも確認されています。
参考:
乳酸菌の抗腫瘍効果|(株)ヤクルト中央研究所
腸内細菌による腸管上皮バリア機能の強化・修復|腸内細菌学会
乳酸球菌と乳酸桿菌が含まれる食品とその健康効果
乳酸球菌と乳酸桿菌は様々な食品に含まれ、それぞれ異なる健康効果をもたらします。
この章では、これらの食品例とそれぞれの健康効果について詳しく解説します。
乳酸球菌が含まれる食品例とその効果
乳酸球菌は、主に乳製品の発酵食品に含まれています。
例えば、ラクトコッカス・ラクティス(Lactococcus lactis)はチーズやバター、ヨーグルトなどに多く含まれます。これらの食品は、腸内の善玉菌を増やし、腸内フローラのバランスを整える効果があります。腸内環境が改善されれば、便秘の解消や免疫力の向上が期待できます。
さらに、乳酸球菌は、味噌や納豆などの発酵食品にも含まれています。これらの食品は、日本の伝統的な食文化の一部であり、健康維持に欠かせない存在です。味噌や納豆に含まれる球菌は消化吸収を助ける酵素を生成し、食事からの栄養摂取を効率化します。
参考:食品における乳酸菌の利用とその働き|日本調理学会誌 Vol.41, No. 1, 55~60(2008)
乳酸桿菌が含まれる食品例とその効果
乳酸桿菌は、ヨーグルトやケフィア、サワークラウトなどの発酵乳製品や発酵野菜に多く含まれています。
代表的な乳酸桿菌には、ラクトバチルス・アシドフィルス(Lactobacillus acidophilus)やラクトバチルス・プランタルム(Lactobacillus plantarum)があります。これらの桿菌は、腸内に定着しやすく、消化促進や腸内環境の安定化に寄与します。
乳酸桿菌が含まれる食品は、消化器系の健康サポートに有益です。例えば、ラクトバチルス・アシドフィルスを含むヨーグルトは、乳糖不耐症の人々に対しても消化を助ける効果があります。
さらに、乳酸桿菌は抗炎症作用を持ち、腸内の炎症を抑えることで腸炎や大腸癌のリスクを低減します。
乳酸球菌と乳酸桿菌の選び方と用途
この章では、球菌と乳酸桿菌の選び方と用途について詳しく解説します。
乳酸球菌を選ぶ際のポイント
乳酸球菌は、主に腸内環境の改善や免疫力の向上に効果があります。例えば、ラクトコッカス・ラクティスやエンテロコッカス・フェカリスを含む製品は、短期間で腸内の善玉菌を増やし、便秘の解消や免疫力の向上に役立ちます。
また、乳酸球菌はアレルギー症状の緩和や感染症の予防にも効果があるため、目的に応じて乳酸菌を選ぶ場合には、特定の菌種が含まれている製品を選びましょう。例えば、アレルギー症状の緩和にはラクトコッカス・ラクティスが効果的とされています。
乳酸球菌を含む製品としては、ヨーグルトやチーズ、味噌、納豆などがあります。製品を選ぶ際には、品質や保存状態にも注意を払いましょう。
参考:
臨床試験およびマウスモデルにおけるアトピー性皮膚炎に対するラクトコッカス・ラクティス11/19-B1株の効果
乳酸桿菌を選ぶ際のポイント
乳酸桿菌の代表例は、ラクトバチルス・アシドフィルスやラクトバチルス・カゼイなどです。これらの乳酸桿菌は消化器系の健康維持や腸内の炎症を抑え、長期的に腸内環境を整える効果があります。消化器系のトラブルを抱えている人や腸内フローラのバランスを保ちたい人にとって、乳酸桿菌は非常に有益でしょう。
また、これら乳酸桿菌は抗炎症作用を持つことも知られており、腸内環境をより良い状態に維持するために必要です。
乳酸桿菌を含む製品には、ヨーグルト、ケフィア、サワークラウト、キムチなどがあります。摂取する前には、製品の製造方法や保存状態をよく確認しましょう。また、長期的に効果を実感するためには、継続的な摂取も重要なポイントです。
参考:5種類のLactobacillus属乳酸菌由来ゲノム DNA の抗炎症作用機構に関する研究
目的別に見る球菌と乳酸桿菌の使い分け
目的に応じて乳酸球菌と乳酸桿菌を使い分けることが、より効果的な健康維持につながります。例えば、短期的に腸内環境を改善したい場合や免疫力を向上させたい場合には、乳酸球菌を選ぶと良いでしょう。一方、長期的に腸内フローラを安定させたい場合や消化促進を目的とする場合には、乳酸桿菌がピッタリです。
また、サプリメントとして両方の乳酸菌を摂取する方法もあります。これらの使い分けを実践することで、腸内環境の改善や全身の健康維持に大いに役立ちます。
まとめ:乳酸球菌と乳酸桿菌の特徴を理解し長期的な健康維持を
乳酸球菌と乳酸桿菌は、それぞれ異なる形状と健康効果を持つ乳酸菌です。
乳酸球菌は免疫力向上や腸内環境改善に即効性があり、乳酸桿菌は消化促進や抗炎症作用で長期的な健康維持に有用性があることが既に分かっています。
これらの特性を理解して、乳酸菌を含む多様な食品を、日常の食事にバランスよく取り入れることが大切です。製品開発、販売の際にも両者をうまく使い分けてターゲットの求めるニーズを満たしましょう。
一覧へ戻る