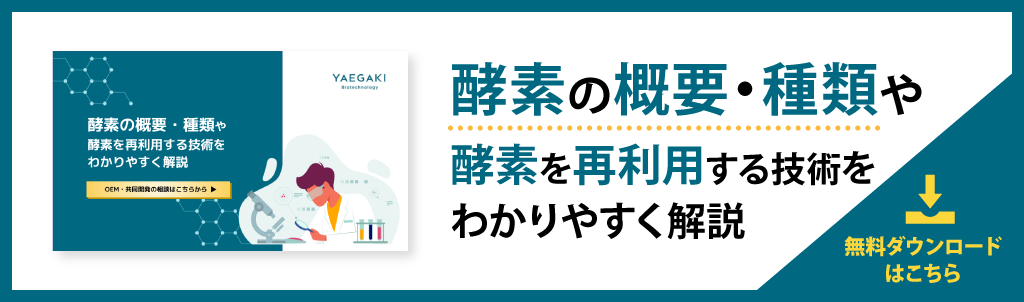乳酸菌による免疫力活性化のメカニズムと最適な摂取方法を解説
乳酸菌とは、腸内環境を整え、免疫力を高める効果が期待される善玉菌の一種です。
乳酸菌は、免疫力の向上や美肌効果など、体の健康維持に寄与します。
さらに近年は新型コロナウイルスの影響で健康志向が高まったことから、注目を集めてきました。
そこで本記事では、乳酸菌がどのようにして免疫細胞を活性化し、病原体に対する体の防御力を向上させるのか、メカニズムを解説します。
また、乳酸菌の効果を最大限に引き出すための最適な摂取方法についても紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
※研究開発コラムは微生物を活用した研究開発において参考になるトピックを集めたもので、全てのテーマについて当社が研究開発を実施しているわけではございません。
目次
免疫力とは
免疫力とは、体が外部からの病原体や異物に対して防御する力のことです。
免疫には、生まれつき体に備わっている自然免疫と、自然免疫では倒せないウイルスや菌を排除する獲得免疫の二つがあります。
自然免疫では、好中球やマクロファージ、NK細胞という免疫細胞が異物を攻撃します。
好中球やマクロファージは病原菌やウイルスを食べてくれる免疫細胞であり、好中球は主に血液中に、マクロファージは主に組織に存在します。病原菌が体内に入ると真っ先に攻撃を行うのが好中球です。
NK細胞は、体内で常に変異した自己細胞やウイルスの侵入を監視している免疫細胞であり、ウイルス感染細胞や変異細胞を見つけたら攻撃をします。
そして獲得免疫は、体内に侵入した病原菌やウイルスの種類を記憶し、次に同じ異物が侵入したときにすぐ攻撃する力を持ちます。
免疫系は白血球や抗体などの細胞や免疫物質が協力して、変異した自己細胞やウイルスや細菌、異物を認識・排除する役割を果たします。
免疫力が高いと、感染症に対する抵抗力が強く、体調の維持が可能です。逆に免疫力が低いと感染症にかかりやすくなり、体調を崩しやすくなります。
乳酸菌が免疫力の活性化につながる理由
乳酸菌の摂取は、免疫力の向上に最適です。ここからは、乳酸菌が免疫力アップに役立つ理由を解説します。
免疫細胞の活動を最適化するため
乳酸菌には、免疫細胞を活性化させる働きがあります。
マウスを使った実験では、乳酸菌がNK細胞を含むさまざまな免疫細胞を活性化することが確認されており、人での実験でも乳酸菌の摂取によってインフルエンザにかかりにくくなることが示されました。
インフルエンザなどのウイルスが侵入しにくくなるのは、ナチュラルキラー細胞の活性が高まるためです。
ナチュラルキラー細胞の活性は、ウイルスに感染した細胞をすぐに排除し、体内でウイルスを増やさない防御反応機能の高まりを指します。
乳酸菌には多くの亜種があり、例えば東京大学薬学部が発見した11-1乳酸菌は、長野県で受け継がれた特別なぬか床から作られたものです。
参考:11-1乳酸菌|11-1乳酸菌の開発販売は株式会社アンテナ
11-1乳酸菌は高い免疫活性力を持ち、病気に対する抵抗力を強化する効果が期待されています。
腸内環境が改善するため
善玉菌が増えると腸の動きが活発になり、腸内環境が整います。
腸内環境が整えば、腸に集まる多くの免疫細胞も活発に働くようになり、免疫力が向上します。
乳酸菌を摂取すれば、腸内の善玉菌の割合を増やすことが可能です。
善玉菌が増えれば腸内細菌叢のバランスが保たれたのち、結果的に体全体の免疫システムが強化され、病原体への抵抗力が高まります。
乳酸菌は免疫力アップだけではない
乳酸菌は免疫力を上げるだけでなく、がんの転移の抑制にも効果があることがわかっています。
2022年、東京大学の研究チームは、酵素処理乳酸菌素材「LFK」乳酸菌の研究を実施し、
LFKが乳がんやメラノーマの肺への転移を抑制できることが確認されました。
メラノーマとは、皮膚の色素細胞であるメラノサイトから発生する皮膚がんの一種です。
通常、メラノサイトは肌の色を決めるメラニンという色素を生成しますが、メラノーマが発生すると、メラノサイトが異常に増殖します。
人種によって発生率は異なりますが、日本人は10万人あたり1~2人とされ、希少がんとして扱われています。
「LFK」は新規性が高い点、がん患者の生存率やQOLの向上が期待される点で評価され、2022年10月4日に特許を取得しました(特許第7152733号)。
東京大学の研究チームが発表したLFKの研究は、がん治療における新たな可能性を示しており、今後の医療分野で活用されることが期待されています。
参考:酵素処理乳酸菌素材「LFK」でがんの転移を抑制、特許を取得 ――肺転移モデルを用いたLFKのがん細胞の肺への生着抑制効果―― | 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部
乳酸菌を摂るメリット
乳酸菌を摂るメリットは、健全な体の実現や老化防止など多くあります。ここから詳しく解説します。
健全な体を実現
乳酸菌の摂取は、健全な体の実現に大きく寄与します。
まず、乳酸菌は腸内の善玉菌を増やし、元々腸内の中にある腸内フローラのバランスを整えることで消化吸収をサポートし、便秘や下痢の改善に役立ちます。
便秘や下痢が改善して腸内環境が良好になると、食事から得られる栄養素がより効率的に吸収されます。
栄養素が体内に効率よく取り込まれることで日常生活での疲労感が軽減され、活力が維持されます。
また乳酸菌には免疫細胞を活性化させる働きもあり、病原体に対する体の抵抗力を高める効果も期待できます。
継続的な乳酸菌の摂取は、内側からの健康をサポートし、全体的な体の健康維持に役立つといえるでしょう。
老化防止
乳酸菌のなかには、老化を防げる可能性が示唆されているものもあります。
国立研究開発法人の農研機構(NARO)の研究者がおこなった実験では、マウスに特定の乳酸菌を与えたことで老化関連症状がおさえられたとする結果が出ました。
なお、実験で使ったマウスは、通常のマウスよりも寿命が短く、骨粗鬆症など老化によって発症する病気を持った「老化促進モデルマウス」です。
乳酸菌は、すでに老化が進んでいるモデルマウスに摂取しても効果がありました。
参考:Lactococcus lactis H61 の老化抑制効果と作用機構の解明に向けて
コレステロールの低減
乳酸菌には、コレステロールを低下させる効果が期待できます。
コレステロールには「善玉コレステロール」と「悪玉コレステロール」があります。
悪玉コレステロールが増えると動脈硬化が進行しやすくなり、心筋梗塞や脳梗塞などにつながります。
一方、乳酸菌は菌が持つ胆汁酸脱抱合酵素の作用により腸内での胆汁酸の再吸収を阻害・排泄を促進する力を持ちます。
そのため乳酸菌を摂取すると肝臓で新たに生成される胆汁酸のためにコレステロールが消費され、血中コレステロール濃度が低下します。
また、乳酸菌は腸内の善玉菌を増やして腸内フローラを改善することで、脂質代謝にもよい影響を与えるとされています。
乳酸菌の効果的な摂り方
ここでは、乳酸菌を効果的に摂る5つの方法をお伝えします。
食物繊維およびオリゴ糖との併用摂取
食物繊維は、腸内で乳酸菌の栄養源、つまり「エサ」として機能します。
食物繊維は便秘の解消にもつながるため、摂取すれば腸内で悪玉菌が増えにくい環境を作れます。
食物繊維が豊富な食品は、以下になります。
- ・しいたけ
- ・ひじき
- ・かぼちゃ
- ・ごぼう
- ・たけのこ
- ・さつまいも
- ・しらたき
- ・切り干し大根
- ・ブロッコリー
- ・モロヘイヤ
- ・あずき
- ・おから
- ・いんげん豆
- ・納豆
- ・そば
- ・ライ麦パン
また、オリゴ糖は胃酸に強く、分解されずに大腸まで届きます。
オリゴ糖が豊富に含まれている食品は、以下の通りです。
- ・たまねぎ
- ・ごぼう
- ・ねぎ
- ・にんにく
- ・アスパラガス
- ・大豆
- ・バナナ
腸内の悪玉菌の増加をおさえる食物繊維、胃に到達しても分解されないオリゴ糖と一緒に乳酸菌を摂ることで、効果的に体調を整えられます。
プロバイオティクスの活用
プロバイオティクスは、生きたまま腸に届き、悪玉菌の増加を抑制する微生物の総称です。
体内に入った後は腸内に到達し、元々腸内にいる「腸内フローラ」という菌のバランスを整え、悪玉菌の増加を抑えます。
しかし、摂取した乳酸菌は腸内フローラと共生することは稀であり、腸内で一定期間働いた後に排出されてしまいます。
そのため腸内の乳酸菌を維持・増加させるには、プロバイオティクスを毎日補充しなくてはなりません。
具体的な摂取方法としては、発酵食品や乳酸菌・ビフィズス菌が含まれている飲料や食べ物、サプリメントなどがあります。
3食すべてに乳酸菌含有食品を導入
朝食・昼食・夕食に1品ずつ、乳酸菌を含む食品を取り入れると、より効率よく乳酸菌が摂れます。
例えば朝に味噌汁、昼に漬け物、夜ご飯の後にデザート代わりとしてヨーグルトを食べるなどです。難しい場合、1日1回でもある程度の効果はあります.。
なお、どうしても難しければ、サプリメントを活用することも選択肢の1つです。
可能な範囲で乳酸菌を含む食品を摂ることが、効果的な摂取につながります。
乳酸菌入りのサプリと併用摂取
乳酸菌が入っているサプリメントをプラスαで摂るのも効果的です。
乳酸菌を食品から摂取するだけでなく、サプリメントも併用すれば、より効果的に腸内フローラのバランスを整えられます。
サプリメントの販売を行う際は表示について薬機法との関連も検討すると共に、原材料・製法・内容をしっかり提示し、安全性を伝えましょう。
毎日の摂取
乳酸菌は摂取すると体内に蓄積はされるものの、摂取をやめると少しずつ減っていきます。
効果を得るには継続的に摂ることが大切であると強調し、販売戦略に取り込みましょう。
乳酸菌の選び方と推奨される摂取量
本章では、乳酸菌の選び方と、おすすめとされる摂取量について解説します。
市場での乳酸菌製品の比較
市場にはさまざまな乳酸菌製品が販売されています。
近年は新型コロナウイルスの影響でより健康志向が高まったこともあり、乳酸菌製品の製造に力を入れている企業も少なくありません。
製品選びの際、含有する乳酸菌の種類や量、製造過程、添加物の有無などを確認する消費者もいます。
製品の品質管理体制や生産施設の信頼性までは購入時に考えていないかもしれませんが、わざわざ考えなくても絶対的な信頼を置いてる消費者のほうが多いでしょう。
企業側として、今後さらなる発展を目指すのであれば消費者の信頼に応え続けることが重要です。
適切な乳酸菌製品の選び方
消費者は、適切な乳酸菌製品を選ぶうえでニーズを重視します。
例えば、腸内環境の改善を目指す場合は、特定の乳酸菌株が有効である、乳酸菌の量などが多いなどとされる製品を選ぶでしょう。
また、乳酸菌の種類や含有量、添加物の有無、パッケージの保存条件を確認し、品質を保証する証拠がある製品を選びます。
企業側は消費者のニーズを常に把握し、それにそった製品をつくることが重要です。
乳酸菌の推奨摂取量
乳酸菌は、一般的には1日に100億〜1000億個を摂取することが推奨されています。
100億〜1000億個という推奨摂取量は、腸内での乳酸菌の生存・定着を促進するために必要な量です。
しかし製品によって含有量が異なるため、ラベルに記載された推奨摂取量は守らなくてはなりません。
さらに、個々の健康状態やライフスタイルに応じて摂取量を調整することも考慮すべきです。
まとめ:免疫力アップでも乳酸菌は重要
乳酸菌の摂取は、免疫力の向上や腸内環境の改善、さらには老化防止やコレステロール低減といった多岐にわたる健康効果が期待されます。
乳酸菌の効果を最大限に引き出すためには、毎日の継続的な摂取が必要であり、適切な量を守ることが大切です。
消費者が適切に乳酸菌を摂るためには、乳酸菌飲料や食品を製造する企業の努力が欠かせません。
企業が、消費者に安心して選んでもらえる製品を提供することは、今後の市場での競争力を維持するための重要なポイントとなるでしょう。
一覧へ戻る