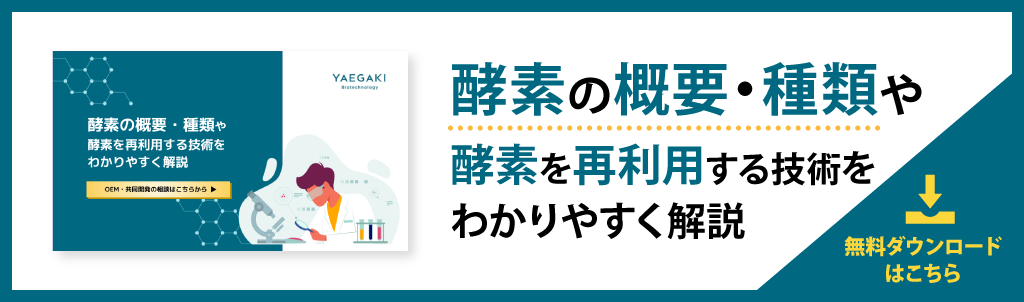麹菌の製造方法とその歴史|伝統的な技術と現代のアプローチ
「麹菌」は日本の国菌であり、日本では古くから麹菌を用いた多様な発酵食品を製造し、独特の食文化を形成してきました。
しかし麹菌とは一体何なのか、具体的にどのように製造するのかよくわからないとお悩みの方もいるでしょう。
そこで本記事では、麹菌の製造方法に着目し、麹菌の重要性や利用価値、詳しい製造方法や麹菌製造の注意点まで詳しく解説します。
麹菌に興味を持っている方、麹菌を生かして新しい事業に挑戦したい方はぜひ参考にしてみてください。
※研究開発コラムは微生物を活用した研究開発において参考になるトピックを集めたもので、全てのテーマについて当社が研究開発を実施しているわけではございません。
目次
麹菌とは
麹菌はカビの一種であり、日本の伝統的な発酵食品の製造に欠かせない微生物です。麹菌は主に米、麦、大豆などの穀物に作用して発酵を助ける酵素を生成し、味噌・醤油・日本酒などの製造に活用されてきました。
麹菌にはいくつかの種類があり、利用される食品や製造工程によって使い分けられます。
代表的な種類としては、味噌・醤油・日本酒の製造に使用される黄麹菌(Aspergillus oryzae)、泡盛に使用される黒麹菌(Aspergillus luchuensis)、そして主に焼酎に使用される白麹菌(Aspergillus kawachii)などがあります。なお、焼酎製造では白麹菌以外に黒麹菌や黄麹菌を使用し、いろいろな風味を出した焼酎も販売されています。
各種類の麹菌は異なる酵素を生成し、それぞれが独自の風味や香りを生み出します。
麹菌の製造方法
麹菌の製造方法は固体培養と呼ばれる方法と液体培養と呼ばれる方法があります。前者が主に伝統的な穀物『麹』を作る手法であり、後者が近代的な培養タンクなどを用いて、効率的に液体培地の中で麹菌を増殖させる手法です。
それぞれにはメリットとデメリットがあります。前者は『種麹』と呼ばれる麹菌が増えるのに最適な穀物に麹菌を植菌し、大量に麹菌を増やして乾燥させたものを用います。
つまり固体培養はこの種麹を大量の蒸した『固体』培地である穀物の上に振りかけて植菌し、『麹』として麹菌を増やす方法です。
固体培養なら麹菌の持つ酵素活性が非常に高い状態で麹菌を増やす事ができますが、穀物の中に麹菌の菌糸が入り込み代謝を行うため、麹菌のみでなく穀物が混じった『麹』としてのみ製造できるという点です。
一方、後者は麹菌を『液体』の栄養成分が詰まった培養タンクで増やすため、麹菌が十分に増えた後容易に麹菌のみを分離する事ができます。
また固体培養と異なり異物が混ざらないよう培地成分や空気まで滅菌・ろ過された閉鎖系の培養タンクで製造するため、他の微生物コンタミネーション(汚染)が無い非常に安全な製造法といえるでしょう。
ここからは固体培養の製造方法について詳しく見ていきます。
種麹の選定と準備
種麹の選定では、製品の最終的な風味や品質を考慮して目的に応じた種類を選びます。例えば、日本酒用の種麹と味噌用の種麹では、異なる特性の麹菌を選ばなくてはなりません。
選定後は種麹を適切な条件下で保存し、使用する際に必要な量を取り出して使用します。種麹の管理が不十分だと発酵が不均一になり、最終製品の品質が低下する可能性があります。
参考:種麹
麹菌培養の基本工程
麹菌の培養とは、米や大豆などの原料に種麹を混ぜ込み、適切な温度と湿度で発酵させる工程です。
まず、原料を洗浄し、蒸してから冷却します。次に、手や専用の機械を用いて種麹を原料に均一に混ぜ込みます。この時に重要なのは温度や湿度の管理です。適切な環境を維持することで、麹菌が最適に繁殖します。
発酵が進むと麹菌は酵素を産生し、原料のデンプンを糖化します。この工程では、麹菌の増殖とともに、適切な酸素供給が必要です。
最後に、発酵が完了した麹を乾燥させ、品質を保つために保存します。各工程での管理が徹底されていないと麹菌の活動が不十分になり、最終製品の品質に影響を与える可能性があります。
発酵と糖化
麹菌の発酵において、糖化の工程は非常に重要です。糖化工程とは、発酵原料から糖類を生成する働きです。具体的には、麹菌の産生するアミラーゼやグルコアミラーゼといった酵素が、デンプンを分解して糖を生成します。そして糖化工程で生成される糖は酵母によってさらに発酵され、アルコールやその他の発酵産物に変換されます。
糖化作用を適切に進行させれば、発酵食品の風味や栄養価が向上し、最終製品の品質が高まります。
重要なのは糖化プロセス中の温度や湿度、時間管理です。これらの条件が適切でない場合、糖化作用が不十分となり、発酵がうまく進まないことがあります。
麹菌 製造の重要性
この章では、麹菌製造の重要性について様々な観点から考察します。
麹菌製造と日本の食文化
麹菌は、日本の伝統的な食文化において非常に重要な役割を果たしてきました。日本酒や味噌、醤油といった代表的な発酵食品は、麹菌の働きにより作られます。
麹菌はデンプンを糖に分解する酵素を産生し、その結果作られる様々な糖類が乳酸菌や酵母菌など他の有用微生物の発酵を促進します。
この一連の複合的な発酵プロセスが独特の風味や香り、うま味を生み出し、有用菌が作る天然の抗菌物質や有機酸により食品の保存性を向上させるのです。
さらに、麹菌を用いた発酵食品はビタミンやアミノ酸などの栄養素を豊富に含んでおり、高い健康効果も期待されています。
日本の食文化は、長い歴史の中で麹菌とともに発展してきました。伝統的な製法と現代の技術が融合することで、品質の高い発酵食品が生産され続けています。麹菌の製造とその重要性を理解することは、日本の食文化の深さとその価値を再認識することに繋がります。
参考:伝統発酵食品に関する食文化的、食品衛生学的および微生物学的研究
麹菌の健康効果と機能性食品への応用
麹菌は健康効果を持つさまざまな成分を生成するため、機能性食品への応用が注目されています。
例えば、麹菌が生成する酵素には消化を助ける作用があり、腸内環境を整える効果があります。さらに麹菌発酵食品には、ビタミンB群やアミノ酸が豊富に含まれており、エネルギー代謝や筋肉の成長をサポートします。
上記のような健康効果が現在注目されており、実際に麹菌を利用したサプリメントやプロバイオティクス飲料などが市場に登場してきました。
麹菌の健康効果を活かした事業展開は、今後ますます注目されるといえます。
麹菌の伝統的な製法と現代の技術の融合
現在の麹菌の製造では、伝統的な製法と現代の技術が融合しています。
麹菌の伝統的な製法において、職人の長年の経験と勘は欠かせません。特に温度や湿度の管理には工夫がこらされており、木製の麹室(こうじむろ)での自然の気候条件を利用しながら発酵を進める方法は、日本各地で古くから行われてきました。
一方、現代の技術を取り入れることで、麹菌製造の効率と品質はさらに向上しています。自動温度調節装置や湿度管理システムなどの導入によって、発酵環境の精密なコントロールが可能となり、安定した品質の麹を大量生産できるようになりました。また微生物の研究が進んだことにより、最適な菌株の選定や、酵素活性を高める工夫も行われています。
麹菌製造と地域活性化の関係
麹菌製造は、地域の伝統産業として地域活性化にも貢献しています。日本各地にはそれぞれに地域の特産品があり、独自の麹菌を用いた発酵食品はその一つです。
そして、秋田県の「酒蔵巡り」や愛知県の「味噌蔵見学」などは観光資源としても活用されており、地域の経済活性化や雇用創出に繋がっています。
また、地元の農産物を原料とした麹菌製造が進められることで、地産地消の推進にも寄与しています。地域の農産物と連携した麹菌製造は、持続可能な地域経済政策の一例といえます。
麹菌 製造のポイント
ここからは、麹菌製造のポイントについて3つ解説します。
温度管理と乾燥技術
麹菌製造において、温度管理と乾燥技術は品質を左右する重要なポイントです。
発酵中の温度が高すぎると麹菌が死滅し、低すぎると発酵が進まないため、適切な温度範囲を維持することが必要です。
一般的な麹菌の最適温度は30度から35度ですが、具体的な温度は麹菌の種類や目的により異なります。また麹菌が増殖する温度と麹菌が産生した酵素が働く温度には違いがあるため、注意が必要です。
発酵が完了した後、麹を乾燥させる工程も重要です。乾燥が不十分だとカビが発生し、品質が劣化するため、適切な乾燥技術が求められます。乾燥中の麹の状態を定期的に確認し、必要に応じて調整を行うことで、品質の高い麹を製造できます。
参考:麹菌は優秀な酵素メーカー!麹菌の種類から麹の作り方、温度管理まで|かわしま屋
品質管理と安全対策
麹菌製造にあたって、品質管理と安全対策も欠かせない要素です。
品質管理は麹菌の培養から最終製品までの各工程で行われ、一定の品質基準を満たす必要があります。具体的には種麹の選定、発酵中の温度・湿度管理、乾燥工程などの合間にサンプルを取り、品質検査を行うことで問題に即時対応できます。
また、安全対策として衛生管理は必須です。製造環境を清潔に保ち、他の細菌やカビの混入を防ぎましょう。
さらに、HACCP(ハサップ)などの食品安全管理システムを導入することで、リスクを低減し、消費者に安心して提供できる製品の製造が可能となります。
継続的なモニタリングと調整
麹菌製造では、継続的なモニタリングとそれに伴う調整が品質を維持するために不可欠です。
発酵プロセス中の温度、湿度、pH値などの環境条件を定期的にチェックし、必要に応じて調整を行います。例えば温度が上昇しすぎると麹菌が死滅するリスクがあるため、温度センサーや自動制御システムを使用した適切な温度管理が必須です。湿度も発酵が進むにつれて変動するため、加湿器や除湿器を使用して調整します。
また発酵が進むと酸性度が変化するため、pH値の適切な範囲を維持することも重要です。
麹菌 製造の注意点
この章では麹菌製造の注意点のうち、3つをピックアップして解説します。
衛生管理とコンタミネーションの防止
麹菌製造において、衛生管理とコンタミネーションの防止は極めて重要です。
麹菌は非常にデリケートであり、他の細菌やカビとの競争に弱い微生物です。そのため、製造環境を清潔に保ち、異物や有害微生物の混入を防ぐことが求められます。具体的には、作業場の定期的な清掃や消毒、作業者の衛生管理が必須です。作業者は、手洗いや消毒を徹底し、清潔な作業着を着用しましょう。
また、製造機器や器具の洗浄も重要です。使用後は速やかに洗浄し、乾燥させることで、細菌の繁殖を防ぎます。
さらに原料の受け入れ時に異物や汚染のチェックを行い、品質が保証されたものだけを使用しましょう。対策を徹底し、コンタミネーションのリスクを最小限に抑えてください。
参考:醤油の異臭とその防止策
温度管理の失敗による影響
温度管理に失敗すると発酵が不均一になり、最終製品の品質に大きな影響を及ぼします。
発酵過程では、麹菌が最適に活動する温度範囲の維持が必要です。
例えば、発酵中の温度が40度を超えると麹菌の酵素産生が低下し、発酵が遅れることがあります。一方、25度以下でも発酵が遅れ、製造スケジュールに支障をきたします。
また製品の風味や品質にも影響することから、消費者の評価を下げる原因となります。発酵室の温度センサーや自動温度調節装置を使用し、常に適切な温度を保ちましょう。また、発酵中の温度変動を最小限に抑えるため、発酵容器の設計や配置にも工夫が必要です。
参考:麹菌は優秀な酵素メーカー!麹菌の種類から麹の作り方、温度管理まで|かわしま屋
原料選定の重要性
麹菌製造において適切な原料を選定すれば、麹菌の発酵プロセスが円滑に進行し、安定した品質の麹の生産が可能となります。例えば米の種類や品質、成分含有量は発酵に大きな影響を与えます。高品質な米の使用によって麹菌が持つ酵素の活性が最大限に引き出され、風味豊かな発酵食品が生まれるでしょう。
また、原料の選定は健康効果にも影響を及ぼします。特定の栄養素や機能性成分を豊富に含む原料が選定できれば、機能性食品としての価値も向上します。
さらに、無農薬や有機栽培の原料を選ぶことで環境保護への貢献も可能です。
原料選定は品質管理の基盤であり、最終製品の競争力を高めるためにも不可欠な要素です。
麹菌の液体培養
これまでは麹菌の伝統的な固体培養法について述べてきましたが、最後に液体培養法について少しだけ解説します。
序文で述べた通り、液体培養法にはデメリットもあるものの、麹菌の固体培養で大きなリスクとなる、『他の微生物のコンタミネーション』が殆どなくなるのが最大の魅力です。
また麹菌そのものを純粋に培養できるためこれまで知られていなかった麹菌の様々な機能性を研究しやすく、近年では動物肉の代替タンパク源として麹菌を用いた肉様製品の研究開発も行われています。
ただし固体培養に比べ、麹菌の液体培養はノウハウや工場設備の関係上、実現できる施設の数は限られています。麹菌の液体培養について知りた方は、これらを持つ製造工場に相談すると良いでしょう。
参考:
毎日新聞 2022年4月6日公開動画『麴菌が世界を救う?「菌肉」プロジェクト始動』筑波大学 生命環境学群生命地球科学研究群生命環境系 糸状菌相互応答学研究室ホームページ
まとめ:麹菌製造の進化により切り拓かれる様々な麹菌活用の未来
麹菌製造の進化は、日本の食文化と健康に新たな可能性をもたらしています。
麹菌は、日本において古くから親しまれてきました。そして現在では伝統的な製法と現代技術の融合により品質と安全性が向上し、多様な機能性食品の開発も進んでいます。
地域活性化や環境保護への貢献も期待されていることから、健康的で持続可能な未来に向けて、今後も麹菌の活用範囲は広がるでしょう。
一覧へ戻る