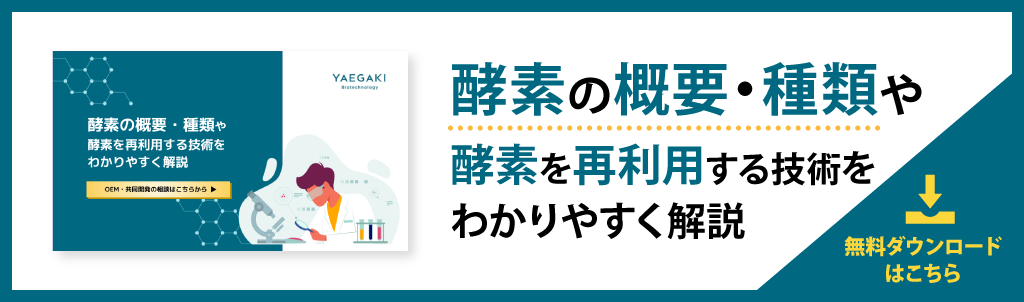発酵食品に使われる微生物効果を高める食品の組み合わせ方も解説
昨今は健康増進を目指すうえで発酵食品の効果が注目されており、積極的に食生活に取り入れる人が増えています。
一方で、発酵食品にはさまざまな微生物が使われているものの、具体的にどのようなものかわからない方もいるでしょう。
そこで本記事では発酵食品に使われる微生物について、詳しく解説します。また、発酵食品の効果をより高める組み合わせ方についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
※研究開発コラムは微生物を活用した研究開発において参考になるトピックを集めたもので、全てのテーマについて当社が研究開発を実施しているわけではございません。
目次
発酵食品の基本
発酵食品とは、微生物の力を活用して食材を発酵させたものです。
発酵食品には醤油・味噌・キムチ・納豆・ヨーグルトなど、さまざまなものが該当します。
発酵食品の最大の特徴は、微生物の力で食材の栄養素やうまみを強めている点です。
さらに保存性を高めることにより、長期保存を可能としています。
なお、発酵と腐敗はよく似たものですが、前者が人間にとって有益な現象であるのに対し、後者は人間にとって有害な現象として扱われます。
つまり、発酵は食材を「人間にとってより良い食品」に変える現象といえます。
発酵食品に使われる代表的な微生物3種
本章では、発酵食品に役立つ微生物の特徴について解説します。
真菌
真菌には人間にとって有害なイメージがありますが、発酵食品に使われるものは無害です。
タンパク質をアミノ酸に変えたり、でんぷんを糖に変えたりするなど、食材のうまみを引き上げる効果があります。
発酵食品に使われる代表的な真菌には、麴菌・白カビ・青カビなどがあります。
なかでも麹菌は日本酒やみりんなどに使用されるなど、日本人にとって身近な微生物です。
また、かつお節・味噌・チーズなどにも真菌が使われています。
なお、菌株の種類や培養条件によっては毒素等を生成する場合もあり、注意が必要です。
細菌
細菌は、発酵食品に用いられる代表的な微生物の一種です。
納豆に使われる納豆菌・漬物やヨーグルトに使われる乳酸菌・食用酢に使われる酢酸菌などが有名です。
細菌を用いた発酵食品は、肌の調子を良くしたり、腸内環境を整えたりするなど、健康増進に役立つ効果が期待できるものが多くあります。特にヨーグルトや納豆は健康食の定番です。
なお、細菌は種類によって発酵のプロセスや効果が異なります。
なかには発酵食品の製造だけでなく、産業排水の浄化や抗生物質の精製などに使われるケースもあります。
酵母
酵母は、アルコール類・パン・醤油などに利用される微生物です。糖を分解することでアルコールと二酸化炭素を精製する作用があり、日本ではカビや細菌と並んで、古来から活用されています。
同じ酵母でも種類によって活用方法が違っており、パン用のイーストやビール用のビール酵母など、特定の食品に特化したものもあります。
また栄養素が高いものや、独特な風味を生み出すものなど、種類によって個性が異なる点も特徴です。
酵母の使用範囲は幅広く、サプリメントや化粧品にも使われます。さらに企業によっては、土壌改良や界面活性剤の製造に活用するケースもあります。
発酵食品に期待できる5つの効果
発酵食品は、健康面でさまざまな効果が期待できる点が魅力です。本章では発酵食品が健康に及ぼす効果を5つ解説します。
栄養の吸収を助ける
発酵食品は発酵の過程で酵母や細菌が栄養素を分解し、体内に吸収しやすい状態にします。
そのため、効率的な栄養の吸収が可能になるうえ、体への負担もかかりません。
例えば調味料として人気がある塩麴は、タンパク質分解酵素も生成します。このため、
肉にもみ込むことでタンパク質を分解し、吸収しやすくする効果があります。
他に食感を柔らかくしたり、うま味を向上させたりする効果もあり、料理に役立つ効果が満載です。
また、微生物の効果によって、食材の栄養価が高められている点も重要です。例えば、納豆は大豆の状態よりもビタミンB2や葉酸などの栄養素が豊富で、イソフラボンも吸収されやすくなります。
加えて、ナットウキナーゼやビタミンK2のような栄養分が発生することから、健康効果を高める力は非常に強いといえます。
参考:
みんなの発酵BLEND|発酵食品って何がいいの?
山﨑勝利| これから見直すべき「発酵食品」の栄養価
腸内環境を整える
昨今は腸内環境を整える腸活が流行しており、発酵食品が注目されています。
発酵食品に含まれる乳酸菌や納豆菌は、悪玉菌の増殖を押さえ、腸内環境を適正化する効果が期待できる微生物です。
ヨーグルトやキムチなど、善玉菌を含む発酵食品を積極的に摂取すれば、腸内環境を整えられます。
腸内環境を整えることは、健康や美容につながる取り組みです。
もし悪玉菌が増殖するようになれば、便秘や下痢になるだけでなく、免疫機能の低下などを招きます。
参考:みんなの発酵BLEND|腸活とは? 発酵食品との関係性
免疫機能を向上させる
発酵食品が免疫機能を向上させる効果は、腸内環境を整える効果と密接に関連しています。
人間の体にある免疫細胞や抗体の約6割は腸内に集まっており、腸内環境が乱れれば免疫機能に悪影響を及ぼします。
腸内環境の乱れによって免疫機能が低下すれば感染症にかかりやすくなるだけでなく、糖尿病・がん・うつ病などに繋がるリスクが高まります。
発酵食品で善玉菌を増やし、腸内環境を整えることは免疫機能の向上につながる取り組みです。
日常的に発酵食品を食べて善玉菌を増やせば、さまざまな病気を予防できる可能性が高まります。
参考:
厚生労働省e-ヘルスネット|腸内細菌と健康
日本検診財団|腸のはなし
生活習慣病を予防する
発酵食品のなかでも、味噌や醤油のような大豆を使ったものは高血圧や高コレステロールを予防する効果があり、動脈硬化の予防が期待できます。
さらに納豆から摂取できるナットウキナーゼは酵素を活性化させ、血栓の分解を促進してくれます。
体の酸化を防ぐ
人間の体内で活性酸素が発生すると、老化が進行しやすくなります。
そのため、老化を抑制するにはポリフェノールのような抗酸化物質の摂取が欠かせません。
味噌や赤ワインなど、発酵食品には抗酸化物質を多く含むものがあります。
さらに腸内環境を整えたり、アミノ酸などを摂取できたりするため、美容への効果も期待できます。
発酵食品を組み合わせるメリットと注意点
発酵食品の効果を効率的に得るなら、食品同士の組み合わせがおすすめです。
しかし、発酵食品を組み合わせる際は、メリットだけでなく注意点も把握しなければなりません。
発酵食品を組み合わせるメリット
発酵食品を組み合わせれば、複数の微生物や栄養素を同時に摂取できます。
微生物は種類によって効果が異なるものですが、発酵食品を組み合わせれば複数の効果を同時に得られるため、効率的に健康増進を図れます。
また、納豆菌のように乳酸菌を活発化させる物質を作れる微生物もいるため、相乗的に効果を高められる点もメリットです。
何より、納豆と醤油のように発酵食品には味の相性が良いものが多くあります。
好みの組み合わせを見つければ、食習慣に発酵食品を取り入れやすくなるでしょう。
発酵食品を組み合わせる際の注意点
発酵食品を組み合わせる際は、食べ過ぎに注意しましょう。
元来、発酵食品は保存用で開発されたものが多く、塩分濃度は高めです。いくら味が良いとはいえ、あまりに多く食べると塩分の過剰摂取や高血圧を招く恐れがあります。
また、ヨーグルトや甘酒のような、塩分が少ないものにも注意が必要です。
これらの発酵食品には糖質が含まれており、過剰に摂取すれば肥満のリスクを高めます。
おすすめな発酵食品の組み合わせ3選
本章では、発酵食品のおすすめな組み合わせを紹介します。一般の家庭で実践しやすい組み合わせなので、ぜひ事業展開の参考にしてください。
納豆とキムチ
納豆とキムチは、味はさることながら、栄養面でも高い相乗効果を発揮する組み合わせです。
納豆に含まれる納豆菌はデンプンからオリゴ糖を生み出す働きがありますが、オリゴ糖は乳酸菌を活発化させるうえで欠かせない物質です。
そのため、乳酸菌を含むキムチを納豆と組み合わせれば、それぞれの効果をさらに高められます。
なお、納豆やキムチと一緒にご飯を食べればオリゴ糖の源を同時に摂取できるため、さらなる効果の向上が期待できます。
ヨーグルトと甘酒
ヨーグルトと甘酒も、実は相性が良い組み合わせです。
ヨーグルトには乳成分を発酵できる乳酸菌、甘酒には米成分を発酵できる乳酸菌が含まれているため、両者を同時に摂取すれば、2種類の乳酸菌を体内に取り入れられます。
さらに甘酒には麹菌が含まれており、乳酸菌が活発化するオリゴ糖も生成されます。
もしヨーグルトに甘さを足したいときには、甘酒がピッタリでしょう。
ただし過剰摂取は肥満につながるため、注意喚起する必要があります。
チーズと味噌
意外な組み合わせですが、チーズと味噌も高い相乗効果を期待できます。
チーズと味噌は、味の相性が良い組み合わせです。チーズを味噌に漬け込むだけで、おつまみにもなる味噌漬けを作れます。
また味噌はアミノ酸やビタミンB1などを含んでおり、チーズはたんぱく質やミネラルなどが豊富です。
それぞれを組み合わせれば、より多くの栄養を摂取できます。
まとめ:発酵食品を組み合わせれば微生物の効果が上がる
発酵食品はカビ・細菌・酵母の働きによって、健康に有益なさまざまな効果をもたらします。
さらに、発酵食品同士を組み合わせれば相乗効果により、さらに効果は高まります。
ただし、発酵食品を組み合わせると塩分や糖分などの過剰摂取につながる点には注意しなければなりません。栄養バランスを考え、適切な量を摂取するよう呼びかけてください。
本記事で紹介した組み合わせ以外にも、発酵食品の組み合わせにはさまざまなものがあります。ぜひ自社の関連製品に適したものを探してみてください。
一覧へ戻る