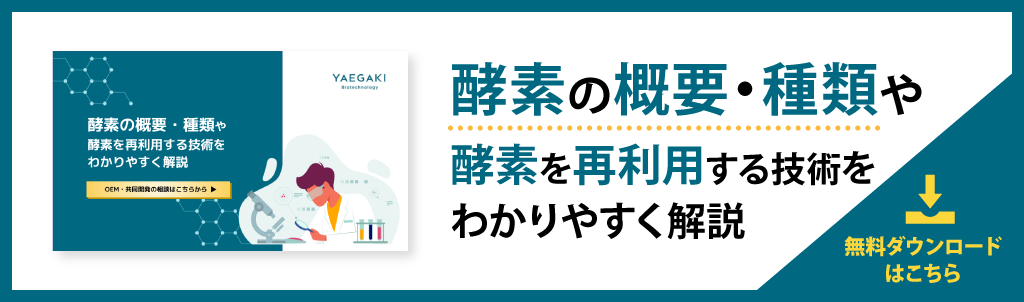乳酸菌の未来|研究の歴史と企業の革新的アプローチ
乳酸菌は、人間の健康促進に寄与する微生物として広く知られています。さらに近年、乳酸菌が腸内フローラのバランスを整え、免疫力を向上させる効果が報告され、研究も盛んになってきました。
本記事では、乳酸菌研究の歴史や最新の動向を紹介し、主要企業の革新的な取り組みやスタートアップ企業の挑戦などについて詳しく解説します。
乳酸菌研究がもたらす未来の可能性と、企業の役割について探っていきましょう。
※研究開発コラムは微生物を活用した研究開発において参考になるトピックを集めたもので、全てのテーマについて当社が研究開発を実施しているわけではございません。
目次
乳酸菌研究の最新動向
乳酸菌研究は、健康促進や医療分野での応用を目指して急速に進展しています。ここからは最新の研究をもとに、乳酸菌の多様な効果や新しい可能性について解説します。
乳酸菌とは何か
乳酸菌は広義には糖を分解して乳酸を生成する微生物の総称であり、自然界に広く分布しています。
狭義にはいくつか定義がありますがその中でも『消費したブドウ糖から50%以上の乳酸を生成するカタラーゼ陰性のグラム陽性細菌』という定義が重要であり、ビフィズス菌は乳酸や酢酸を生成しますが、乳酸の割合が50%以下のため乳酸菌に分類されません。
しかし広義の乳酸菌は上述のように一般的に乳酸を生成する微生物全てを指すため、ビフィズス菌が含まれる事もあります。本稿では狭義の乳酸菌に絞り話を進めます。乳酸菌は食品においては、主に乳製品や発酵食品に多く含まれます。
代表的な乳酸菌には、ラクトバチルス属、ラクトコッカス属、エンテロコッカス属などがあり、それぞれ異なる特徴と健康効果を持っています。
ラクトバチルス属やラクトコッカス属は小腸や大腸近位部内で宿主が摂取した栄養残渣や未消化栄養成分を代謝して乳酸を生成し、腸内環境を酸性に保って有害菌の繁殖を抑えます。また、エンテロコッカス属は主に小腸に多く存在し、免疫系を刺激し、病原菌に対する抵抗力を高めています。
参考:乳酸菌の健康機能|Comprehensive Medicine Vol.17 No.1(2018)
乳酸菌研究が注目される理由
多岐にわたる健康効果と新しい応用の可能性が、乳酸菌研究が注目される主な理由です。
まず、乳酸菌は腸内環境を改善し、食物の消化吸収を助けることで消化器系の健康を保ちます。腸内フローラのバランスを整えることで、便秘や下痢などの消化器系の不調を改善するだけでなく、免疫力の向上にもつながることがわかってきました。
また近年の研究では乳酸菌がアレルギー症状を緩和し、炎症を抑える効果があることも示されています。
さらに、乳酸菌はメンタルヘルスにも影響を及ぼすことが解明されつつあります。腸と脳の関係を示す「腸脳相関」の研究により、乳酸菌がストレスや不安を軽減し、うつ症状を改善する可能性が示唆されました。
参考:
乳酸菌の健康機能|Comprehensive Medicine Vol.17 No.1(2018)
腸内フローラとメンタルヘルス|公益財団法人 ヤクルト・バイオサイエンス研究財団
乳酸菌サプリメントの可能性
乳酸菌の様々な効果の解明を受けて、乳酸菌サプリメント市場は急速に拡大しています。
ここからは乳酸菌サプリメントの効果や開発について、基本的な部分を解説します。
腸内環境を整えるサプリメントの効果
乳酸菌サプリメントの主要な効果は、腸内環境の改善です。腸内には多様な細菌が共存しており、そのバランスが健康に大きな影響を与えます。
乳酸菌は善玉菌として腸内フローラを整え、悪玉菌の増殖を抑えます。その結果、便通の改善・消化吸収の促進・免疫力の向上などの効果に繋がります。
また消化酵素の分泌を助け、栄養素の消化吸収を促すことから、体全体の健康向上が期待できます。さらに乳酸菌は腸内の免疫細胞を活性化し、全身の免疫力を高めるため、感染症の予防やアレルギー症状の軽減に効果的です。
安全性と効果を追求する製品開発
乳酸菌サプリメントの開発に求められるのは、安全性と効果の両立です。そのため、品質管理・科学的根拠・消費者ニーズへの対応などが重視されています。
大前提として、乳酸菌サプリメントは厳しい品質管理のもとで製造されなければいけません。使用する乳酸菌の種類や量を検証し、最適な配合を行うのです。製造過程では、外部からの汚染を防ぐための衛生管理が必要です。
また、乳酸菌の効果を科学的に証明するため、臨床試験を行います。試験によって特定の乳酸菌株がどのような健康効果を持つか明確にすれば、消費者に信頼性の高い情報が提供できます。
乳酸菌の医療への応用
乳酸菌の医療への応用は、腸内環境の改善・免疫力の強化・感染症予防など多岐にわたります。ここからは乳酸菌がどのように医療に応用されているか、代表的なものを解説します。
乳酸菌と健康の関係
腸内細菌は、人間の健康に多大な影響を与えます。腸内には約100兆個もの細菌が存在し、そのバランスが健康状態を左右します。腸内フローラの乱れは、消化器系のトラブルだけでなく、免疫系や神経系にも影響を及ぼすことがわかっています。
そして乳酸菌は、腸内細菌のバランスを整える役割を果たします。善玉菌としての乳酸菌は有害な病原菌の増殖を抑え、腸内環境を健康に保つのに貢献します。これにより、消化吸収の改善や免疫力の向上、さらにはメンタルヘルスの改善にもつながります。
乳酸菌治療の新展開
乳酸菌を利用した治療法は、プロバイオティクス治療として注目されていますが、近年では新たな展開が見られます。
最近の研究により、Leuconostoc mesenteroidesという乳酸菌が肥満を防ぐことが確認されました。この乳酸菌は糖から菌体外多糖(EPS)を大量に生成します。このEPSをマウスに摂取させた実験では、腸内環境が改善され肥満を防ぎました。EPSは食物繊維のようなプレバイオティクス効果を持ち、この乳酸菌は、プロバイオティクス効果とプレバイオティクス効果を併せ持つシンバイオティクス乳酸菌として期待されています。
また、EPSは乳酸菌の代謝産物としてポストバイオティクス成分としても注目されており、肥満や2型糖尿病の予防・治療に役立つ可能性も示唆されています。
参考:乳酸菌が作る菌体外多糖による腸内環境改善と肥満抑制|東京農工大学
乳酸菌を活かした創薬研究とその可能性
現在では、乳酸菌の健康効果を利用した創薬研究も進展しています。特に近年では、腸内フローラを標的とした治療薬開発が試みられています。
腸内フローラは代謝・免疫・感染防御・脳機能などに大きな影響を与えている可能性が示唆されているため、腸内細菌を創薬のターゲットにする動きが出てきました。
腸内フローラのバランスを調整することで、肥満・心疾患・喘息・炎症性腸疾患・精神神経系疾患など、様々な疾患の治療を目指す新しい治療薬の開発が進められています。
実際に、特定の腸内細菌の補充・選択的除去、遺伝子改変プロバイオティクスの開発を通して疾患の治療や予防に生かす試みが既に行われています。
参考:腸内細菌叢の機能と創薬応用の可能性について|ファルマシア Vol. 53 No. 11 2017
主要企業の革新的な取り組み
乳酸菌の研究を行っている企業は、乳酸菌の多様な健康効果を最大限に引き出すための革新的な研究を日々進めています。
ここからは代表的な企業とそのアプローチ方法について、まとめて解説します。
ヤクルト本社
ヤクルト本社は、乳酸菌研究のパイオニアとして長年にわたり革新的な取り組みを続けてきました。1935年に創業者の代田稔博士が、Lactobacillus casei Shirota(商標名乳酸菌シロタ株)を発見し、この菌株の健康効果を基にした乳酸菌飲料「ヤクルト」を開発しました。シロタ株は、腸内の悪玉菌を抑制し、腸内環境を改善する効果があり、多くの研究によってその有効性が裏付けられています。
ヤクルト本社は、乳酸菌の健康効果をさらに深く追求するために、様々な研究を行ってきました。特に、シロタ株が免疫系に与える影響についての研究が進められており、これまでに、感染症の予防、アレルギー症状の軽減、さらにはがん予防に対する可能性が示されています。
カルピス株式会社
カルピス株式会社は乳酸菌研究において先進的な取り組みを行っている企業の一つです。創業以来、乳酸菌の健康効果に注目し、多くの製品を開発してきました。創業者の三島海雲氏がモンゴルで出会った伝統的な発酵乳からヒントを得て開発されたカルピスは、乳酸菌と酵母の働きによって生み出される独特の風味と健康効果が特徴です。
カルピス株式会社は長年培ってきたノウハウを活かし、さまざまな乳酸菌の分離・培養技術を進化させてきました。特に、「カルピス由来乳酸菌」として知られるLactobacillus acidophilus L-92(商標名L-92乳酸菌)は、免疫力の向上やアトピー性皮膚炎の症状改善に効果があるとされ、健康食品やサプリメントに広く活用されています。
参考:Lactobacillus acidophilus L-92株の抗アレルギー作用について
明治ホールディングス
日本における本格的な医科プロバイオティクスの認知が広まったのは、同社が研究開発したLactobachillus gasseri OLL2716(商標名LG21乳酸菌)の研究が始まりと言えます。胃内は強酸の環境にあるため、通常の乳酸菌では定着できないと言われていました。しかしこの菌は胃内の強酸環境下でも生育でき、胃がんの原因として知られる胃ピロリ菌の増殖を抑制する菌として発見され、その後も様々な医学的研究が行われています。
また免疫力を保つ乳酸菌として国内で最も著名なLactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus OLL1073R-1(商標名1073R-1乳酸菌)は高齢者におけるインフルエンザウイルスの感染予防効果があるとして研究され、この菌の作る細胞外多糖(EPS)成分が保健効果を持つ事など特徴的な研究をしており、同社のヨーグルト製品などで用いられています。
その他にも『おなかの健康を保つ』という乳酸菌の従来の機能性だけでなく、全身の健康維持に役立つ独自の様々な乳酸菌株を研究開発しているのが特徴です。
また明治ホールディングスは乳酸菌の機能性を最大限に引き出すため、独自の培養技術や製造プロセスを開発しました。この技術により、乳酸菌製品の健康効果をより効果的に消費者に届けることが可能となりました。製品のラインナップも、ヨーグルトや乳酸菌飲料、サプリメントなど多岐にわたり、様々な消費者のニーズに応えています。
参考:
J Antimicrob Chemother. 2001 May;47(5):709-10.
Br J Nutr. 2010 Oct;104(7):998-1006.
ヨーグルトの製法|明治ヨーグルトライブラリー
タカナシ乳業タカナシ乳業が研究している代表的な乳酸菌は、Lactobacillus rhamnosus GG(商標名乳酸菌LGG)です。この菌は腸内フローラのバランスを整えるだけでなく、感染症の予防やアレルギー症状の緩和に効果があることが確認されています。また、大腸の炎症を改善する効果も示唆されており、近年日本でも増加している潰瘍性大腸炎やクローン病の予防効果が期待されています。
参考:Lactobacillus GG 発酵乳の炎症性腸疾患に対する作用の検討|第16回腸内細菌学会
注目のスタートアップ企業と乳酸菌の未来
近年、様々なスタートアップ企業が乳酸菌研究の新たな可能性を探求し、製品や技術を開発しています。
ここからはスタートアップ企業の取り組みを中心に、乳酸菌関連の研究を紹介します。
株式会社ラウンドリング
株式会社ラウンドリングは近年設立されたスタートアップ企業で、乳酸菌を活用したスキンケアの新しいアプローチとして「ビオメディ」を開発しました。粘質多糖を生成する乳酸菌Lactobacillus bulgaricus TY569の発酵物エキスを用いています。
ビオメディは「健康な肌は美しい」という信念のもと、乳酸菌の持つ力を最大限に活かして皮膚常在菌(スキンフローラ)を整えるために開発された製品です。
ビオメディは、肌と肌状態を大きく左右している皮膚常在菌へのクリーンな環境提供を目指し、スキンシンビオシス、ナチュラル&メディカル、シンプルステップの3つの方針と共に製品をプロモーションしています。
未来のスキンケア市場において、乳酸菌を活用した新しいアプローチを提案し続ける企業として、現在でも成長と発展を続けています。
株式会社LABバイオテック
株式会社LABバイオテックは北海道大学発のバイオベンチャーで、乳酸菌を利用した次世代の食品とサプリメントの開発に注力しているスタートアップ企業です。北海道内の植物や発酵食品からストーリー性のある乳酸菌を分離する事業を行う他、各地域の特産品から乳酸菌を分離し、「ふるさと乳酸菌」という地域振興のための乳酸菌研究開発受託なども行っています。
独自の乳酸菌としてはⅠ型アレルギーの抑制効果があるとする、Pediococcus pentosus sp. KB-1(商標名Clark乳酸菌)の研究開発を行っています。
乳酸菌の研究課題と未来展望
乳酸菌の研究課題と未来展望では、効果のメカニズム解明や応用範囲の拡大が重要なポイントです。ここでは乳酸菌研究の課題と今後について、解説します。
乳酸菌研究の今後の課題
乳酸菌の課題のひとつに、個々の効果のメカニズム解明があります。乳酸菌は多くの効果が実証されているものの、具体的なメカニズムはまだ完全には解明されていません。どのようにして乳酸菌が免疫系を調整するのか、腸内フローラにどのような変化をもたらすのか、さらなる研究が必要です。
また、個別化されたプロバイオティクスの開発も課題としてあげられます。個々の人々の腸内フローラは非常に多様であり、一つの乳酸菌が全ての人に同じ効果をもたらすわけではありません。パーソナライズドプロバイオティクスの開発には、個々の腸内環境に適した乳酸菌の選定と効果の確認が求められます。
参考:有用乳酸菌の単離と腸管付着メカニズムの解明に関する研究|Milk Science Vol.61,No.3 2012
微生物との共存に向けた研究
乳酸菌を含むプロバイオティクスは、腸内の微生物同士の相互作用を理解する上で重要な研究対象です。
腸内には数百種類以上の微生物が存在し、これらがバランスを保ちながら共存しています。乳酸菌が腸内フローラ全体にどのような影響を与えるのか、善玉菌と悪玉菌のバランスをどのように調整するのかを解明する研究が進められています。
一方で、乳酸菌を含む微生物がどのようにして宿主(人間)の健康を支えているのか、その共生関係の解明は、今後のプロバイオティクス研究の最重要なテーマといえるでしょう。
また、異なる環境(例えば、地域や食文化)の中で最適な乳酸菌の選定も重要です。上述のLABバイオテックのような特定の地域や生活習慣に適した乳酸菌の研究は、その地域特有の健康問題への適切なアプローチとなる可能性があります。
企業が描く未来のビジョンと社会貢献
乳酸菌研究において企業の役割はますます重要になっており、多くの企業が研究開発に力を入れて社会貢献を目指しています。
現在では、とくに乳酸菌を活用した製品による、健康寿命の延伸が期待されています。企業は科学的根拠に基づく製品開発を通じて、生活習慣病の予防や高齢者の健康維持に貢献していかなくてはなりません。
また、企業は地域社会との連携を深め、乳酸菌研究を通じて地域の健康増進に貢献しています。例えば、地域特産品と乳酸菌を組み合わせた製品開発や、地元の学校や医療機関との共同研究が進められています。実際に今回紹介させていただいたスタートアップ企業の株式会社LABバイオテックでも、「ふるさと乳酸菌づくり」が提案されています。
乳酸菌研究がもたらす未来の可能性
乳酸菌研究の進展は、未来の健康社会に多くの可能性をもたらすでしょう。
医療利用においては、腸内フローラを利用した癌治療や、上述の明治HDのLG21乳酸菌のような抗生物質に代わる新しい感染症治療法などが考えられます。
また、腸内フローラの研究が進めば、個々の腸内フローラに基づくパーソナライズドニュートリションの提供が可能となります。
パーソナライズドニュートリションとは、科学にもとづく多様な評価(ビッグデータ)を活用し、一人ひとりに的を絞った助言や製品を提供するシステムです。研究が進めば、やがて一人ひとりに最適な乳酸菌サプリメントや食品を提供できる未来がくるでしょう。
まとめ:乳酸菌研究の可能性と企業の役割
乳酸菌研究はまだ多くの課題を抱えていますが、その進展により健康社会の実現に大きく寄与してきました。
企業は研究開発を通じて社会貢献を果たし、未来の健康問題に対する解決策を提供する役割を担っています。
乳酸菌の新しい可能性が次々と明らかになるなか、企業研究の重要性はさらに高まるでしょう。今後も乳酸菌研究の進展とそれを支える企業の取り組みに注目し、健康で持続可能な未来を目指してください。
一覧へ戻る