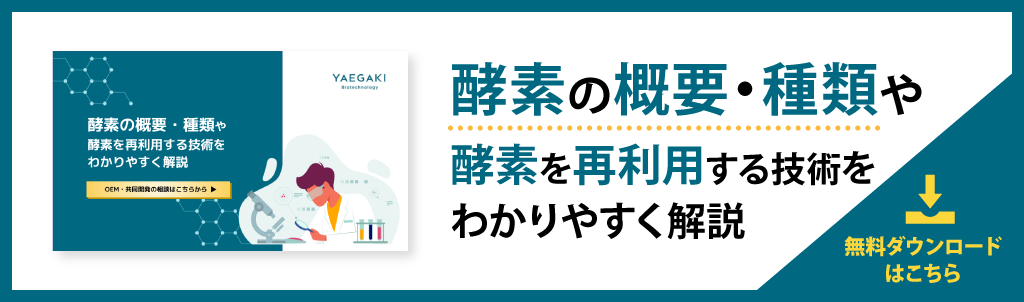食品だけではない多様な酵母菌の活用事例
パンやワインをつくるのに欠かせない酵母菌ですが、その活用範囲は食品製造のみにとどまりません。
本記事では、酵母菌の生物学的特性から産業応用、社会貢献までを詳しく解説します。最新の研究成果や事例も紹介するので、幅広い領域で活躍する酵母菌の今後について考察してみてください。
※研究開発コラムは微生物を活用した研究開発において参考になるトピックを集めたもので、全てのテーマについて当社が研究開発を実施しているわけではございません。
酵母菌とは
ここではまず、酵母菌の特徴について解説します。
酵母菌の生物学的特性
酵母菌は真核生物に分類され、細胞内に細胞核を含んでいます。この特性により、酵母菌は他の真核生物と同様に細胞内の機能を調節し、遺伝情報を次世代に受け継ぎます。
また、酵母菌は単細胞生物であることから、単独の細胞で代謝や繁殖など完全な生命活動が可能です。酵母菌は好気性・嫌気性両方の代謝経路があり、さまざまな環境条件下で生存できます。
さらに、酵母菌は糖分を利用してアルコールや二酸化炭素を生成する発酵能力を持ちます。この特性により、酵母菌は食品の発酵やアルコール飲料の製造などに古くから利用されてきました。
酵母菌の利用法と産業応用
酵母菌は、その多様な特性を活かしてさまざまな産業分野で利用されています。
例えば食品産業においては、酵母菌は食品の発酵プロセスに広く使用されます。特にパンやビール、ワイン、チーズ、味噌・醤油などの製造では重要な役割を果たしてきました。酵母菌が食品中の糖分を発酵させることでアルコールや二酸化炭素が生成され、食品に独特の味わいや風味が生まれるのです。
医薬品産業においては、酵母菌は遺伝子組み換え技術を活用して、医薬品製造に利用されます。インスリンやワクチンの生産では、酵母菌が多く利用されてきました。
バイオ燃料産業では、酵母菌はバイオ燃料であるバイオエタノールの製造に利用されています。穀物やサトウキビなどの原料から糖分を取り出し、酵母菌を使って発酵させることでエタノールを生成するのです。
酵母菌の生態系における役割
それでは次に、酵母菌はもともと生態系の中でどのような役割を担っているのかをみていきます。
土壌における酵母菌の植物生育促進
酵母菌は有機物を分解し、土壌中の栄養素を植物が取り込みやすい形に変換します。特に酵母菌はアミノ酸やビタミンなどの栄養素を生産し、これらが植物の成長に必要な栄養源となります。
酵母菌には、植物の根の発達を促進する効果もあります。酵母菌の細胞壁に含まれる酵素が、土壌中で植物が根を成長させる手助けをします。根がしっかりと成長することで、植物はより多くの栄養素を吸収し、強力な根系を形成します。
また、酵母菌の特性としてあげられるのは病原菌の増殖抑制の効果です。自然界においては、特に土壌中の病原菌や害虫に対して制御作用を発揮し、植物の病気や害虫被害を軽減します。
微生物としての酵母菌が果たす役割
酵母は微生物として、自然界が循環するための一端を担っています。
その最も重要な役割のひとつが、分解です。酵母菌は有機物を分解する能力を持ち、腐敗した植物の残骸や動物の糞便などの有機物を分解して土壌を肥沃にします。そして、その土には新たな植物が生育し、自然が循環します。
また、酵母菌は生態系の一部として、他の微生物や植物との相互作用によって生態系のバランスを維持しています。例えば土壌中の酵母は、他の微生物相と相互にバランスを調整することで、広く生態系全体を安定させてきました。
酵母菌の産業応用事例
これまでに紹介してきた酵母菌の特性を利用して、様々な産業が展開されています。ここからは、酵母菌の産業応用事例を3つご紹介します。
ビールやワインなどの醸造業界での活躍
酵母菌は、ビールやワインなどの醸造業界で非常に重要な役割を果たしています。
酵母菌が麦芽や果物の糖分を代謝することで、アルコールや二酸化炭素が生成されます。この発酵過程により、ビールやワインなどのアルコール含有の炭酸飲料やアルコール飲料が生産されます。
また酵母菌の種類や発酵条件によって、アルコール飲料の味や香りが異なります。酵母菌が生成する二次代謝産物が、最終製品の風味や香りに大きく影響を与えるためです。
醸造家は適切な酵母菌を選択し、目的とする味や香りを引き出すための条件を調整します。特定の酵母株を特定の条件下で発酵させ、製品の品質や味の一貫性を維持することで、地域特産のワインや地ビールをつくることが可能です。
参考:日本ビール株式会社|ビールの味わいは酵母で決まる!【ビール酵母の話】
食品関連業界での酵母エキスの活用
食品関連業界では、酵母エキスがさまざまな目的で活用されています。
酵母エキスは、食品の風味や旨みを増すための調味料として広く使用されています。特に、スープやソース、調味料などの加工食品において、酵母エキスは味のベースとして利用されます。
また、酵母エキスはビタミンやミネラル、アミノ酸などの栄養素を豊富に含んでいます。そのため、栄養価の向上を目的として、酵母エキスが食品に添加されることもあります。
さらに、酵母エキスには抗菌作用や酸化防止作用もあるとされています。そのため保存性を向上させる目的で、化粧品や食品に酵母エキスが添加されることも少なくありません。近年ではプラントベースフード(PBF)などで肉や魚の風味を製品に与える目的で、それらの風味を持つ酵母エキスの開発なども行われています。
参考:
食品分野で広く活用される酵母菌
酵母エキスの活用法(シェアシマinfo記事より)
酵母菌の働きがもたらす製造効率向上
酵母菌は、取り扱いの容易さや情報の多さから工業分野で幅広く用いられ、工業的な製造プロセスに組み込まれることが多い微生物です。
酵母菌は工業プロセスにおいても主に発酵を主導し、糖分をアルコールと二酸化炭素に分解します。目的とする生成物に合致した適切な酵母菌株の選択や最適な発酵条件の検討によって発酵プロセスを効率化し、より多くの製品が生産できます。
また、酵母菌の製造プロセス導入によるエネルギー消費の削減も見逃せません。酵母菌などの微生物による発酵プロセスは従来の化学的なプロセスと異なり常温・常圧で進行するためです。適切な酵母菌株の選択をすれば温度や圧力の制御が容易になり、さらなるエネルギー削減ができます。
参考:バイオエタノール生産における酵母の培養及びエタノール発酵プロセスシミュレーションの検討
酵母菌の研究成果を活かした事例
酵母菌の研究成果を生かした事例は多岐にわたりますが、ここではその中でも注目されている3つの事例を解説します。
界面活性剤の分野での酵母菌の利用
産業技術総合研究所、アライドカーボンソリューションズ株式会社、琉球大学は共同で、「バイオサーファクタント」と呼ばれる高機能な界面活性剤を開発しました。
バイオサーファクタントとは、酵母菌や納豆菌などの微生物が作り出す天然脂質で、その多くは界面活性剤としての機能を持ちます。バイオサーファクタントは合成界面活性剤に比べ、極めて低濃度で効果を発揮できることが特徴です。
また、合成界面活性剤よりも生分解性に優れ、環境への負荷が少ない特性を持っています。バイオサーファクタントは洗浄剤や乳化剤などの製品に利用されるほか、石油汚染の浄化や医薬品製造など幅広い分野で応用されています。
このような高機能界面活性剤の開発により、再生可能資源を活用した低炭素社会への貢献が期待されます。
参考:産業技術総合研究所|酵母を利用して非可食バイオマスから高機能界面活性剤を量産
酵母菌が供給するビタミンやミネラルの重要性
酵母菌は発酵により多様な栄養素を供給しますが、酵母菌体自体にもタンパク質をはじめビタミン・ミネラル・食物繊維など様々な栄養素が含まれています。これらの栄養素は人体の代謝プロセスには不可欠であり、健康維持に重要です。
これら酵母菌体の活用事例としては、酵母菌由来の栄養補助食品があげられます。これらの製品は、ビタミンやミネラルの補給だけでなく、消化器系の健康や免疫機能のサポートにも役立ちます。その他にも、酵母菌を利用したビタミンやミネラルを豊富に含む発酵食品などもあります。
商品の例としては、アサヒグループ食品のエビオスやちぐさ物産のビール酵母などです。
食品業界における酵母菌の品質向上事例
食品業界における酵母菌の品質向上の手段として、酵母菌株の選抜や改良があげられます。食品製造において特定の酵母菌株を使用すれば、製品の品質や味、香りを向上させることができます。また特定の酵母菌株のみを使用すれば、より効率的で一貫した製品の製造が可能です。
酵母菌株の選定は、発酵力・耐糖力・耐久力・凝集性・色・乾燥酵母の品質など、様々な項目について行われてきました。例えば、パンに適した酵母とビールに適した酵母の間には、凝集・分散性の違いがあります。
パン酵母に求められるのは分散性で、パンの原材料中で全体的に分散することで細かいスダチのパンができます。一方でビール酵母に求められるのは凝集性です。ある程度発酵が進んだところで酵母が凝集し沈殿した方が、透明度の高いビールの実現につながります。
酵母菌の活用による社会貢献事例
ここでは、酵母菌に関係の深い社会貢献の事例について2つ解説します。
清酒酵母を用いた機能性表示食品の開発例
ライオン株式会社の研究においては、特定の酵母菌に睡眠の質を向上させる機能があることが報告されています。
現代社会の多忙な状況下であっても、現代人は健康を維持し、日中の活動性を高めることが求められます。そのため、深い眠りの割合を増やし睡眠の質を向上させる工夫をする必要性が出てきました。
ライオン株式会社で睡眠の質の向上を目指した食品素材を探索したところ、「清酒酵母」が睡眠の質を向上させることを発見しました。清酒酵母は清酒の製造や、酒粕を利用した食品として古くから食されてきたものです。
この清酒酵母は腸内分泌細胞に作用して脳からセロトニンの分泌を促し、睡眠の質を改善させることが分かっています。
こうした経緯を経て、機能性表示食品「グッスミン 酵母のちから」が発売されています。
参考:清酒酵母による睡眠の質改善作用と機能性表示食品への応用
酵母菌を活用したバイオ燃料事業の推進
酵母菌は、持続可能なエネルギー源の開発にも貢献しています。
近年、化石燃料による環境問題を解決するための代替エネルギーとして、バイオエタノールなどの代替燃料が開発されています。
バイオエタノール生産時に利用するエタノール発酵をする微生物には、酵母や特定の細菌類などが知られています。しかし細菌類はエタノールの耐性が低くウイルス等にも弱いことから、稼働しているプラントのほとんどは酵母を利用しているのが現状です。
バイオエタノール生産の最大の課題はコストであり、生産コストを下げるため高効率にエタノールを生産できる酵母菌の選択と効率のよい発酵プロセスの開発が実施されています。
開発の過程では、酵母菌の突然変異株の選定や高温や酸性条件下でのストレス耐性の確認、遺伝子改変による機能強化など、様々な試みがなされています。
参考:バイオエタノール生産用ストレス耐性酵母の開発と特性評価
まとめ:酵母菌の多彩な可能性に今後も注目しよう
古くから人間と関わりの深い酵母ですが、現在では食品や飲料の製造からバイオ燃料の生産まで、様々な分野で重要な役割を果たしています。近年、酵母菌の研究やバイオテクノロジーの進歩により、持続可能な社会の構築に向けての新たな可能性も開けつつあります。
私たちの生活をより豊かにしてくれる酵母菌の多彩な可能性に、今後も注目が集まるといえるでしょう。
一覧へ戻る