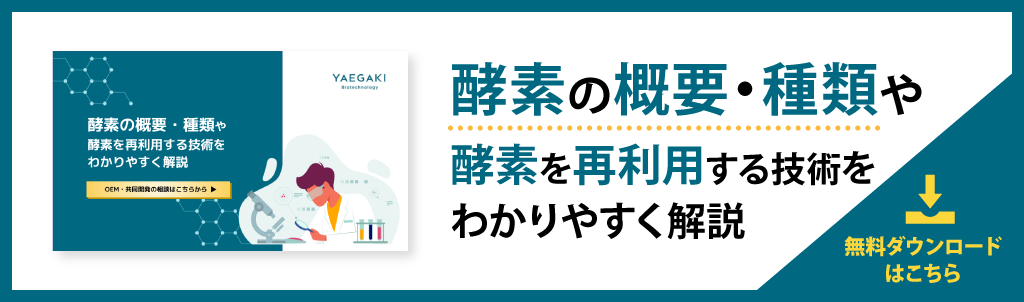天然色素の製造を徹底解説 食品添加物の指定に必要な書類や流れとは
「天然色素の製造について知りたい」「天然色素を製造する際の注意点は何か」と悩む方は多いでしょう。
天然色素は食品添加物に分類されるため、関連する法律などを遵守して製造する必要があります。
そこで本記事では、天然色素の基礎知識や、製造基準、注意点などについて解説します。効率的な事業着手には、ポイントを押さえることが大切です。
食品添加物の指定申請に関する情報も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
※研究開発コラムは微生物を活用した研究開発において参考になるトピックを集めたもので、全てのテーマについて当社が研究開発を実施しているわけではございません。
目次
天然色素の基礎知識
この章では、天然色素の基礎知識について解説します。
天然色素は食品添加物である
天然色素とはいわゆる天然着色料のことであり、食品衛生法上は「食品添加物」として扱われます。
日本で使用できる添加物の中に天然着色料というカテゴリーは存在しませんが、既存添加物と一般飲食物添加物の総称として「いわゆる天然着色料」という名称が使用されています。下記に食品添加物の概要をまとめました。
| 種類 | 概要 | 例 |
| 指定添加物 | ・安全性を評価し、厚生労働大臣が指定したもの・466品目 | ・ソルビン酸・β-カロテンなど |
| 既存添加物 | ・いわゆる天然着色料・長年使用された食経験があるもの・例外的に大臣の指定を受けることなく使用・販売などが可能・357品目 | ・クチナシ色素・コチニール色素など |
| 天然香料基原物質(天然香料) | ・動植物由来の天然の物質で、食品の香り付けに利用するもの・約600品目 | ・バニラ香料・カニ香料など |
| 一般飲食物添加物 | ・いわゆる天然着色料・飲食物の内、添加物として利用されるもの・約100品目 | ・寒天・シソ色素など |
新たに利用される食品添加物は全て、安全性を評価した後、厚生労働大臣の指定を受け「指定添加物」に追加されます。
天然色素の規格
添加物のなかには成分規格や保存基準が定められているものもあり、求められる規格に適合しなければなりません。具体例として、第10版食品添加物公定書に記載されている、アカキャベツ色素の規格の概要を記載します。
【アカキャベツ色素】
| 定義 | キャベツ(Brassica oleracea var. capitata L.)の葉から抽出して得られたシアニジンアシルグリコシドを主成分とするものである。デキストリン又は乳糖を含むことがある。 |
| 色価 | 色価(E10%1cm )は50以上で、その表示量の90~110%を含む |
| 性状 | 暗赤色の粉末、ペーストまたは液体で、わずかに特異なにおいがある。 |
| 確認試験 | 本品の表示量から、色価50に換算して0.1gに相当する量を量り、クエン酸緩衝液 (pH3.0)100mLに溶かした液は、赤~暗紫赤色を呈する1.の溶液に水酸化ナトリウム溶液(1→25)を加えてアルカリ性にするとき、暗緑~薄い黄緑色に変わるクエン酸緩衝液(pH3.0)に溶かした液は、波長520〜540nmに極大吸収部がある。 |
| 純度試験 | 鉛 Pbとして2 µg/g以下(2.0 g、第1法、比較液鉛標準液4.0mL、フレーム方式)ヒ素 Asとして3 µg/g以下(0.50 g、第3法、標準色ヒ素標準液3.0mL、装置B) |
| 色価測定 | 色価測定法により次の操作条件で試験を行う。・測定溶媒 クエン酸緩衝液(pH3.0)・測定波長 波長520~540nmの極大吸収部 |
食品添加物の製造などの際は、定められた規格の確認が重要です。
参考:厚生労働省|第10版食品添加物公定書 D 成分規格・保存基準各条
代表的な天然色素を紹介
この章では、代表的な天然色素について紹介します。
アカキャベツ色素
アカキャベツ色素の概要は次のとおりです。
| 定義 | ・キャベツ (Brassica oleracea var. capitata L.) の葉から抽出して得られたシアニジンアシルグルコシドを主成分とする・デキストリン又は乳糖を含むことがある |
| 分類 | 一般飲食物添加物/食品添加物公定書 |
| 特徴 | ・比較的耐熱、耐光性に優れる・水やアルコールに溶ける・油脂には不溶・pHの影響を受けて色調が変化する・アブラナ科植物の独特の臭いがある |
| 色調 | 赤~赤紫色 |
| 食品への表示例 | アカキャベツ色素、ムラサキキャベツ色素、野菜色素、アントシアニン色素など |
| 用途 | ・ダイコンの桜漬けや柴漬けなどの漬物・あんこ(餡)やチョコレートなどの菓子類・乳酸菌飲料などの飲料 |
アントシアニン系色素の中で最も使用される天然色素です。
イカスミ色素
イカスミ色素の概要は次のとおりです。
| 定義 | ・モンゴウイカ(Sepia officinalis Linnaeus)等の墨袋の内容物を水洗いしたものより、弱酸性含水エタノール及び含水エタノールで洗浄し、乾燥して得られたユーメラニンを主成分とするもの |
| 分類 | 一般飲食物添加物/既存添加物自主規格 |
| 特徴 | ・水、油脂に不溶・粉体混合や練り込みで使用・耐熱性、耐光性が非常に強い |
| 色調 | 黒~褐色 |
| 食品への表示例 | イカスミ色素、イカ墨 |
| 用途 | ・パン製品・麺類・菓子類・パスタソース |
水や油に溶けにくいため、用途を検討する必要があります。
ウコン色素
ウコン色素の概要は次のとおりです。
| 定義 | ・ウコン (Curcuma longa L.) の根茎から得られた、クルクミンを主成分とするもの・食用油脂を含むことがある |
| 分類 | 既存添加物/食品添加物公定書 |
| 特徴 | ・アルカリ性・赤褐色・水への溶解性は低い・pHや熱に対しては安定・耐光性がやや弱い・金属イオンとの共存で色が暗くなる |
| 色調 | 黄色 |
| 食品への表示例 | ウコン色素、ターメリック色素、着色料(ウコン)、着色料(クルクミン) |
| 用途 | ・沢庵などの漬物・栗のシロップ漬け・グミなどの菓子類・和菓子など |
光に対する安定性がやや低いため、透明な容器での保管は不適です。
天然色素を含む添加物の製造基準
この章では天然色素を含む添加物の製造基準について、第10版食品添加物公定書を元に紹介します。
添加物一般
添加物一般を製造する際の製造基準は、下記の通りです。
【添加物を製造または加工する場合】
製造や加工に必要不可欠な場合以外は、下記の物質を使用しないこと
- ・酸性白土
- ・カオリン
- ・ベントナイト
- ・タルク
- ・砂
- ・ケイソウ土
- ・二酸化ケイ素
- ・炭酸マグネシウム
- ・上記に類似する不溶性の鉱物性物質
- ・特定牛の脊柱
【添加物の製剤について】
・添加物*および食品**以外のものを使用しないこと
*法第10条に基づき指定されたもの、天然香料、一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものおよび既存添加物名簿に記載されているものに限る
**いずれも法第11条第1項に基づき規格が定められているものにあってはその規格に合うもの、水にあっては食品製造用水に限る
【組換えDNA技術で得られた微生物を利用する場合】
・厚生労働大臣が定める基準に適合する方法で行うこと
【微生物を用いて酵素を製造する場合】
・非病原性の培養株のみを用いること
・毒素を産生する可能性のある培養株を用いる場合は、精製の過程で毒素を除去すること
製造のパターンに応じて対応が異なるため、注意が必要です。
ウコン色素などの抽出物
ここでは抽出物に関連する規定を紹介します。
・下記に掲げる物質を製造、加工する場合は、太枠内に一覧で示した物質を(抽出などの製造工程で)使用しないこと
| ウコン色素、オレガノ抽出物、オレンジ色素、カラシ抽出物、カンゾウ抽出物、カンゾウ油性抽出物、クチナシ黄色素、クローブ抽出物、香辛料抽出物、ゴマ油不けん化物、シソ抽出物、ショウガ抽出物、精油除去ウイキョウ抽出物、セイヨウワサビ抽出物、セージ抽出物、タマネギ色素、タマリン ド色素、タンニン(抽出物)、トウガラシ色素、トウガラシ水性抽出物、ニガヨモギ抽出物、ニンジンカロテン、ローズマリー抽出物及び天然香料 |
使用してはならない物質一覧(太枠)
| 亜酸化窒素、アセトン、エタノール、グリセリン、酢酸エチル、酢酸メチル、ジエチルエーテル、シクロヘキサン、ジクロロメタン、食用油脂、1,1,1,2-テトラフルオロエタン、1,1,2-トリクロロエテン、二酸化炭素、- 1031 – 1 -ブタノール、2-ブタノール、2-ブタノン、ブタン、1-プロパノール、2-プロパノール、プロパン、プロピレングリコール、ヘキサン、水、メタノール |
・下記の(抽出物質については)表の通り、容量基準を超えて残存しないよう使用すること
| 対象物質 | 規定 |
| メタノール、2-プロパノール | 50µg/g |
| アセトン | 30µg/g |
| ジクロロメタン、1,1,2-トリクロロエテン | 合計量が30µg/g |
| ヘキサン | 25µg/g |
製造前に、該当するものがないか確認しておくことが大切です。
天然色素を含む食品添加物の指定等について
この章では、天然色素を含む食品添加物の指定等について解説します。
基本的な考え方
食品添加物の指定等では、安全性と有効性について科学的な評価が求められます。
【安全性】
要請された使用方法において確認がなされること。
【有効性】
下記のいずれかに該当する有効性を示すこと。
- 食品の栄養価の保持
※2)に当たる場合や、通常の食事の中で重要度が低い場合は、栄養価を意図的に低下させることも、正当と判断される場合がある - 特定の食事が必要な消費者が用いる食品について、これを製造する際に必要な原料や成分の供給
※疾病の治療やその他の医療効果を目的とする場合は除外 - 食品の品質保持、あるいは安定性の向上
- 食品の味覚、視覚等の感覚刺激特性の改善
- 食品の製造、加工、調理、処理、包装、運搬又は貯蔵の過程での補助的な役割
食品の健康影響評価は、内閣府食品安全委員会で実施されます。
参考:厚生労働省|食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針
食品添加物の指定等の流れ
食品添加物の指定等を受ける基本的な流れは、次のとおりです。
- 厚生労働大臣宛に要請書を提出する
- 安全性に関する資料等を基にした、食品健康影響評価の実施(内閣府食品安全委員会)
- 2.の結果をふまえ、薬事・食品衛生審議会において審議(厚生労働省)
- 3.の終了後、厚生労働大臣宛に答申を実施
- 薬事・食品衛生審議会の答申をふまえ、「食品衛生法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 23 号)」の改正等を実施(厚生労働省)
食品健康影響評価や薬事・食品衛生審議会の中で必要な場合は、資料の追加提出が必要なこともあります。
一連の流れの中では、要請された添加物について安全性および有効性が慎重に検討されます。
なお、提出する要請書には、成分規格案や使用基準案などの資料を添付しなければなりません。提出資料については、次の見出しを参考にしてください。
参考:
厚生労働省|食品添加物の指定等の流れ
厚生労働省|食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針
提出資料
申請時に提出する資料の概要は、次のとおりです。
【成分規格案】
要請書に成分規格案を添付することを原則とする。
【使用基準案】
・当該食品添加物の使用対象食品、使用量、使用方法等を限定する必要がある場合に添付
・使用基準の改正を要請する場合は、下記を添付する
- 当該食品添加物の使用基準
- 要請する使用基準改正案の対照表
【概要書】
下記に示す8項目について、概要を簡潔に記載します。
| No. | 項目、求められる資料 | 記載すべき内容 |
| 1 | 名称および用途について | 【名称】・一般名(和名及び英名)、化学名(IUPAC 名に準拠)【用途】・国内や諸外国での使用状況・コーデックス委員会で規定された用途 |
| 2 | 起源または発見の経緯について | ・開発された時期や国、食品添加物の使用の経緯等 |
| 3 | 諸外国における使用状況について | ・諸外国における許可状況・具体的な使用食品、使用基準、成分規格等・コーデックス委員会等の国際機関における使用基準や成分規格 |
| 4 | 国際機関等における安全性評価について | ・JECFA 等の国際機関、諸外国等における安全性評価の結果の概要 |
| 5 | 物理化学的性質および成分規格について | ・食品添加物公定書の通則、一般試験法等を参考に、適切な方法で試験した結果に基づいた結果・構造式や分子量など、全14項目について記載 |
| 6 | 使用基準案について | ・使用基準を設定する必要がある場合や、設定の必要がない場合、使用基準の改正の際には、他の資料を元に、その根拠を明らかにする |
| 7 | 有効性について | ・用途ごとに期待する効果があることを示す試験を行う。似た用途の既存の添加物がある場合は、効果を比較する・食品中での安定性に関する試験を行う。安定でない場合は、分解物の種類や生成程度について検討・食品中の主要な栄養成分に与える影響について検討 |
| 8 | 安全性について | ・「添加物に関する食品健康影響評価指針」にしたがい、食品健康影響評価に必要となる情報を示す |
品質や安全性、有効性が疑われる資料については、資料の信頼性等にかかわらず提出しなければなりません。
参考:厚生労働省|食品添加物の指定及び使用基準改正 要請資料作成に関する手引
天然色素を製造、指定申請する際のポイント
この章では、天然色素を製造して申請する際のポイントについて解説します。
安全性を担保する
天然色素は食品添加物に分類されるため、製造等には第10版食品添加物公定書に従う必要があります。
下記の観点から、添加物の製造などには、安全性を確保することが重要です。
厚生労働省の「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針」において「食品添加物は、人の健康を損なうおそれがなくかつその使用が消費者に何らかの利点を与えるものでなければならない」と明記されていること、指定申請後は食品健康影響評価が実施されることから、安全性は非常に重視されています。
そのため天然色素の製造や指定申請の際は安全性を第一義とし、科学的根拠を提示できることがポイントです。
有効性を証明する
食品衛生法上、食品添加物として扱われる天然色素の製造、指定申請の際は、有効性について科学的根拠を示さなければなりません。
食品の栄養価や品質保持、安定性の向上、製造、運搬などの際に役立つなど、示したい機能の有効性を証明することで、申請後の流れがスムーズになります。
まとめ:天然色素の製造、指定には安全かつ有効であることが重要
天然色素はいわゆる天然着色料であり、食品衛生法上は食品添加物に分類されます。そのため、製造などを行う際は、関連する法律や製造基準、規格などに従うことが大切です。
添加物指定の際には、安全性や有効性を明らかにした資料をもとに、健康への評価や有効性の審議がなされた後、食品衛生法施行規則が改正されます。
製造や指定申請のポイントは安全性と有効性を明確に示すことであり、曖昧な点がないよう注意が必要です。
天然色素の特性や国の食品添加物に対する考え方を押さえることで、効率的に事業に取り組めます。
一覧へ戻る