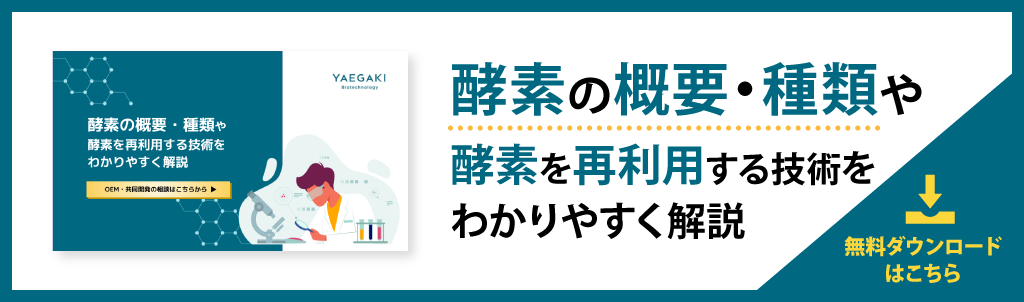乳酸菌は本当に酸素に弱い?特徴や効果についてわかりやすく解説!
人体に良い影響を与えてくれる乳酸菌は「善玉菌」とも呼ばれていて、ブドウ糖や乳糖を分解して乳酸を作り出す「乳酸発酵する性質」がある細菌の総称です。
乳酸菌が増殖しやすい環境を整えることで乳酸発酵が促進されるため、発酵食品の味が美味しく変化したり、長期間保存性が高まります。
他にも乳酸菌を人間の体内に取り入れることで、腸内環境の改善や免疫システムのサポート、アレルギーの抑制など多くの効果に繋がります。
しかし乳酸菌は酸素に弱く、生育環境に酸素は必要ないとされています。
本記事では乳酸菌は酸素に弱いのか、特徴や増殖する条件、発酵する条件や仕組み、乳酸菌の効果についてわかりやすく解説します。
乳酸菌の活用を検討している企業は、ぜひ参考にしてください。
※研究開発コラムは微生物を活用した研究開発において参考になるトピックを集めたもので、全てのテーマについて当社が研究開発を実施しているわけではございません。
目次
乳酸菌の特徴
乳酸菌は人間の健康に良い細菌として広く知られていますが、詳しい特徴を知る方は少ないでしょう。
そこでここからは乳酸菌の特徴について、詳しく解説します。
発酵能力がある
乳酸菌には、糖類を発酵して有機酸(主に乳酸)を生成する能力があります。
食品加工においてこの乳酸発酵を利用することで、食品や飲み物が酸性になり、チーズやヨーグルトなどの発酵食品が生まれます。
発酵の過程で独特の風味が生まれることもあり、これまでの食品を異なる方向から活かすことも可能です。
腸内環境の改善や免疫システムをサポート
乳酸菌は腸内細菌叢のバランスを善玉菌を増やし、悪玉菌の増殖を抑制することで改善することが可能です。
善玉菌が増えれば代謝がよくなるほか、腸の運動が促進されスムーズな排便に役立ちます。
また腸内環境が良好になることで免疫システムが改善し、アレルギーの抑制や風邪の予防に繋がるともされています。
多くの種類がある
乳酸菌は糖から乳酸を作る微生物の総称であり、自然界のさまざまな場所にあります。
実際に命名・提案されている乳酸菌は、現在、26属・381種・50亜種も存在しているとされています。
代表的な乳酸菌には、ヨーグルトに使用するブルガリア菌やサーモフィラス菌があり、乳酸菌として知っている方も多いでしょう。
乳酸菌の特性や理想の環境は種類により異なるため、まずは活用したい乳酸菌ならではの特徴を知ることが大切です。
参考:辨野義己論文 | プロバイオティクスとして用いられる乳酸菌の分類と効能
乳酸菌が活発に増殖するための条件
乳酸菌の発酵に必要なのは、適温の環境・酸素のない状態・炭水化物(基質)です。
ここからは乳酸菌が増殖する環境を整えるため、条件の内容を詳しく解説します。
適切な温度が保たれている
乳酸菌は温暖な環境を好むため、一般的に温度は30℃前後が最適とされています。
ただし異なる乳酸菌の種類によって最適な温度には違いがあるため、増殖させる生育環境の温度管理には注意が必要です。
例えばヨーグルトの製造で利用されるラクチス菌の理想的な培養温度は30℃ですが、ブルガリア菌は37〜45℃と高めです。
また乳酸菌の増殖には、生育環境の適切な温度だけでなく湿度も重要です。
湿度が高すぎる環境になると他の微生物の発生が促進され、乳酸菌の生育を妨げる可能性があるため注意する必要があります。
生育場所に酸素が少ない
わずかに例外はありますが、ほとんどの乳酸菌は通性嫌気性菌であり、酸素が無い状態だけでなく酸素の存在下でも増殖することが可能です。
しかし酸素が豊富な条件下では、他の微生物と競合する可能性があります。
そのため酸素がない生育場所のほうが、乳酸菌はより発酵を促進する力が高まるといえます。
乳酸菌を活用して発酵を促進させたいときは、なるべく酸素を減らしましょう。
炭水化物が豊富に存在する
乳酸菌は発酵の過程で糖分を代謝して有機酸を生成するため、特にエネルギーを生成させるために栄養素として炭水化物を好みます。
そのため、例えば乳糖(牛乳中の糖分)や果糖(果物中の糖分)など、糖分を含む基質が存在することが発酵するために必要です。
また栄養素としてビタミン、ミネラルを適切に提供することも、乳酸菌を増殖させるために必要です。
嫌気性の細菌と好気性の細菌の違い
乳酸菌は酸素に弱いとされることもありますが、実際の働きを知るにはまず嫌気性と好気性の細菌について知る必要があります。
そこでここからは通性嫌気性と通性好気性との違いや、それぞれの代表的な細菌についてわかりやすく解説します。
通性嫌気性とは
通性嫌気性の細菌は、通常は酸素が少ない状況や全くない状況どちらでも活発に増殖します。
通性嫌気性の細菌であれば酸素がある状態で死滅することはありませんが、腸内や発酵食品の中など、酸素が制限された環境で活発に活動します。
通性嫌気性の細菌として代表的なものは、乳酸桿菌、大腸菌です。
なお、偏性嫌気性の細菌は、大気レベルの酸素がある環境では死滅してしまいます。
偏性嫌気性の細菌として代表的なのは、ビフィズス菌、バクテロイデスです。
好気性とは
好気性・微好気性の細菌は、少量の酸素があれば増殖できます。
通気性の高い食品や容器内で見られることが多く、酸素がある状態を好むのが特徴です。
好気性の細菌として知られているのは、胃がんの原因菌などで知られるピロリ菌です。
なお、偏性好気性の細菌は酸素がない環境だと生育できず死滅してしまいます。
偏性好気性の細菌として代表的なのは、結核菌、酢酸菌などです。
通性嫌気性の乳酸菌は酸素呼吸しないとどうなるのか?
多くの乳酸菌は一般に通性嫌気性であり、酸素がない、もしくは少ない状態で活発になります。
そのため酸素に弱いとはいえないものの、乳酸菌にとって酸素がない、もしくは少ない状態は理想といえるでしょう。
ここからは酸素がない環境で、酸素呼吸をしてない乳酸菌の状態について解説します。
乳酸発酵する
乳酸菌は酸素呼吸ができなくなると代謝の主要な経路として乳酸発酵を選択し、糖分を代謝して乳酸を生成します。
発酵により乳酸が多く蓄積されれば、酸素が存在しない環境でもエネルギーの生産が可能です。
酸性環境を維持して増殖を促進させる
乳酸発酵で生成された乳酸は生育環境を酸性にして他の微生物の成長を抑制するため、優位に増殖できます。
酸性環境を維持すれば腸内や発酵食品中などに乳酸菌が増加するため、効率的に乳酸菌の長所を伸ばせます。
食品を発酵させる
乳酸菌が食品を発酵させるプロセスは乳酸発酵の一環であり、酸素が少ない、もしくはない状況下で起こります。
例えば、乳製品のヨーグルトやチーズ、発酵食品の漬物やキムチ、しょうゆや味噌をはじめとした醸造食品などが乳酸発酵に該当します。
酸素が少ない環境を利用して食品を発酵させれば、味や香りが向上するだけでなく、栄養価も変化します。
また酸性条件下での発酵により食品が雑菌による汚染・腐敗から守られ、安定して長期間保存することも可能となります。
乳酸菌6つのプラス効果
乳酸菌を人間が体に取り入れると、プラスの効果が期待できます。
ここからは参考として、乳酸菌が人間の体に与えるメリットを6つ解説します。
乳酸菌の働きを活かすため、ぜひ参考にしてください。
腸内環境の改善
乳酸菌は腸内の善玉菌(有益な菌)の増加を促進し、悪玉菌(有害な菌)の増殖を抑制します。
良好な腸内環境は、消化や栄養吸収の改善に寄与し、全身の健康にも影響を与えてくれます。
消化器官の健康促進
乳酸菌は消化器官での善玉菌の増加を支援し、食物の分解や吸収を助けます。
胃腸の健康が促進され、消化不良や便秘などの問題を緩和する可能性があります。
免疫システムのサポート
乳酸菌は免疫システムを活性化させる効果があります。
理由は善玉菌の増加が、免疫細胞の活性化や免疫応答の改善に寄与するからです。
腸内の健康な状態が免疫システム全体の調整に影響を与え、感染症や炎症に対する防御機能を向上させてくれます。
抗菌作用
乳酸菌は酸性条件を作り出すことで、他の微生物の増殖を抑制します。
これにより、食品や腸内での有害な微生物の繁殖を防ぎ、健康を維持します。
アレルギーを抑制できる
腸内環境の改善がアレルギー反応の抑制に影響することから、一部の研究によれば乳酸菌の摂取がアレルギー症状の軽減に寄与する可能性があるとしています。
そのため、花粉症で毎年悩んでいる方にとって乳酸菌を摂るメリットは大きいといえます。
参考:株式会社明治研究本部|乳酸菌の免疫調節効果に関する研究
食品の風味改善や保存が可能
発酵食品の製造過程において、乳酸菌は食品の風味や保存性を向上させます。
ヨーグルトやキムチでは乳酸菌による発酵が行われており、食品が豊かな風味を持つようになります。
また保存性が向上することから、製造場所から遠く離れている場所でも腐敗することなく、食べることが可能となります。
まとめ:乳酸菌は酸素に弱くないが増殖や発酵しやすい環境を整えることが重要
乳酸菌は酸素に弱いとされることもありますが、酸素が苦手かどうかは乳酸菌の種類により異なります。
乳酸菌のなかには、大気レベルの酸素で死滅する偏性嫌気性菌と酸素の有無にかかわらず生息できる通性嫌気性菌があります。
多くの乳酸菌は通性嫌気性菌であり、酸素が無い環境でより活発に乳酸溌酵をするため、酸素を少なくすることが重要です。
酸素がなく適切な温度や湿度で管理されていて、栄養素が豊富な環境であれば通性嫌気性菌の乳酸菌の長所を伸ばせます。
ぜひ本記事の内容を参考にしていただき、乳酸菌の増殖や乳酸発酵をしやすい環境を整えてください。
弊社は、微生物の培養や発酵に関する研究開発技術の知見を活かし、新たなモノづくりに挑戦する企業様、研究機関様とのコラボレーションを推進しています。気になる方は、ぜひ下のボタンからお問い合わせください。
一覧へ戻る