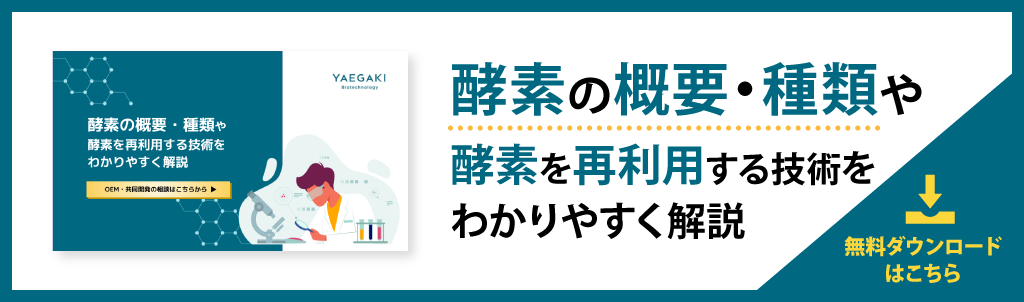タンサ(短鎖)脂肪酸の効果とは?腸活につながる食べ物も紹介
近年は腸活に役立つさまざまな栄養素が発見され、積極的に取り入れられるようになりました。
タンサ(短鎖)脂肪酸は手軽に摂取できるうえ、健康に役立つ栄養素として注目を集めるようになりました。一方、タンサ脂肪酸には複数の種類があり、それぞれ特徴が異なることから何にどのような効果があるのか気になっている方も多いでしょう。
そこで本記事では、タンサ脂肪酸について解説します。タンサ脂肪酸の種類や効果だけでなく、腸活につながる食べ物についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
※研究開発コラムは微生物を活用した研究開発において参考になるトピックを集めたもので、全てのテーマについて当社が研究開発を実施しているわけではございません。
目次
タンサ(短鎖)脂肪酸とは
タンサ脂肪酸をはじめとする脂肪酸は油脂を構成する成分の一種であり、通常数個~数十個の炭素が鎖状につながった構成をしています。
このような脂肪酸のうち、炭素数が6個以下のものがタンサ(短鎖)脂肪酸と呼ばれます。
タンサ脂肪酸は、大腸でビフィズス菌や酪酸菌などがオリゴ糖や食物繊維を取り込んだ際に生産する代謝物質のひとつです。
産生されたタンサ脂肪酸は、そのまま大腸に吸収され、大腸粘膜組織に取り込まれます。一部は血流に乗って全身に運ばれ、腎臓や肝臓など、さまざまな部位に運ばれます。
そしてタンサ脂肪酸は腸管上皮のエネルギー源になったり腸内環境を整え、免疫力を向上させる効果が期待できます。そのため、現在では腸活においても有効な成分として注目されています。
代表的なタンサ(短鎖)脂肪酸
腸内細菌により産生されるタンサ脂肪酸に該当する成分は、主に酢酸・プロピオン酸・酪酸の3種類です。これらは揮発性のタンサ脂肪酸で、VFAとも呼ばれます。本章では、それぞれの成分について解説します。
酢酸
酢酸はタンサ脂肪酸のうち、一般的に哺乳動物の大腸にもっとも多い成分です。
酢酸は酢に多く含まれているイメージがありますが、酢を摂取しても小腸で吸収され、大腸にまで届くのはごくわずかです。実際に大腸にある酢酸のほとんどは、ビフィズス菌などさまざまな腸内細菌が産生したものです。
大腸の酢酸には近年明らかになった新たな機能として、免疫グロブリンの一種である粘膜IgA(免疫グロブリンA)の産生を促進する効果があり、さらに一部の病原性大腸菌に結合するIgAが増加する事で腸内フローラを制御する可能性が示唆されています。また粘膜IgAの増加は免疫力を強化することで感染症予防効果が期待できます。
京都大学などによる研究では、脂肪細胞の表面に酢酸と結合するタンサ脂肪酸の受容体があり、この受容体が過剰となった酢酸などにより活性化する事でエネルギーの蓄積が抑制されエネルギー消費に傾き、肥満を抑制する事が示されています。
また大腸の上皮細胞にできた傷を修復し、健康な状態を保つうえでも役立つ事も報告されています。
参考:
腸内細菌からのメッセージ 短鎖脂肪酸の生理的役割|坂田隆
酢酸の腸内免疫制御に関する研究成果が科学雑誌「Nature」に掲載!(2021年7月15日株式会社ダイセル プレスリリース)
腸内細菌による宿主のエネルギー恒常性維持機構の解明-短鎖脂肪酸受容体GPR43活性化は脂肪の蓄積を抑制し肥満を防ぐ-
酪酸
酪酸は、酪酸菌が水溶性の食物繊維や糖質を代謝して産生するタンサ脂肪酸の一種です。酪酸は大腸の働きを活発化させるエネルギー源になる成分であり、他の成分より優先的に使われます。
さらに酪酸は免疫細胞の司令塔であるT細胞の暴走を抑制する、制御性T細胞の比率を増やし、免疫機能を正常に保つ効果がある成分として注目されている点も特徴です。
酪酸菌などの摂取により、酪酸が大腸で積極的に作られると制御性T細胞の比率が増えるため、免疫機能のバランスを維持できます。
ただし、酪酸を産生する酪酸菌はぬか漬けなど一部の食材からしか摂取できません。そのため、効率的に摂取するにはサプリメントなどで補う必要があります。
参考:腸内細菌が作る酪酸は制御性T細胞を誘導して、腸管の炎症を抑制する|東京大学医科学研究所
プロピオン酸
プロピオン酸は腸内細菌が糖質や水溶性食物繊維から産生するタンサ脂肪酸の一種であり、主にはチーズなどに含まれる成分です。
プロピオン酸は腸内細菌が産生した後に体内に吸収されると肝臓で代謝され、コレステロールを抑制する効果があります。
また、近年では妊娠中の母親がプロピオン酸を摂取すると、胎児の肥満を抑える効果も期待されています。さらに授乳期に母親がプロピオン酸を摂取する事で、乳児の気管支喘息(アレルギー性気道炎症)を抑制する可能性も示唆されています。
参考:
チーズを美味しくする少数派微生物 プロピオン酸菌(北海道立総合研究機構)
妊娠中の食物繊維摂取は胎児の代謝機能の発達を促し、 出生後、子の肥満になりにくい体質をつくる|国立研究開発法人日本医療研究開発機構
プロバイオティクス細菌による血中脂質改善作用|近藤しずき・清水金忠
授乳期の短鎖脂肪酸が子の気管支喘息を改善する-プロピオン酸-GPR41経路を介した喘息抑制メカニズムの解明-
タンサ(短鎖)脂肪酸の効果
タンサ脂肪酸は、さまざまな効果が期待できる成分です。本章では、タンサ脂肪酸の代表的な効果について解説します。
肥満を防ぐ
タンサ脂肪酸は、肥満を防止する効果が期待できる成分です。タンサ脂肪酸には交感神経を活性化させ、基礎代謝を高める効果があります。
基礎代謝が高まれば脂肪の燃焼が促進されるため、肥満の抑制が可能です。
加えて、体内に吸収されたタンサ脂肪酸が血流に乗って全身を巡ると、脂肪組織に栄養が取り込まれないようにします。その結果、脂肪の蓄積が抑制され太りにくい体になるといえます。
血中コレステロールを低下させる
血中コレステロールの低下も、タンサ脂肪酸に期待できる効果です。
北海道大学で行われた原博博士のラットを使った研究では、タンサ脂肪酸は肝臓におけるコレステロールの合成を強力に阻害し、血中コレステロール濃度を低下させる効果があることが発見されました。
特に、発酵性が高い水溶性食物繊維から産生されたタンサ脂肪酸は、高いコレステロール抑制効果があるとされています。
タンサ脂肪酸を適切に摂取すれば、悪玉コレステロールによって発生する動脈硬化などの予防につながります。
参考:プレバイオティクスから大腸で産生される短鎖脂肪酸の生理効果|原博
免疫力を高める
タンサ脂肪酸の一種である酢酸や酪酸は腸のバリア機能を保持し、粘膜を修復する作用があります。これにより、体内の免疫機能を正常化し、腸管から体内深部への病原菌の侵入を防ぐ効果が期待できます。
タンサ脂肪酸を積極的に摂取すれば、感染症対策につながるでしょう。
また、タンサ脂肪酸は腸内の悪玉菌の増殖を抑制・殺菌する効果があります。特に酢酸は殺菌効果が高く、腸内で善玉菌が活性化するきっかけを作れます。
参考:腸内細菌由来短鎖脂肪酸における宿主エネルギー代謝機能制御|清水秀憲、北野隆司、木村郁夫
認知機能の低下を抑制する
タンサ脂肪酸は、認知機能とも関連している成分として注目されている点も特徴です。
一般社団法人Jミルクの発表では、タンサ脂肪酸や中鎖脂肪酸には認知機能の低下を抑制する効果があるとされています。
特にタンサ脂肪酸の一種である酪酸は認知機能の低下を防ぐ効果が高く、1日当たり約180mg摂取すれば、認知機能の低下リスクを15%も低下させることがわかりました。
一般社団法人であるJミルクは、タンサ脂肪酸や中鎖脂肪酸を摂取するうえでも、牛乳や乳製品の積極的な摂取を推奨しています。
参考:牛乳・乳製品に特徴的に含まれる「短鎖脂肪酸」「中鎖脂肪酸」と認知機能との関連|一般社団法人Jミルク
タンサ(短鎖)脂肪酸を増やす方法
タンサ脂肪酸は健康に多大なメリットを与える成分です。しかし、タンサ脂肪酸を含んでいる食品は限られており、直接的な摂取は容易ではありません。
そこで本章では、タンサ脂肪酸を効率的に摂取する方法について解説します。
ビフィズス菌を摂取する
タンサ脂肪酸は牛乳・乳製品・ぬか漬けなどに含まれていますが、大量に摂取するのは簡単ではありません。
しかし、タンサ脂肪酸を産生してくれる菌類を腸内で増やせば、体内でタンサ脂肪酸を増やせます。
タンサ脂肪酸を産生する菌類の代表は、ビフィズス菌です。ビフィズス菌は乳製品や乳性飲料などに多く含まれているため、ヨーグルトや乳性飲料などを摂取すれば、結果的にタンサ脂肪酸の産生量を増加できます。
また、ビフィズス菌を大腸まで届けられるサプリメントの摂取も有効的な方法です。
なお、酪酸菌にもビフィズス菌と同様にタンサ脂肪酸を増やす効果が期待できます。
しかし酪酸菌はぬか漬けなどのような一部の食材にしか含まれていないため、サプリメントでの摂取が効果的です。
食物繊維を摂取する
タンサ脂肪酸を増やす菌類を摂取するなら、同時に菌類のエサになる食物繊維も摂取しましょう。
タンサ脂肪酸は、菌類が水溶性食物繊維を発酵することによって産生する成分です。食物繊維を増やすことにより菌類が活発化すれば、より多くのタンサ脂肪酸の産生を実現できます。
水溶性食物繊維は野菜・果物・海藻類などに多く含まれており、サプリメントからでも摂取できます。ビフィズス菌を豊富に含んだ食品と組み合わせれば、より効果的にタンサ脂肪酸を増やせます。
また、食物繊維だけでなく、オリゴ糖も腸内の菌類の活性化につながる成分です。オリゴ糖はきなこ・バナナ・たまねぎ・はちみつなどに多く含まれており、特にきなこは含有量が高いことで知られています。
食物繊維と一緒に摂取し、効率的にタンサ脂肪酸を増やしましょう。
タンサ(短鎖)脂肪酸の今後
昨今は健康のために腸内環境を整え、腸内の善玉菌にアプローチする腸活がトレンドです。
腸活においてはさまざまな菌類や成分が注目されていますが、タンサ脂肪酸はそのなかでも大きな注目を集めています。
腸活を推進する多くの企業においても、タンサ脂肪酸は注目されており、自社事業にも積極的に取り入れられています。
例えば、大手食品メーカー江崎グリコ株式会社では「タンサ活」と称し、タンサ脂肪酸の積極的な摂取を推奨しています。
今後も多くの企業で、タンサ脂肪酸の活用が進められるでしょう。より新しい活用方法が発見されることにも期待が高まっています。
参考:菌活のトレンド「タンサ活」って何?太りにくい体を作る食事の法則とは(アスレシピ)
まとめ:タンサ脂肪酸は腸活に欠かせない存在
腸内で作られるタンサ脂肪酸には酢酸・酪酸・プロピオン酸の3種類があり、健康に有益なさまざまな効果をもたらします。
タンサ脂肪酸を十分に摂取すれば、肥満防止・免疫力の向上・血中コレステロールの低下などの効果が期待できます。
近年、ブームとなっている腸活においても、タンサ脂肪酸は注目されるようになりました。
多くの企業でもタンサ脂肪酸を活用した事業が展開されるなど、ビジネスにおいてもタンサ脂肪酸の存在感は増しています。
健康増進・ビジネス双方の観点において、タンサ脂肪酸は今後も注目を集めるでしょう。
一覧へ戻る